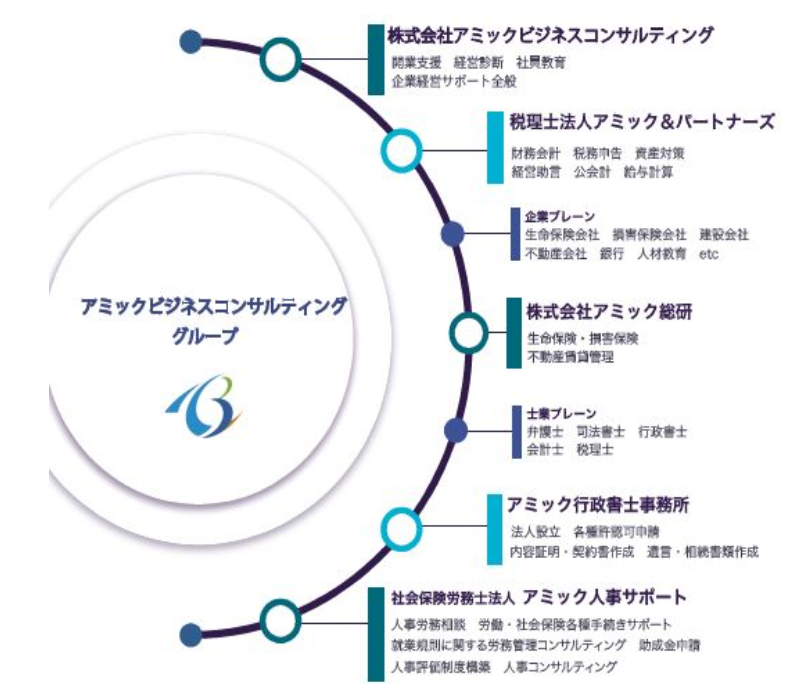一般診療所は、年間で7768件開設、6982件が廃止されており、(2018年10月〜2019年9月の情報。参考:令和元(2019)年医療施設(動態)調査)年々その数は微増しています。さらに、継承を含む「医療法人の合併」も2000年代中盤の10件前後から2017年には年間30件を超えるなど増加傾向にあります。
当記事では、そんな継承の実情を明らかにすべく、2020年4月に、他人からの継承にて開業した「医療法人 みなとクリニック」の田中崇洋医師にインタビュー。
・継承開業をするにあたって利用したサービス、サイト
・継承後に患者さんを増やした方法
などを紹介していただきました。
クリニックの承継案件多数!
CLIUS・クリニック開業ナビでは東京・大阪を中心に、クリニックの承継案件、医療モール、居抜き物件など、様々な物件形態をご紹介しています。一般には非公開の物件情報も続々掲載増加中です。もしご希望の物件が見つからない場合には、専任のコンシェルジュによる現地調査も無料で行います。
詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。
田中崇洋医師の経歴を教えてください
まず2010年、地元の九州大学医学部を卒業した後、縁もゆかりもない福井県の杉田玄白記念公立小浜病院で研修医として働き始めました。遠回りして医学部に入ったため、できるだけ早く現場で通用するスキルを身に付けたいと思い、医療過疎地で研修することが近道だろうと考えその病院を選びました。
福井県は全国的にも救急医療が発達した地域で、素晴らしい指導医のバックアップを受けつつ、初日から救急外来を担当するほど現場意識が高い病院だったと記憶しています。そこではその後の専門となる一般・消化器外科の手術だけでなく、乳がんなど乳腺外科の手術、場合によっては肺や呼吸器の手術を沢山執刀させてもらったり、抗がん剤治療も担当するなど、臨床医として幅広い経験をさせてもらいました。
医療過疎地の病院で医師が少なかったため、研修医時代から積極的に戦力として臨床に携わらせてもらうという経験を、同病院で2013年まで積ませてもらいました。
その後は、元々指導してくれていた先生の推薦もあり、京都府・三菱京都病院に移りました。
京都の病院は、もともといた福井県・杉田玄白記念公立小浜病院よりも医師数は約2倍、病床数は半分だったので、後期研修医2年目の自分には前の病院と同じようには執刀させてもらえないのではないかと心配していました。
しかし、これまでの実績を評価していただき、異動後初めての執刀手術が腹腔鏡下低位前方切除術、同年に腹腔鏡下胆管空腸吻合術を自分のたてた手術手順で執刀させてもらうなど、消化器外科医として定例手術と緊急手術に専念する日々を送らせてもらいました。また、小さな病院ながらも、緩和ケア内科、腫瘍内科の先生も在籍していたので、本当に幅広い分野の勉強につながったと思います。その環境がとてもありがたく、結果的に7年ほど働きました。
開業を決めたきっかけを教えてください
先ほど話したように、ありがたいことに研修医1年目からたくさんの手術に関わり、さまざまな経験をさせていただきましたが、2017年の30半ばになったころ、年齢的にも自身のキャリアを見つめ直したことがきっかけです。
前述したようになるだけ早くスキルを身につけようと走り続けた結果、気付いたらかなり多くの執刀経験を積み海外学会などでも口演させてもらい、自分の思い描いていた以上の目標を達成できていました。
その一方で毎年同じ日常の繰り返しとなっているようにも感じ、異動などを意識するようになりました。
私は医局には属していないものの、京都大学の関連施設で勤務することのできるグループに属していましたので異動先のリサーチをしましたが、勤務環境的に所属していた病院を超える施設が見つからずにいました。そうして全く別な道も模索する中、もともと母方の祖父や父が経営者だったこともあり自分でクリニックを運営する側になりたいと徐々に思うようになり、開業を決意しました。
ゼロからの開業ではなく、継承開業に至った経緯は?
具体的に開業準備をする数年前から、「クリニックの開業」に関する情報収集はしていました。
当時読んでいた「診療所経営の教科書【第2版】〈院長が知っておくべき数値と事例〉」(2017 / 日本医事新報社 / 著・小松 大介、監修・大石 佳能子)という本は、特に勉強になりました。10年後の外来患者の傾向といったデータが詳しく書いてあり、団塊の世代が亡くなることに伴い外来患者が減少する未来についての記載などを見て「今後、新規で開業をするにはリスクが大きすぎる」と思いました。
これからのクリニック経営が難しくなるとすると、すでに患者さんを抱えているクリニックをM&A的に継承した方がいいだろうと考え、さらなる情報収集を始めました。
継承開業にあたって参考にしたサイト等を教えてください
全体的な情報収集は、Twitterで活動する医師アカウントから
開業全般に関する情報は、先に説明した本のほか、オンラインサロンやTwitterでも日々調べていました。特に、医師によるTwitterアカウントには、医師の本音や経営状況が赤裸々に載っているので非常に参考になりました。
Twitterで全国の開業医と繋がって、実際にクリニックの見学に行かせてもらったこともあります。そうした横のつながりや情報交換に助けてもらうことも多く、Twitterで培った関係性は侮れないと感じました。
具体的な譲渡案件は、リクルートメディカルキャリアから
継承案件については、開業の3年ほど前から時々見ていました。どういった継承案件があるのか知るために、譲渡先を探している人とマッチングできるサイトにはいくつか登録して問い合わせもしていました。
当院については、開業を決意し積極的に情報収集していたところ、登録していたリクルートメディカルキャリアの担当者からお電話をいただき、紹介してもらいました。みなとクリニックの事業継承を検討している医師はほかに何人もいたようでしたが、私が一番早くに伺ったからか、無事に譲渡が成立しました。
面接には、リクルートメディカルキャリアの担当者も同席してくれました。面接を受ける上で継承動機など様々聞かれましたが、準備し過ぎても不自然になるだろうと思い特にこれといって特に準備はしませんでしたが、来院数の推移や主なかかりつけ患者さんのキャラクターなどはこちらからはっきりと聞くようにしました。
>>株式会社リクルートメディカルキャリアの継承サービス「ヒキツグ」はこちら
クリニックの承継案件多数!
CLIUS・クリニック開業ナビでは東京・大阪を中心に、クリニックの承継案件、医療モール、居抜き物件など、様々な物件形態をご紹介しています。一般には非公開の物件情報も続々掲載増加中です。もしご希望の物件が見つからない場合には、専任のコンシェルジュによる現地調査も無料で行います。
詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。
継承開業で気をつけるべきことは?
経営に直結するお金の部分です。
譲渡案件の中には「無償譲渡」のものや、破格の値段のものがあります。継承開業を検討されている医師の方は、そのようなクリニックを魅力的に思うかもしれません。しかしそれらには、継承までのスケジュールが極端に短いことや、クリニックで抱える患者さんが非常に少ないなど、それなりのネガティブな理由があります。
目先のお金に惑わされず、継承開業のメリットを享受できるか案件かどうかも考えて検討してもらえれば幸いです。
さらに財務状況の確認も大事ですので、ときには専門家の意見も交えて確認しておくことをおすすめします。
継承後に法人の借入金が明らかになった、などのトラブルを聞いたこともありますので、継承前のデューデリジェンスは必須です。
私は、譲渡を検討しているクリニックの経営情報はできるだけ税理士の方にも見てもらっていました。幸いなことに私の場合は金銭面のトラブルもなく、前の院長がとても良い人だったこともあり、もともと提示されていた額より譲渡代金をさらに安くしてくださったり一部医療機器を継承前に新しくしてくれたりと、本当にありがたかったです。
継承開業のメリットを教えてください
私が感じたことで言うと、やはり、医療機器や建物などがすでに揃っているので、ゼロから始めるよりも低予算で開業できたことだと思います。
一方で、継承開業にあたって新しくしたところもあります。
継承時に新しくした点
・クリニックの改装
・紙カルテから電子カルテへ移行
・据え置き型からハンディ型のエコーへの買い換え
改装は継承後1ヶ月で院内薬局を廃止したこともあり、受付から診察室を隣接させること、診察室と検査室、処置室を裏動線でつなげること、スタッフルームの増設を重点的に行いました。継承前は受付と診察室の間に薬局があり、事務スタッフとの情報伝達がやりにくかったり、診察室と検査室が離れ過ぎていたなど様々な問題点がありましたが、改装することによってかなりのストレスが軽減されました。
さらにスタッフ間での情報伝達はインカムを取り入れてそれぞれの持ち場についたままやり取りができるようにもしました。
また、当院はもともと紙カルテでの運用をしていたので、私が継承して2ヶ月タイミングで電子カルテに変えました。レセコンはもともと使用されていたRCAを引き続き使っています。オンプレORCAからクラウドORCAには変えましたが、事務の方もあまり大きな違和感なく使ってくれていると思います。
参考:電子カルテとは? オンプレとクラウドの違い、導入費用、選定時期までを解説
その他に、もともと据え置き型のエコー(GE製)はあったのですが、ドップラーの機能が無かったのと、在宅患者の増加に伴い訪問診療時にエコーを使用する機会が増えることを見越して、すぐに持ち運びできるタイプのものに買い換えました。
コニカミノルタ社のSONIMAGE MX1α(ソニマージュ エムエックスワンアルファ)というポータブルエコーですが、据え置き型並みの画質と様々な機能を備えており、クリニック内外で使用できる優れものです。
また、紙カルテのままだと、在宅医療を行うために患者さんのファイルを探して用意し、持ち運ぶ必要がありますが、クラウド型カルテであれば、インターネット環境下のパソコン一台さえあればどの患者さんの診察にも対応できます。ポータブル型エコーも、患者さんのご自宅に持っていけるので、診察の幅が広がることにつながりました。
継承時の2020年4月は、在宅の患者さんは2名程度でしたが半年後には40名ほどに増え、現在も増え続けておりますので、クラウド型電子カルテもポータブル型エコーも、在宅医療を行うために必要な投資だったと改めて感じています。
在宅患者をどのように増やしましたか?
最初は、もともとかかりつけの患者さんで、徐々に来院が困難になってきた患者さんに対し「来院が難しければ訪問診療も対応します」と伝え、地道に患者数を増やしていきました。
そのほかは、在宅医療を手がけていく中で自然と訪問看護師さんや介護事業所とのつながりができたので、看護師さんや事業所に対して、自院が訪問診療を積極的にやっていることをアピールし、訪問診療を望んでいる患者さんを紹介してもらっています。
また、患者さんを併診してもらっている近隣の総合病院へ営業にも行きました。事前に地域連携室に連絡し「当院は24時間対応で訪問診療をしているので、近隣の患者さんで通院が困難な方がいらっしゃる場合は当院に教えてください」とお話ししたところ、徐々に認知されるようになり総合病院から在宅希望患者の紹介が来るようになりました。
さらに9月からは緩和医療専門医を持つ大学の同級生が副院長に就任し、がん末期で在宅緩和ケアが必要な患者さんの紹介が増えました。
訪問診療を手がけるクリニックは増えてきているように思えますが、医師複数名体制で積極的に困難症例を受け入れることは当院の大きな強みではないかと実感してきております。
半年ほどで在宅患者数を大きく伸ばすことが出来たのも、継承によって外来診療の基盤がしっかりとしていたことと、クリニックとしての認知度が30年近くかけてすでにあったからです。ゼロからの開業で外来も在宅も、となればこうはいかなかったと思います。
このように、継承してすぐに事業拡張に着手できるのも、継承開業のメリットだと思います。
特徴
対応業務
その他の業務
診療科目
特徴
対応業務
その他の業務
診療科目
この記事は、2021年3月時点の情報を元に作成しています。

取材協力 医療法人みなとクリニック 院長 | 田中 崇洋
九州大学医学部を卒業の後、杉田玄白記念公立小浜病院、三菱京都病院 消化器外科を経て、2020年4月に医療法人みなとクリニックを継承開業し院長へ就任。外科疾患、消化器疾患に対する治療に加えて、生活習慣病(高血圧症・脂質異常症・糖尿病など)をはじめとする内科疾患の治療を実践している。
他の関連記事はこちら

執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
他の関連記事はこちら