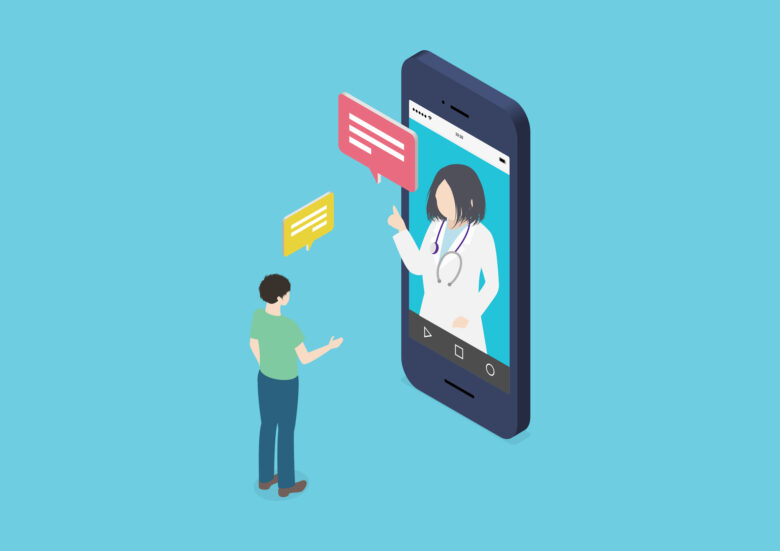
ここ数年、さまざまな分野において「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の重要性が叫ばれています。DXとは、デジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を目指す取り組みのことで、医療分野においてもこの言葉をよく耳にするようになりました。
医療分野においても同様で、「医療DX」という言葉を聞く機会も増えました。そんななか新たに登場した用語が「診療報酬改定DX」ですが、診療報酬改定DXとは具体的にどのようなDXなのでしょうか? 詳しく解説していきます。
診療報酬改定DXとは?
まずは、診療報酬改定DXについて説明します。
診療報酬改定DXとは、診療報酬改定に係る作業をDX化させることを意味します。「DX化」とはなにかというと、デジタル技術を活用して変革を目指す取り組みを推し進めることです。
では、「診療報酬改定に係る作業」とはなにかというと、改定された内容の告示から改定施行日までの間に、診療報酬改定に伴うシステムを反映させることを意味します。この作業をおこなうのは、電子カルテをはじめとする、診療報酬と紐づいているシステムを扱っているベンダーです。各ベンダーは、公開された資料を読み解きながら、自社のシステムのロジックに落とし込んで、システムに反映させるという作業を、改定施行日までに終わらせる必要があります。
公示および施行の日程は、2022年度の診療報酬改定に関してまでは、前者が3月、後者が4月とされてきました。つまり、公示から施行まで約1か月しかないなか、先に説明した作業を完了させなくてはならないということになりますが、それに加えて、改定施行日以降も、疑義解釈が通知されるたびに変更作業を重ねていかなければなりませんでした。
こうした状況を、デジタル技術を駆使して改善していく目的で掲げられた取り組みが、「診療報酬改定DX」だというわけです。
「診療報酬改定DX」は「医療DX令和ビジョン2030」の施策のひとつとして誕生した用語
「診療報酬改定DX」という用語が初めて使われたのは、2022年5月のことです。
同月、自由民主党政務調査会によって、医療のDX化・医療情報の有効利用を推進するための提言である「医療DX令和ビジョン2030」なる提言がなされましたが、この提言における施策のひとつとして、「診療報酬改定DX」が掲げられたのです。
「医療DX令和ビジョン2030」とは?
「医療DXビジョン2030」とは、2030年を見据えて、医療分野におけるDXを進めていこうという提言で、次の3点を骨格が骨格として掲げられています。
1. 全国医療情報プラットフォームの創設
2. 電子カルテ情報の標準化
3. 診療報酬改定DX
それぞれについて簡単に説明していきます。
全国医療情報プラットフォームの創設
医療情報や介護情報をクラウド間で連携させて、必要なときに必要な情報を入手できるようにする仕組みをつくろうというものです。これが実現すれば、マイナンバーカードで受診した患者の同意を得ることで、患者の医療情報を各医療機関や薬局で共有できるようになります。
加えて、患者自身がマイナポータルを通して自身の情報を確認できるようになることから、国民の健康への関心が高まることや、情報の二次利用によって、治療の最適化やAI治療などの新技術開発、大規模臨床研究や新薬の開発などへの利用が進むことも期待されています。
つまり、全国医療情報プラットフォームの創設にあたって、各医療機関には、オンライン資格確認の導入とともに、マイナンバーカード対応のシステムを導入することが求められるということになります。オンライン資格確認は、2023年4月より原則義務化されているので、これから体制を整える医療機関は少ないと考えられますが、新規開業する病院やクリニックなどは、厚生労働省の特設サイトなどを参考にすることをおすすめします。
参照:日医on-line「オンライン資格確認の導入の原則義務化」と「オンライン資格確認等システムを通じた患者情報等の活用に係る診療報酬上の評価の見直し」について
参照:厚生労働省「オンライン資格確認の導入について(医療機関・薬局、システムベンダ向け)
また、オンライン資格確認に対応できるよう体制を整えてはいるものの、実際にはオンライン資格確認をおこなうことは少ないという医療機関はかなりの数にのぼると考えられますが、政府は、診療報酬改定DX対応方針の取組スケジュール案において、令和6年以降、さらにオンライン資格確認を拡充させていきたい方針であることを示しています。
参照:厚生労働省「診療報酬改定DX対応方針 取組スケジュール(案)」
電子カルテ情報の標準化
電子カルテ情報の標準化とは、電子カルテの情報の記載方法や交換方式を標準規格化する取り組みです。これが実現すれば、医療機関同士でスムーズに情報を交換したり、必要なデータを共有したりすることができるようになります。
手続きの流れとして、まずは診療情報提供書・退院時サマリー・健診結果報告書の3文書と、傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査・処方の6情報を対象に標準化を進め、順次、対象となる情報を拡大することが想定されています。
診療報酬改定DX
こちらが本記事の本題です。具体的にどのような施策であるのかはこのあと詳しく説明していきます。
診療報酬改定DXの具体的な内容は?
「診療報酬改定DX」の具体的な施策は、大きく次の4つにわけられます。
それぞれ詳しく解説していきます。
診療報酬改定の円滑な施行
診療報酬改定は2年に1度おこなわれていますが、先に解説した通り、2022年におこなわれた診療報酬改定までにおいては、改定内容の工事が3月、改定施行が4月というパツパツなスケジュールが実践されていました。しかし、「医療DX令和ビジョン2023」の提言がなされた後、初めての診療報酬改定である、2024年度の診療報酬改定においては、診療報酬改定を円滑に施行するために、施行日が例年よりも後ろ倒しとなる6月1日に設定されました。これにより、各システムベンダーは改修テスト期間を十分にとれるようになっただけでなく、各医療機関は、診療報酬改定後初めてとなるレセプト請求を、余裕を持っておこなうことができるようになりました。
共通算定モジュールの開発
改修作業に時間がかかる原因のひとつとして、各システムベンダーが独自に算定モジュールを開発しているという実態がありました。そのため、厚生労働省、審査支払期間、ベンダー、デジタル庁が協力して共通算定モジュールを作成すれば、診療報酬改定時には、各ベンダーは当該モジュールの更新をおこなうだけで作業が完了するという想定で、「共通算定モジュールを導入することが課題解決につながる」と考えられています。ただし、現行の診療報酬点数の仕組みはかなり複雑であるため、モジュール作成がうまくいくのかは未知数であるとされています。
共通算定マスタ・コードの整備と電子点数表の改善
診療報酬改定DXは、最終的に、前述した「全国医療情報プラットフォーム」と連携させることを目標として掲げています。そのためにも、コードを標準化させて、全国の医療機関で患者情報を共有することが必要です。
なお、共通算定マスタおよびコードの詳細は次の通りです。
また、この項目に関しては「公費・地単公費の医療費助成情報のマスタ作成」も併せておこなわれることになるため、地方自治体が独自におこなっていた公費負担医療などの受給資格や負担割合などの情報が管理可能になることから、公費などを適用させたあとの自己負担金を正確に計算できるようになるとされています。
標準様式のアプリ化とデータ連携
医療機関で作成する診療計画書や同意書などの各種帳票の標準様式を、アプリなどで提携できるようシステムを変革していきます。また、施設基準届出などの電子申請をシステム改修によってさらに推進していきます。
診療報酬改定DXによるクリニックにとってのメリット
診療報酬改定DXが推進されることによって、クリニックが得られるメリットとしては次の点が挙げられます。
それぞれ詳しくみていきましょう。
診療報酬改定に関連する業務不可が軽くなる
2024年度の診療報酬改定より改定施行日が6月1日となったことで、現に、診療報酬改定後、初めてのレセプト請求までの期間が延びたことで「短期間の間に新しい仕様に対応しなければならない」というプレッシャーは軽減されています。共通算定モジュールなどの開発が実現すれば、さらに業務不可が軽減されると予想されます。
ただし、共通算定モジュールを利用するためには、オンラインに接続できるレセコンの導入が不可欠なので、自院で使用しているレセコンの仕様によっては、メーカーの乗り換えが必要となる場合もあります。
医療機関をまたいだ診療費の計算がスムーズになる
共通算定マスタ・コードが整備されると、医療機関をまたいだ診療費の計算が可能となります。現状、医療機関ごとに計算している高額療養費を他院の診療費と合算できるようになるほか、特定疾患や自立支援などの公費での管理表を撤廃することもできます。
医療機関がベンダーに支払うコストが下がる可能性がある
現状、各ベンダーが独自におこなっている、診療報酬改定時のプログラム開発を政府が担うことになれば、レセコン用のプログラム開発が容易になることから、医療機関が負担しているメンテナンス料が下がる可能性が考えられます。各システムの新規導入時のコストに関しても同様です。
地域包括医療システムの強化
データの連携・共有が進めば、地域包括ケアシステムを支えているネットワーク構築が推進されます。これによって、地域の高齢者をより強力にサポートすることができるようになると考えられます。
診療報酬改定DXによるクリニックにとってのデメリット
診療報酬改定DXが推進されることよるクリニックにとってのデメリットとしては、次の2点が考えられます。
それぞれ詳しく解説します。
結果的に取り組みが失敗する可能性がある
ここまで解説してきた通り、共通算定モジュールの作成などは、現段階では、必ず成功するとはいえません。そのため、「作業が楽になることを期待していたのに何も変わらなかった」と残念な気持ちになる可能性も否定できません。
取り組みが成功した場合、一時的に忙しくなる可能性がある
共通算定モジュールの作成などが成功して、最終的には診療報酬改定に対応するための作業が楽になるとしても、システムの運用方法が大きく変わるタイミングには、一時的に対応しなければならないことが増える可能性があります。特に、クリニックの繁忙期と重なった場合などは相当な労力となる可能性も考えられます。
診療報酬改定DXの現状・進捗
前述の通り、診療報酬改定DXの4つの核のうち、特に「共通算定モジュールの開発」は、うまくいくかどうかは未知数であると公表されています。ただし、厚生労働省が令和5年4月に公表した「診療報酬改定DX対応方針(案)」では、「診療報酬改定DX対応方針 取組スケジュール(案)」として、令和7年度中に共通算定モジュールの施策運用をおこなうことが想定されています。
これがうまくいったら、令和8年度に共通算定モジュールを提供、令和10年度以降には、実情に応じて共通算定モジュールの提供を拡大していきたいという考えを示しています。
また、共通算定モジュールの試行運用、提供、提供拡大とフェイズを進めていくことと並行して、オンライン資格確認の拡充を目論見ている旨も示しているため、医療機関側ができること・すべきこととしては、診療報酬改定DXの行方を見守りながら、オンライン資格確認への対応体制を強化することであるといえるでしょう。
参照:厚生労働省「診療報酬改定DX対応方針(案)」「診療報酬改定DX対応方針 取組スケジュール(案)」
2030年までの医療分野におけるDXについてしっかり理解して適切に対応しよう
先に述べた通り、「医療DX令和ビジョン2030」は2030年を見据えた提言で、医療の質向上と効率化を大きな目的としています。そのため、現時点では実現可能性が未知数な対策も含まれているとはいえ、着実にDX化が進んでいくことは間違いありません。そのときどきで適切な対応ができるよう、診療報酬改定DXの進捗を含め、定期的なチェックを欠かさないことをおすすめしますよ。同時に、マイナンバーに対応できる体制を強化することも不可欠ですが、これに関しては、個人情報保護の観点から、セキュリティ対策に力を入れていくことも肝心です。「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を今一度読み込み、必要なシステムを導入するだけでなく、こまめに重要なデータのバックアップをとったり、スタッフに対して、患者データを安全に扱うための講習会を開いたりすることも考えてみてくださいね。
参照:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)」
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2025年3月時点の情報を元に作成しています。





