
クリニックのホームページ運営では「SEO対策が大事」だとよく言われています。
しかし、SEO対策を実施するには、ITに関する豊富な知識が必要なように思えます。
今回取材した、さいとう内科循環器クリニックも、2019年6月の開院以降、クリニックに関するさまざまなキーワードで検索順位の上位を獲得しているため、いわば“SEO対策に強い”クリニックといえるでしょう。
さいとう内科・循環器クリニックのSEO上位キーワード(一部抜粋)
「マスク 表裏」→1位(マスクの表裏)
「心雑音」→1位(心雑音について)
「不整脈 息苦しい」→1位(動悸や息苦しさなど→不整脈の症状かもしれません)
「コロナ対策 クリニック」→2位(新型コロナウイルスの当院の感染対策)
※2021年1月4日現在。検索ランキングは常にアップデートされますので、Google AnalyticsやGoogle Search Consoleで随時チェックしたり、ホームページ制作会社からの定期的なレポート報告を依頼することをおすすめします。
そんな同院院長の齋藤 幹 医師に、クリニックでのSEO対策の秘訣をうかがったところ、なんと齋藤医師は「開業前はSEO対策について、全く知識がなかった」と話します。
この記事では、結果としてわずか半年という短期間に自院のホームページをSEO上位へと押し上げた、齋藤医師のホームページ運営法や参考文献などをご紹介します。
基礎知識:SEOとは
SEO(Search Engine Optimization)
日本語で「検索エンジン最適化」のこと。キーワード検索の結果、サイトが上位表示されるよう、Webサイトの構成やコンテンツなどを調整することを言う。
GoogleやYahoo!で調べ物をしたときに、検索結果の一番上に表示されるサイトが最もクリックされやすいと言われています。
多くの人は、検索結果として表示されたものすべてをクリックしていくことはありません。上から順番に見出しや説明文の冒頭をチェックしていき、有益な情報に辿り着いた時点でチェックを辞める人がほとんどでしょう。
たとえば腹痛があって近所の医療機関を探すために「●●町 内科 腹痛」などのキーワードで検索したとして、1ページ目に表示されたクリニックのほうが患者から選ばれやすいということです。
表示される順番については、検索エンジンごとのアルゴリズムによって決まっています。そのため、アルゴリズムの特性や、検索されやすいキーワードの両方を考慮しながら、できるだけ上位に表示されるよう施策を講じていくことが必要なのです。
そのため、自身のサイトが上位表示されるよう、ホームページのコンテンツや、ホームページの構成そのものの最適化をすることを、SEOと総称しています。
自身のサイトが上位表示されクリックされやすくなると、その分訪れてくれる人が増えるため、クリニックにとっては集患・増患につながる可能性があります。このようなことから、近年SEOの重要性は強く叫ばれるようになっています。
画像作成:編集部
それでは、検索で上位表示されることも多い「さいとう内科・循環器クリニック」の齋藤医師は、ホームページ運営をする上でどのような点に気をつけているのか? インタビュー形式で紐解いていきます。
齋藤 医師の ホームページ運営におけるモットー
- 編集部
- 2020年10月に「コロナ対策 クリニック」というキーワードで調べていたときに、「さいとう内科・循環器クリニック」が1位で表示されておりました。
ホームページを詳しく見てみると、新しい診療支援システムを積極的に取り入れていますし、コロナ対策や疾患に関する情報発信もされています。それに伴って、さまざまなキーワードで上位表示されていますよね。
ホームページを運営、更新する上でどんなことを意識されていますか?
ホームページ運営の参考にしたのは…
- 編集部
- そもそもホームページは制作会社に依頼して作りましたか?それとも、ホームページ制作システムを使ってご自身で作りましたか?
- 齋藤 医師
- 私は医院向けホームページ制作システムを提供しているWevery!(ウェブリィ)(株式会社ウェブリィ)にお願いして、基本的な構造は作っていただいて、内容については自分で制作しました。
- 齋藤 医師
- 開業準備の際に、株式会社ウェブリィの創設者である河村伸哉さんのセミナーを聞きに行ったことがありました。最初は「変な勧誘があったらどうしよう」と思っていたのですが、セミナーを聞くと、至極真っ当なことをおっしゃっていると感じました。
その後、河村さんの本(「医院ホームページ作成の教科書 院長が知っておくべき増患のための6原則」マスブレーン)や記事を読んで、クリニックのホームページ制作におけるシステム利用や運用支援はWevery!さんにお願いしようと決めました。
- 編集部
- 当時の河村さんの影響は大きかったんですね。
- 齋藤 医師
- そうですね。実際にWevery!で担当してくれたのは河村さんではありませんが、担当者から言われた「コツコツとブログを書いてください」というお話も、意識しています。
定期的なブログ記事の更新はSEOで一番効果がある、もっとも即効性が高い…というわけではないものの、広告出稿などと違ってお金もかからないですし、開業したばかりで時間がある私には合っていると思いました。
ブログ更新のルール:定期的な更新と、1記事あたり約2,000字以上の執筆
- 編集部
- ブログ記事を更新する上で、心がけていることはありますか?
- 齋藤 医師
- 河村さんの著書やWevery!の担当者さんからは「1記事あたり2,000字以上」とアドバイスをいただいたのである程度意識しています。
※編集部・脚注※
2,000字と聞いて、「なぜそんなに長い文章が必要なの?」と驚く人は多いでしょう。上位に表示されるにはおおよそこのくらいの文字数が有効だとされていますが、その理由はいくつかあります。
まず、全体の文字数が多いと、ページ内で被りがない「ユニークワード」が増えることが挙げられます。SEO対策を取るうえでは、メインキーワードと一緒に検索されやすい単語についても考えることが重要なのですが、この単語の種類が多ければ、検索に表示される機会が増えるからです。
Googleの考え方としては、「メインのワードについて誰かに教えるとき、ほぼ必ずこのワードも出てくるはずだ。だから、その言葉についても触れているコンテンツはいいものであるはずだ」というものなのでしょう。
2つめの理由は、文字数が多ければ読む時間がかかるため、ユーザーのページ滞在時間が長くなることです。ページ滞在時間は、Googleアナリティクスでも指標のひとつになっているため、Googleから評価を得るための要素となり得ます。
こちらも、「いい情報はじっくり読みたくなるはず」「必要なものがあれば、きっと長い時間を過ごすだろう」といったGoogleの考え方がもとになった指標です。
※※※
記事の内容としては、主に疾患に関することをひとつの記事でまとめています。「心雑音について」や「動悸や息苦しさなど→不整脈の症状かもしれません」といった記事がそうです。
また、先にも言った通り、私のパーソナリティに関するブログ記事を公開することもあります。
定期的に記事を更新することで、「新しい情報を定期的にアップしている有益なサイトだ」とGoogleに認識されることも教えてもらったので、目標としては1週間に1記事更新を目指しています。現実には2週間に1回ほどになっているので、まだまだですね(笑)。
- 編集部
- なるほど。さまざまなアドバイスをWevery!さんから受けているんですね。
- 齋藤 医師
- ただ、Wevery!さんや河村さんの言うことをすごく信じてるというよりも、僕が「こうじゃないかな」と思っていることを河村さんも言っている、という感覚です。
<齋藤医師が意識している ブログ更新のポイント>
・定期的に記事を書く(疾患の解説など)
・記事の文字数は2,000字程度を目安に
・執筆した記事の内容を定期的にアップデートする
- 齋藤 医師
- これらのポイントは、まだ完璧に実行できているわけではありませんが、一つの指標としています。
クリニック・サイトを見つけてもらうための工夫:MEO対策
- 編集部
- ホームページの運営と関連しますが、MEO対策もしっかりされていますよね。
「さいとう内科・循環器クリニック」はGoogle上に写真もたくさんアップしているので、クリニックを調べた人にとって親切な情報提供をされていると思いました。
MEO対策とは
MEO(Map Engine Optimization)。
地図検索(主にGoogleマップ)で上位表示させる施策。上位表示されることで、商圏内のターゲットユーザーの目に付く機会が増え、店舗や施設の認知・来店につながる可能性が高まる。ネットからの新たな集客チャネルとして注目されている。
※編集部・脚注※
具体的に「MEO」とは、地図上の事業所に関するGoogleビジネスプロフィールの情報をローカル検索結果として表示させるための施策です。
「ローカル検索結果」とは、検索をした場所によって検索結果が変わる仕様のことです。たとえば、「内科」と検索した場所が東京であれば、東京の内科が表示されますし、大阪であれば大阪の内科が表示されます。もしくは、「新宿 内科」といったように地名を含むキーワードで検索した際にも、同じように特定のエリアの内科が表示されます。
このように、MEOは地域に密着していることから、「ローカルSEO」とも呼ばれています。
ローカル検索結果においては、地図上に3つの事業所が表示されるため、同業者のなかで上位3位までに表示されると、格段に患者の目につきやすく、集患・増患につながる可能性が高い傾向にあります。
MEOで上位に入るためには、まずはGoogleビジネスプロフィールに登録して情報を充実させることです。情報を充実させる方法に関しては、前述のSEO対策の説明も併せてご参照いただくといいでしょう。
また、文字としての情報を充実させるだけでなく、写真を投稿することも重要です。写真はオーナーが投稿したものが採用されることが多いため、清潔感などが伝わる内装写真、場所がわかりやすい外観写真などを心がけましょう。
2つめは、口コミの数、よい口コミを増やすこと、そして口コミが入ったときに丁寧に返信することです。ネガティブなコメントであっても、「不快な思いをさせて申し訳ありませんでした」の謝罪を返すことによって、やりとりを見た人にいい印象を抱いてもらいやすくなります。
※※
- 齋藤 医師
- 恥ずかしい話、私はMEOの仕組みを理解していません。これもWevery!の河村さんの本をもとに、見よう見まねで行っています。
Googleビジネスプロフィール(旧:Googleマイビジネス)に登録し、随時写真をアップしたり、クリニックのホームページのリンクを設置したりと工夫しています。
<GoogleビジネスプロフィールでのMEO対策 実施ステップ>
・Googleに会員登録後、ログインする
・Googleビジネスプロフィールの利用を開始する
┗「ビジネス名」(クリニックの正式名称等)をする ※後に変更可
┗「ビジネス所在地」(郵便番号、住所等)を入力する
┗「ビジネスのタイプ」(業種)を選択する
┗「連絡先情報の入力」(電話番号、WebサイトのURL)を登録する
┗「ビジネスの確認」で確認コードを郵送してもらう
┗クリニックに郵送されたハガキに記載のコードをGoogleビジネスプロフィールに入力する
→Googleマップで表示される、クリニックのページを編集できるようになる(情報の追加を実施)
- 齋藤 医師
- 時々やり方に悩むこともありますが、Wevery!の担当さんにメールで聞いて解決しています。何か大きな野望があるわけではないですが、知識がないながらも勉強して人に聞き、まずやってみようと思って進めています。
- 編集部
- ほぼSEOに関する知識がないところからスタートして、セミナーや本などから学びながら、着実に対策をして結果が出ているという事実は、SEO対策に悩む開業医の励みになると思います。
クリニックが実践すべきSEO対策とは
ここからは、齋藤先生のお話も参考にしながら、クリニックが実践すべきSEO対策を確認していきます。
クリニックが取り組むべきSEO対策は、大きく以下の3種類にわけることができます。
- 内部対策(オンページSEO)
- 外部対策(オフページSEO)
- コンテンツSEO
それぞれ詳しくみていきましょう。
内部対策(オンページSEO)
内部対策(オンページSEO)は、ホームページの内部構造に対しておこなうSEO対策です。どういうことかというと、ページ同士をリンクさせたり、ページの表示スピードを上げたりすることで、ユーザビリティを上げていくということです。
具体的には、サイトマップを作成してページ内を巡回しやすくしたり、タイトルや見出しのタグを入れたりすることによって、GoogleやYahoo!などの検索エンジンからの評価向上を目指します。
特に大切な内部対策について以下に詳しく説明します。
titleタグ、descriptionタグを適切に設定する
ページタイトルを表す「titleタグ」、そのページに何が書かれているかを表す「descriptionタグ」はそれぞれ、検索結果画面、検索結果のタイトル下に表示されます。そのため、どちらもホームページを開く前の段階でホームページの内容を伝える役割を持っているということになります。
titleタグは全角32文字以内、descriptionタグは全角130文字以内が推奨されています。
h1タグを適切に設定する
hタグとは、「見出しに設定するタグ」のことです。hタグは「h1」から「h6」までにわけられますが、数字が少ないほどフォントが大きくなります。
つまり、たとえばh1タグで囲んだ文字列=大見出し、h2タグで囲んだ文字列=中見出し、h3タグで囲んだ文字列=小見出しといった具合で使い分けすることになるため、基本的にはh1タグがページのテーマを表す“大見出し”の役割を担っているということになりますます。
そのため、h1タグで囲む文字列には、そのページに何が書かれているのかをわかりやすく伝えられる言葉を選ぶことが大切です。
なお、h1タグで表示される文字の大きさが大きすぎてホームページのデザインと合わない、自分の感性と合わないなどの場合は、h3タグで囲んだ文字列=大見出し、h4タグで囲んだ文字列=中見出し、h5タグで囲んだ文字列=小見出しとしてもいいですし、はたまた、見出しの大きさを4段階以上にわけてもOKです。
altタグを適切に設定する
altタグとは、挿入されている画像の意味を説明するテキストのことです。別名「代替テキスト」とも呼ばれます。なぜaltタグを適切に設定することが大切であるかというと、サイトを巡回しながら、検索エンジンが検索の順位を決めるための要素を収集する「クローラー」は、画像を見ただけではその内容を把握できないためです。そのため、altタグを設定して画像の内容を正しく伝えることで、検索結果順位にプラスとなる影響を与えられるのです。
外部対策(オフページSEO)
外部対策(オフページSEO)とは、外部サイトやSNSからの被リンクやサイテーションを獲得するために実施するSEO対策です。外部からリンクが張られることを「被リンク」、外部サイトやSNSで企業名(クリニック名)が言及されることを「サイテーション」といいますが、外部対策においては被リンクおよびサイテーションが大変重要です。なぜかというと、GoogleやYahoo!から、「外部サイトが紹介したいと思う良質なコンテンツをあげている」と認識されるためです。
被リンクやサイテーションを獲得するために具体的にどんなことをすればいいかというと、たとえば院長のインタビュー記事を掲載するなど、ホームページ訪問者にとって役立つコンテンツを盛り込んでいきます。
コンテンツSEO
コンテンツSEOとは、ユーザーの悩みを解決するような良質なコンテンツを制作することです。たとえば耳鼻咽喉科なら、「鼻水 アレルギー 1月」などのキーワードで検索したユーザーに対して、季節ごとのアレルゲンや、アレルギー以外に考えられる疾患などをまとめた記事を制作することなどが考えられます。
コンテンツSEOは、該当する記事を読んだ潜在患者がすぐに来院するとは限りませんが、「このクリニックの先生はこういう症状に詳しそう」「信頼できそう」という印象を抱いてもらいやすいため、治療が必要となったタイミングで来院してくれる可能性が考えられます。
SEOの質を上げるためのキーワード選定には「キーワード分析ツール」が不可欠
自院がどんなキーワードをもとに検索されているか、競合がどんなキーワードをもとに検索されているかを調べるためには、「キーワード分析ツール」が不可欠です。キーワード分析ツールとは、そのwebサイトがどんなキーワードで検索されているかを調べるツールです。
キーワード分析ツールは、無料で利用できるものも有料のものもありますが、無料で使えるものでもっともよく知られているのは「ラッコキーワード」です(※ただし、有料プランを利用すればより詳しい分析結果を得られます)
「ラッコキーワード」を使って競合のホームページがどんなキーワードで検索されているのかを調べるためには、まず、トップページ内の「サイト調査(競合調査等)」のタグを選びます。すると、ドメインまたはURLを入力する欄が表示されるので、そこに競合クリニックのホームページURLを打ち込みます。すると、競合のホームページへのリーチにつながったキーワードと、各キーワードの月間検索数、推定流入数、SEO難易度などが表示されるので、その結果をもとに、自院のホームページの改善方法を考えていくことができます。
また、「ahrefs(エイチレフス)」も使い勝手のよさから多くのユーザーに支持されているので、併せて試してみてもいいかもしれません。
その他のキーワード分析ツールに関しては以下をご参照ください。
参照:クリニックのホームページに盛り込むキーワードの選定方法は?
診療科別SEO対策
上記3つはSEO対策の基本となりますが、対策を講じる時点で考えるべきことは診療科によって違いがあります。なぜかというと、検索されやすいキーワードが診療科によって異なるためです。
集患・増患のためには、患者・潜在患者の来院につながりやすいキーワードを選定することが不可欠です。たとえば東京・新宿にある心療内科なら、「新宿 心療内科」のキーワードはもちろん入れ込みますが、同じエリアの同じ診療科のクリニックも同じキーワードを選定しているため、競合と被りにくいキーワードも併せて盛り込んでいくことが重要です。
たとえば、不眠症患者の診療を得意としているなら、不眠症に悩んでいる人に検索されやすいキーワードを選定することが大切ですし、夜間や土日に診療をおこなっているなら、その点も打ち出していきたいところです。
また、美容外科に関しては、レーザーなどの医療機器に精通しているユーザーが検索する可能性が高いため、最新医療機器を導入している場合などは積極的にキーワードに盛り込んでいきましょう。
クリニックSEOでよくある失敗
クリニックSEOでよくある失敗としてまず挙げられるのが、「十分な対策をとれていなくてアクセスが増えない」ですが、これに関しては、SEO対策の記事などを参考にホームページを改良していく以外ありません。自院での改良が難しいなら、専門家にSEO対策を依頼するのも一手です。
一方、“失敗する前に避けるべき”なのは、医療広告ガイドラインや薬機法に抵触することです。前者に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰則が科されるうえ、罰則事例として公表されることもあります。後者に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはその両方が科されるとされています。
クリニックSEOで成功する秘訣
続いては、クリニックSEOで成功する秘訣を説明します。クリニックSEOで成功するためには、以下の2つを意識することが大切です。
- E-E-A-T
- YMYL
それぞれ詳しくみていきましょう。
E-E-A-T
E-E-A-Tは、Googleが定める検索品質評価基準のひとつです。それぞれの頭文字は「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」からとられています。
具体的には以下の点が評価されます。
経験:発信内容が実体験に基づいているか、独自性があるか
専門性:発信者が正式な資格を有しているか、発信内容に誤りはないか
権威性:その内容についてどれだけ優位性があるか
信頼性:運営者や執筆者の名前や顔写真、経歴が明記されているか
YMYL
YMYLは、「Your Money Your Life」の頭文字をとった言葉で、人のお金や生命・健康・生活に重大な影響を与えるジャンルを指します。医療以外にも金融やフィットネスなど多彩なジャンルが含まれますが、これらに該当するジャンルのホームページについては、検索エンジンが特に厳しく評価をおこなっているため、そのことを意識しながらホームページを作成・運営していくことが大切です。
まとめ
パソコンでの作業に苦手意識がある人は、「SEO対策なんてちんぷんかんぷんだし、自分ではとてもできる気がしない」と思うこともあるかもしれません。しかし、これから先もクリニックを長く運営していきたいなら、ホームページ制作や運営を業者に依頼するにしても、ある程度仕組みなどを理解しておいたほうが、制作会社のよしあしを見極めることもできますし、「こういう施策も取り入れてほしい」といった話し合いもできるので、少しずつでも知識を吸収していけるといいかもしれませんね。
実績1700件以上 知識がなくても簡単 最短30分で公開できる ホームページ制作サービス特徴
①集患対策やスマホ対応が付いて初期費用0円、月額5000円から利用可 ②クラウドシステムですので、Googleやインターネットの情勢に合わせて、常にお使いのサイトが自動でアップデートします。 ③誰でも簡単に、内容の修正や追加ができます。 ④これまで1000件以上の医療機関・介護施設の経営支援を行ってきた「日本経営グループ」が、Wevery!を運営しています。対応業務
デザイン作成 SEO対策 広告運用代行 ライティング サーバー保守・管理 撮影 リニューアル 更新のみ対応 CMS SNS運用支援その他特徴
集患支援 実績多数 UI/UXに強い 地域密着型 LP制作に強い ロゴ制作対応 セキュリティに強い診療科目
内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
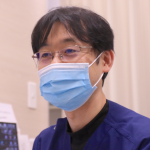
取材協力 さいとう内科・循環器クリニック 院長 | 齋藤 幹
大学卒業後、循環器科・循環器内科を専門に勤務。大学病院や専門病院での経験を経て、2019年に「さいとう内科・循環器クリニック」を開業。医学博士、内科認定医、総合内科専門医、循環器専門医・指導医、臨床研修指導医。
他の関連記事はこちら

監修 Wevery!創設者 メディキャスト株式会社 | 河村 伸哉
東北大学法学部卒業後、フリーランスを経て、大手飲料メーカーや通信系システム会社等のウェブサイト作成を経験。現在は、日本経営グループのメディキャスト株式会社にて、医療機関のマーケティングを担当。16年間で1400件以上のウェブサイトをプロデュースし、増患に導いた。診療科目別の増患ノウハウへの信頼はあつく、ドクターの強みを生かした訴求方法で日々提案を行っている。
他の関連記事はこちら

執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
他の関連記事はこちら







