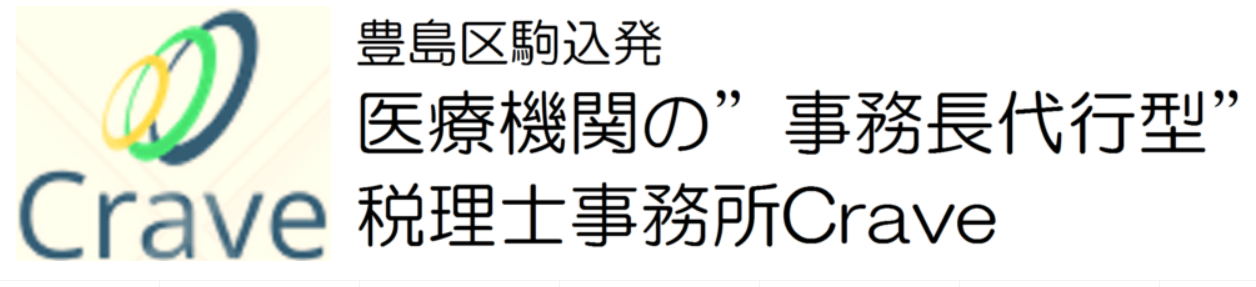中小企業や個人クリニックを運営するに当たり、大きな保障と節税効果をもたらす「中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)」があります。この制度は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産したり経営難に陥ったりすることを防ぐことを目的とした共済制度です。今回は、この制度を利用した簡単にできて効果的な節税対策についてご紹介します。
「中小企業倒産防止共済制度」とは
「中小企業倒産防止共済制度」とは、中小企業倒産防止共済法に基づいて、国が全額出資している『独立行政法人中小企業基盤整備機構』(中小機構)が運営しています。本来は取引先が倒産してしまった際に巻き込まれて連鎖倒産したり、経営難になったりすることを防ぐためにある制度です。共済に加入することで貸付制度が利用できるようになるほか、個人診療所においては、制度を利用し節税をすることも可能です。共済の掛け金の全額が税法上必要経費として認められる上に、条件に応じて掛け金が全額戻ってくるのです。掛け金を前納することも可能で、利益が多く出そうな場合の決算対策にも利用できます。
加入資格
中小企業倒産防止共済制度に加入できる医療機関は、引き続き1年以上事業を行っている個人診療所で、医療法人は加入できません。具体的には以下のように定義されています。
- 個人事業者または会社で、表1の「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する方
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
40カ月以上納付している場合、全額戻ってくる
中小企業倒産防止共済制度では、掛け金の全額を法人の損金・個人事業の必要経費に算入できるという節税メリットがあります。月額掛け金は、5,000円から20万円まで5,000円単位で選ぶことが可能で、最大で年240万円の掛け金を経費として計上できるのです。掛け金は、800万円に達するまで積み立てることができ、解約すると掛け金納付月数と解約の方法に応じた割合で返金を受け取ることが可能です。返金(解約手当金)の割合は以下の表2のように設定されており、40カ月以上納付している場合には全額が返金されます。
| 掛け金納付月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
|---|---|---|---|
| 1カ月~11カ月 | 0% | 0% | 0% |
| 12カ月~23カ月 | 80% | 85% | 75% |
| 24カ月~29カ月 | 85% | 90% | 80% |
| 30カ月~35カ月 | 90% | 95% | 85% |
| 36カ月~39カ月 | 95% | 100% | 90% |
| 40カ月以上 | 100% | 100% | 95% |
解約の理由
- 任意解約……共済契約者が任意でいつでもできる解約
- みなし解約……個人事業主の死亡、法人の解散・分割などによる解約
- 機構解約……掛け金の滞納や不正行為があったときの機構側からの解約
ただしこの返金は、個人の場合は事業所得に、法人の場合は益金に算入されます。掛け金が全額損金となり、返金が全額所得になるということは、所得の課税時期を先送りしていることを意味します。掛け金による節税とは当座の節税であり、重要なのは返金をいつ受け取るかという出口戦略になります。
まとめ
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、医療法人は加入できませんが、個人事業主の医師には検討の価値がある共済です。掛け金が経費となり、40カ月以上納付していれば掛け金の全額が戻ってきます。ただし、解約して受け取った共済金は収入になるため、解約のタイミングを見定める必要があります。
特徴
対応業務
その他特徴
診療科目
特徴
対応業務
その他特徴
診療科目
この記事は、2021年3月時点の情報を元に作成しています。