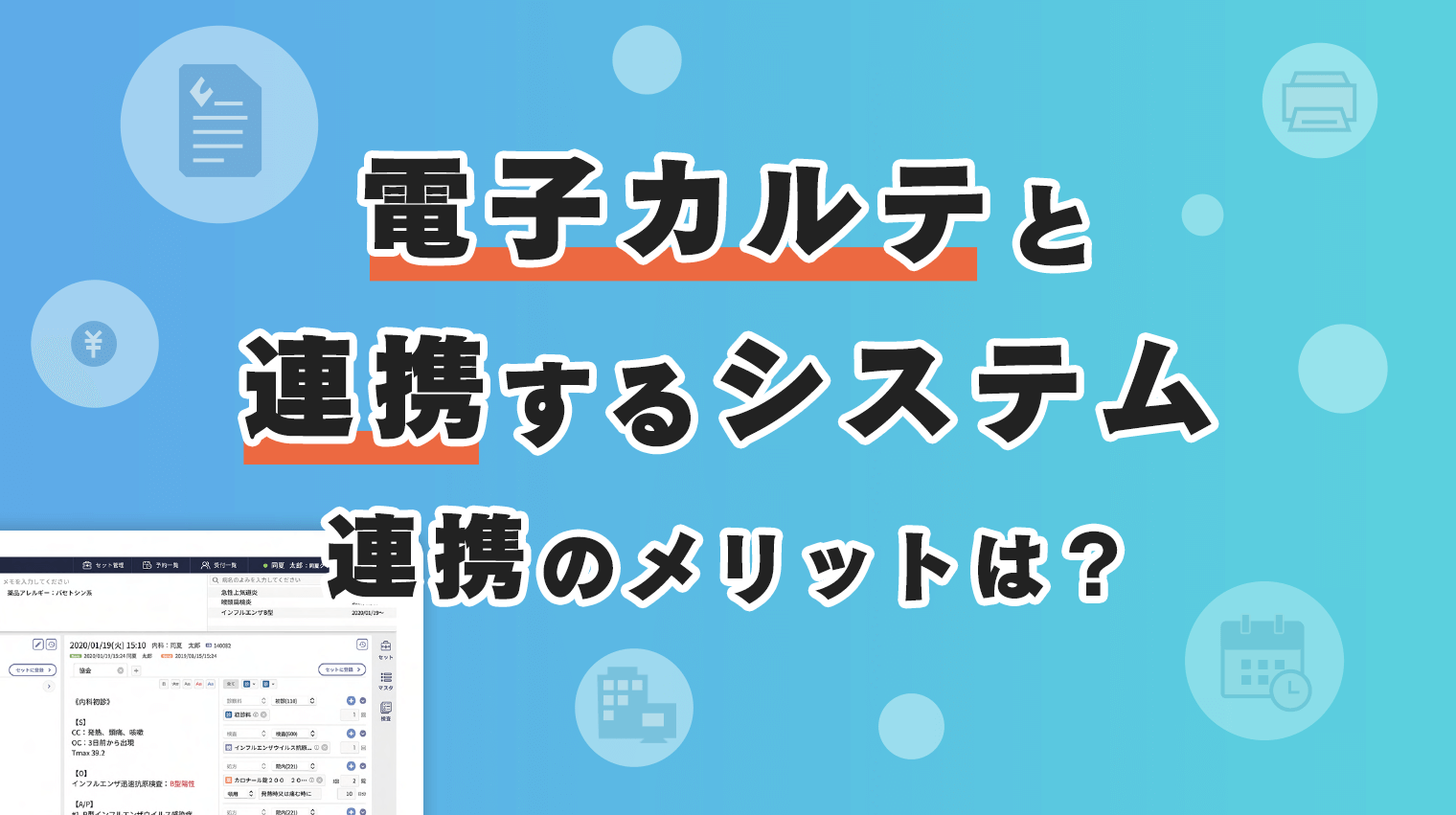
自院に導入する電子カルテを選ぶにあたってのチェックポイントはいくつかありますが、「どんなシステムと連携できるか」も大切なチェックポイントのひとつです。そこで今回は、理由について詳しく知ってもらうために、電子カルテと連携できるシステムの種類や、連携することによるメリットを解説していきます。
電子カルテ連携の意義とは?
まずは、電子カルテと連携可能なシステムを連携させることの意義について説明していきます。電子カルテと連携可能なシステムはいくつかありますが、その多くは、電子カルテと連携させることなく単独でも使うこともできます。そのため、現状は電子カルテを導入しておらず紙カルテを使っているクリニックなどは、電子カルテと連携可能なシステムであっても、連携させることなく、単独で使っているケースがあるでしょう。
では、各システムを単独で使わずに電子カルテと連携させるとどんないいことがあるのかというと、それぞれのシステムで計測したデータなどをスムーズに電子カルテに取り込めるというメリットがあります。電子カルテと各システムに物理的距離があっても、問題なく取り込むことができます。もちろん、取り込んだものはそのまま電子カルテで保存することができるので、業務効率がアップします。
電子カルテと連携可能な10のシステムの紹介
電子カルテと連携可能なシステムは大きく9種類あります。どんなシステムがあって、連携することでどんなことができるようになるのかについて、一つずつ順番に解説していきます。
予約管理・問診システム
Web予約システムやWeb問診システムと電子カルテを連携させると、患者がパソコンやタブレットから入力した基本情報や問診内容が電子カルテに反映されます。
そのため、医師がカルテに記入する時間を削減できるだけでなく、患者の待ち時間を減らすこともできます。
また、患者に来院前にweb問診をおこなってもらうようにすれば、事前に患者の状態をうかがい知ることができるため、受付の時点でトリアージできます。
薬剤情報管理システム
薬剤情報管理システムとは、医療機関や薬局における薬剤情報を管理するための機能を備えたシステムです。システムを活用することで、薬剤に関する情報を検索したり、用量や投与期間、重複などをチェックしたりすることができますが、システムを電子カルテと連携していなければ、処方のたびにシステムを立ち上げなければならないため不便極まりないといえます。
PACS(医療用画像管理システム、医療画像保管伝送システム)
PACS(パックス)とは、「Picture Archiving and Communication System」の頭文字を並べた言葉で、日本語にすると「医療用画像管理システム」または「医療画像保管伝送システム」となります。X線、CT、MRIなどで撮影した画像情報の管理・保管・伝送を効率よくおこなうためのシステムなので、画像へのアクセスや画像の共有がスムーズになり、治療や診断に役立てることができます。
PACSを電子カルテと連携させれば、X線やXT、MRIで撮影後、読影室や診察室にいながらにして、パソコンやタブレット端末から結果を閲覧・参照できます。
電子カルテがクラウド型であれば、院外からでも電子カルテにアクセスできるため、院外からでも画像を確認できるということになります。そのため、緊急時に院内に医師がいない場合でも、画像を見て処置の指示を出すことができます。
また、電子カルテを開けば画像を確認できることから、診察室などで患者に画像を見てもらいながら状態の説明ができることも大きなメリットです。
透析管理システム
透析管理システムとは、名前の通り、透析に関するデータを管理するシステムです。電子カルテと連携しておけば、透析に関するデータと診療データを突き合わせて治療方針などを決めることができます。
また、受付・予約管理から体重、血圧などの身体情報、処置、注射、薬剤などの透析処置に関連する情報が透析管理システムに自動的に取り込まれるため、電子カルテを起点に他部門と情報共有ができます。
バイタル測定システム・健診システム
体温、血圧、脈拍、呼吸をはじめとするバイタルサインを測定するシステムや健診システムを電子カルテと連携させておけば、測定記録が自動で電子カルテに反映されるため、入力の手間を省けるだけでなく、誤入力や未入力を防ぐこともできます。
電子カルテのメーカーによっては、血液や尿などの生化学検査、細菌検査などの検査機器との連携も可能で、ヒューマンエラーを軽減することができます。
検査システム
検査システムと電子カルテを連携させておけば、検査依頼も検体ラベル発行も検査結果の共有もスピーディです。
業務の簡素化はもちろん、患者の待ち時間短縮も実現できます。
会計(レセプトコンピュータ)・決済システム
会計、決済システムおよび自動精算機との連携に関しては、正確にいうと、電子カルテそのものと連携させるのではなく、電子カルテと紐づくレセプトコンピューターと連携させることになります。
会計・決済システムをレセプトコンピューターと連携させておけば、会計時の計算ミスを防止することができるうえ、つり銭補充の負担を軽減できます。また、計算の必要がなくなるので、受付の人員削減につながる場合もあります。キャッシュレス決済を導入している場合は、院内での感染防止などにも役立てられます。
リハビリシステム
患者の基本情報登録やスケジュール管理・実績登録、帳票類を作成できるリハビリシステムと電子カルテを連携させておけば、運動療法士や看護師とスムーズに情報を共有できることから、リハビリのスケジュール管理も楽になります。
リハビリシステムには、「療法士勤務スケジュール管理機能」「総合計画書作成処理機能」「総合評価作成機能」「リハビリカルテ登録機能」「リハビリ未実施患者管理機能」などがあります。
オンライン診療システム
オンライン診療システムとは、インターネット上で診察や診断、薬の処方などをおこなうことができるシステムです。医師と患者は、スマホやタブレット、パソコンなどのデバイスを通して相手の声や表情を確認できます。そのため、基本的にはビデオ通話機能が備わっていますが、薬の処方のみで患者の症状を確認する必要がない場合などは、映像なしで通話機能だけを使うこともあります。また、オンライン診療システムには、診療予約機能や処方箋の発行機能、料金支払い機能なども備わっています。
電子カルテとオンライン診療システムを連携させておけば、医師は、自宅や外出先からでも、電子カルテに入力されている患者のデータを確認しながらオンライン診療をおこなうことができます。処方箋の発行機のなども備わっているため、クリニックに戻らなくてもその場から薬を処方することもできます。
また、足腰が悪く通院が困難な患者が自宅にいながらにして診療を受けられることや、2次感染や院内感染を防げることも大きなメリットです。
チェックイン連携
「チェックイン連携機能」とは、患者が来院した際、受付機と連動して、電子カルテに自動的に患者の来院を記録する機能です。この機能があれば、緊急性の高い患者や、対応に注意を要する患者を即座に把握できるため、最適な対応が可能となります。
電子カルテと各種システムで連携できることは?
電子カルテ連携によって、各種システムと連携できることとしては、主に以下が挙げられます。
①患者属性
②オーダ情報
③予約・受付情報
④診察記録
⑤検査結果
⑥画像データ
⑦システム起動
⑧診察費や薬代などの金額情報
①~⑥に関しては患者の症状などの具体的なデータとなります。
加えて、電子カルテと各種システムを連携させておくことで、一方を立ち上げるともう一方も自動で起動するのも特徴です。また、診察や検査にかかった金額も連携されます。
電子カルテと各種システムの連携のファーストステップ「頭書き連携」とはの方法
電子カルテと各種システムなどとの連携方法のうち、まず重要なのが「頭書き連携」です。頭書き連携とは、電子カルテに登録した患者データを、連携したシステムに自動的に転送させる機能です。たとえば、予約管理・問診システムとPACSと連携させている場合、電子カルテに新患情報を登録すれば、予約管理・問診システムとPACSにも患者情報が自動的に反映されます。
オンライン資格確認と電子カルテの連携の重要性
「オンライン資格確認」とは、医療機関や薬局などの窓口において、マイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号などによって、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。オンライン資格確認をおこなうためのシステムは電子カルテとも連携可能です。オンライン資格確認のためのシステムと電子カルテを連携すれば、資格確認や患者の薬剤情報の閲覧、特定健診情報の閲覧が可能となるため、これまでより充実した患者情報を診察前に確認することができます。
まとめ:電子カルテ連携のポイント
電子カルテと各種システムは、必ずしも連携させなければいけないということはありません。ただし、電子カルテと各種システムを連携させることによるデメリットは特になく、ここまで説明してきた通り、多くのメリットを享受できるため、少しでも早く連携させることをおすすめします。
ただし、「連携させるか・させないか」という観点から悩むことは一切ありませんが、電子カルテや各種システムのメーカーによっては、「連携不可」ということがあり得るので、電子カルテおよび各種システムを選ぶ際に、「連携可能かどうか」をチェックすることは必須といえます。
また、もうひとつの留意点として、「セキュリティ対策に力を入れることが不可欠」ということも挙げられます。電子カルテには患者の個人情報がぎっしり詰まっているので、連携を進めるにあたっては、さらにセキュリティ対策を強化していくことが大切です。
この記事は、2022年7月時点の情報を元に作成しています。




