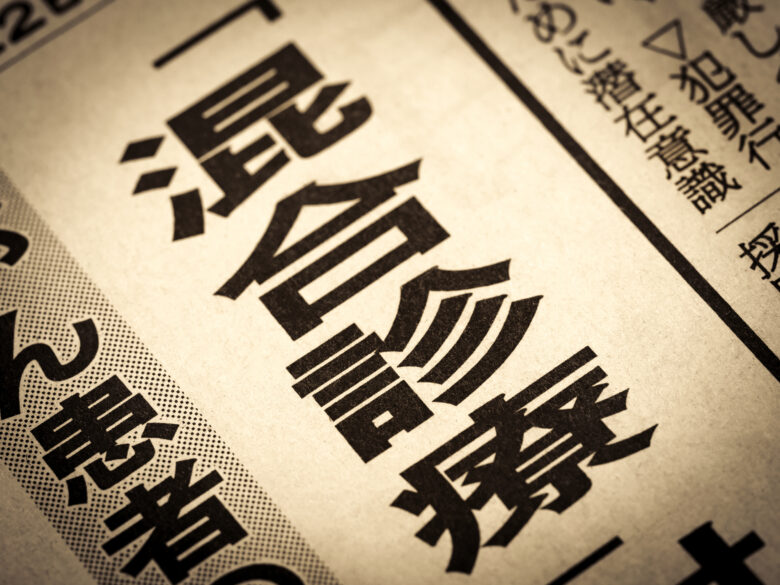
医療機関で患者に提供される診察や診療は、医療費の請求先や金額の設定といった金銭的観点からみると、大きく2種類にわけられます。ただし、2種類に加えて、両方を導入した「混合診療」をおこなっている医療機関も存在します。どんな場合に混合診療をおこなうことになるのか、また、混合診療をおこなううえでの注意点はあるのかなどを詳しく解説していきます。
- 混合診療とは?
- 混合診療が日本国内では原則承認されていない理由とは
- 混合診療が認められているケースとは?
- 混合診療に関するよくある疑問
- Q: 混合診療の定義における「疾病に対する一連の治療過程」とは、治療期間全体を指すのか?
- Q: ひとつの疾病に対する治療を2つ以上の医療機関でおこなった場合、1つの医療機関では保険診療、そのほかの医療機関では保険外診療をおこなった場合は混合診療になるのか?
- Q.:2つ以上の疾患の治療を同じ医療機関で受けた場合、1つの疾患の治療を保険診療、そのほかの疾病の診療を保険外診療でおこなった場合は混合診療になるのか?
- Q.:保険診療での治療期間内に、ドクターズコスメやコンタクトレンズ、サプリメントを処方することは問題ないか?
- Q. 患者が公費での定期予防接種と自費での任意予防接種を同時に受けることには問題はないか?
- 混合診療に関する他国の考え方は?
- 混合診療をおこなう可能性がある場合、ルールをよく確認しよう
混合診療とは?
混合診療とは、疾病に対する一連の治療過程において、保険診療と保険外診療(いわゆる自由診療)を併せておこなうことを意味します。
ただし、日本では原則として混合診療は承認されていないため、一連の治療過程において自由診療をおこなった場合は、当日の診療は(保険適用の診療部分を含め)全額患者自己負担とされるルールとなっています。
承認されていない理由を説明する前に、まず、保険診療と自由診療がどのような診療であるのかを改めて確認しましょう。
参照:公益社団法人東京都医師会「混合診療(健康診断・予防接種・自費医療など)」
保険診療とは
保険診療とは、国民健康保険やその他の健康保険に加入している人が、医療機関において受けられる「国民皆保険制度によって保障されている公的医療制度の対象となる診療」です。患者の自己負担額は診療にかかった医療費の1~3割で、残りの医療費は、医療保険の運営主体である「保険者」によって支払われます。
なお、国民健康保険も健康保険も、患者の医療費負担が1~3割であることは変わりありませんが、前者に加入しているのは個人事業主やパート、アルバイト、農業・漁業従事者などで、後者に加入しているのは会社員や公務員およびその扶養家族です。また、前者に関しては、保険料は全額自己負担となりますが、後者に関しては勤務先との折半となります。
自由診療とは
自由診療とは、保険診療では対応できない「公的医療制度の対象外となる診療」を指します。つまり、治療費が全額患者負担になるということです。なぜ保険診療では対応できないかというと、保険診療では認められていない、先進的な技術や新しい治療法を用いた医療を提供するためです 。
なお、診療方法は基本的には保険診療と自由診療の2つですが、自由診療と混同しがちな診療方法として、「自費診療」「先進医療」というものもあるので、これについても簡単に説明します。
自費診療とは
自費診療とは、保険診療の範囲内の治療において、保険適用外の医療サービスを患者が選択した場合、100%患者の自己負担の費用が発生する診療です。
たとえば、保険適用の銀歯でも治療自体は可能なところ、見た目の美しさを譲れずにセラミックの歯を選択した場合、自費診療となります。
わかりやすくいうと、「保険診療の範囲で治す選択肢があるかどうか」によって、自由診断なのか自費診断なのかを区別できるということになります。また、上記に挙げた例に関していうと、最終的に作り物の歯を入れる前の段階の治療に関しては保険適用となるため、一から十まで自由診療の場合と比較すると、患者の経済的負担が軽いといえるでしょ う。
先進医療とは
先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術を用いた療法を指します。先進医療は基本的に公的医療保険の対象外となります 。ただし、先進医療を受けるに至るまでの診察や検査、入院料などの費用は、保険診療でまかなうことができます 。
混合診療が日本国内では原則承認されていない理由とは
保険診療と自由診療の違いを確認したところで、混合診療の話に戻ります。
前述の通り、混合診療は原則として日本国内では承認されていませんが、その理由は主に次の2つとされています。
患者の負担が不当に拡大する恐れがあるため
国民皆保険制度によって、本来なら、保険診療によって国民全員が一定の自己負担額を支払うことによって平等に必要な医療を受けられるはずが、混合診療が承認されることになれば、個人の経済状況によって受けられる医療に差が出るため
科学的根拠のない特殊な医療の実施を助長する恐れがあるため
海外では承認されており、一定の評価を得ている治療であっても、日本の医療制度下では現状、安全性や有効性が確認されていない医療が、保険診療と併せて提供されることで、間違った形で医療が広まってしまう可能性が考えられるため
ただし、前述の通り、混合診療は“原則としては”認められていませんが、例外として認められているケースも存在します。
混合診療が認められているケースとは?
前述の通り、混合診療は日本では原則認められていませんが、例外的に認められているケースもあります。具体的にどんな場合に認められているかというと、「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」の3つのケースにおいては認められています。「評価療養」とは、保険導入のための評価をおこなうために提供される診療や薬品などを指します。一方、「選定療養」とは、保険導入を前提とはしていません。
「評価療養」「選定療養」に関しては、具体的には次のような診療や薬品がこれらに該当します。
評価療養
(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)
選定療養
このうち、「差額ベッド代」をもとに混合診療の仕組みを説明すると、「入院基本料相当である基礎的部分」は“保険外併用療養費”として医療保険で給付、上乗せ部分である差額ベッド代は、自由診療費として患者から徴収することになります。なお、“保険外併用療養費”において、患者から料金徴収する際の要件(料金の掲示など)は明確に定められています。
参照:公益社団法人東京都医師会「混合診療(健康診断・予防接種・自費医療など)」
患者届出療養
また、「患者申出療養」とは、国内未承認の医薬品などを迅速に保険外併用療養として使用してみたいという患者の思いに応えるために、患者からの申出を起点とする保険外併用療養の仕組みとして創設された制度です。
患者申出療養としては初めての医療を実施する場合
患者が国に対して申出したのち、患者申出療養評価会議による審議がおこなわれ、申請が認められた場合、原則として約6週間後に患者申出療養が実施されます。
既に患者申出療養として前例がある医療を他の医療機関が実施する場合
患者が臨床研究中核病院に対して申出したのち、臨床研究中核病院は国が示した考え方を参考に、患者に身近な医療機関の実施体制を個別に審査します。臨床研究中核病院が実施できると判断した場合、速やかに地方厚生局に届出をおこない、原則として約2週間後に、患者にとって身近な医療機関において患者申出療養が実施されます。
混合診療に関するよくある疑問
続いては、混合診療が認められるケースを踏まえたうえで、「混合診療に関するよくある疑問」とその回答を紹介していきます。
Q: 混合診療の定義における「疾病に対する一連の治療過程」とは、治療期間全体を指すのか?
A:「一連の治療過程」とは、診療がおこなわれた当日だけでなく、治療期間すべてを指します。つまり、たとえば4月1日に保険診療で治療をおこない、翌4月2日に同じ症状に対して保険外診療で治療をおこなった場合、混合診療だと判断されることになります。
Q: ひとつの疾病に対する治療を2つ以上の医療機関でおこなった場合、1つの医療機関では保険診療、そのほかの医療機関では保険外診療をおこなった場合は混合診療になるのか?
医療機関が異なる場合も、疾病が同じであれば、「一連の治療過程」と判断されます。つまり、ある疾患の治療をAクリニックにおいて保険外診療でおこなっていた場合、その疾患の治療をBクリニックにおいて保険診療でおこなうことはできないということになります。
Q.:2つ以上の疾患の治療を同じ医療機関で受けた場合、1つの疾患の治療を保険診療、そのほかの疾病の診療を保険外診療でおこなった場合は混合診療になるのか?
これに関しては、混合診療ではないと判断されます。たとえば、湿疹の症状などで皮膚科を受診した患者が、湿疹が完治していない間に、同じ医療機関において自由診療の美容点滴を受けることなども問題ありません。
Q.:保険診療での治療期間内に、ドクターズコスメやコンタクトレンズ、サプリメントを処方することは問題ないか?
A:3つめの回答で述べた美容点滴を受けた場合と同じく、これに関しても問題はありません。ただし、厚生労働省は、「療養の給付と直接関係のないサービスについては、保険診療との併用の問題が生じないことを明確化する必要がある」としています。
具体的には、ドクターズコスメやコンタクトレンズ、サプリメントなどを販売するにあたっては、サービスの内容や料金を院内のわかりやすい場所などに掲示する必要があるとされています。また、100%自費で徴収した分に関しては、保険診療とは別であることがわかる領収書を発行することが求められます。さらに、患者が商品のことをきちんと理解して、患者の意思で購入していることや、あいまいな名目で会計をおこなわないことなどもルールとされています。
Q. 患者が公費での定期予防接種と自費での任意予防接種を同時に受けることには問題はないか?
A:この場合も、まず、全問と同じく、「療養の給付と直接関係のないサービスについては、保険診療との併用の問題が生じないことを明確化する必要がある」とされています。
加えて、予防接種に関しては、初診料または再診料の診察代を保険診療と自由診療の両方で算定してしまう「二重請求」とならないよう注意する必要があります。
たとえば、市区町村が実施する定期予防接種に関しては、診察代は公費となり、ワクチン代と診察料の両方が含まれているため、同時におこなった保険診療において別途診察料を計上することが認められていません。
一方、インフルエンザの予防接種をはじめとする任意の予防接種は自由診療となり、各医療機関が自由に料金を設定できることから、「自己負担費用分はワクチン代のみで、診察料は含まない」と設定している医療機関もありますが、当該患者が別途保険診療で通院中の場合、インフルエンザの予防接種を受けた分に関して診察料を請求することは二重請求にはなりません。
この違いをよく理解したうえで、患者が公費での予防接種と自費での予防接種を両方受ける場合、もしくは他の疾患で通院中にいずれかの予防接種を受ける場合などは、二重請求になっていないかをしっかり確認する必要があるといえます 。
混合診療に関する他国の考え方は?
前述の通り、日本では原則として、混合診療は承認されていません。では、日本以外の国はどうかというと、イギリス、カナダは日本と同じく、原則として混合診療の提供を認めていません。ただし、たとえばイギリスにおいては、原則としては禁止でありながら、NHS医療(国民保健サービス)では治療困難かつNHS医療提供区間とは別の区間において診療する場合に限っては混合診療を認めています。
一方、オーストラリアはオプションとして混合診療を認めていますし、スイスでは、医師は強制保険によってカバーされない医療も実施することができることになっているなど、国によって考え方に違いがあります 。
そのため、日本に関しても、混合診療に対する考え方が今後どのように変わっていくかはわかりませんが、少なくとも、現状において、日本医師会は混合診療の容認に反対の立場をとっています。その根底には、先の説明とかぶりますが、「お金の有無で健康や生命が左右されるようなことがあってはならない」との考えがあるとされています。
参照:日本医師会 日医NEWS「混合診療ってなに? ―Q&A―」
混合診療をおこなう可能性がある場合、ルールをよく確認しよう
日本では原則として混合診療は承認されていませんが、前述の通り、混合診療が認められるケースは意外と多くあります。さらに、これから先も医療は発達し続けることを考えると、患者申出療養制度の適応となるケースも増えていく可能性が高いですし、先進医療に関する混合診療の定義に関して変化が生じる可能性もあります。そのため、「混合診療をおこなわないように気を付けよう」というスタンスでいるよりも、「患者のことを考えても混合診療がベストだと考えられる場合は、どうすればルールに抵触しないかをしっかり確認するようにしよう」という心構えでいることが大事かもしれませんね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2025年3月時点の情報を元に作成しています。





