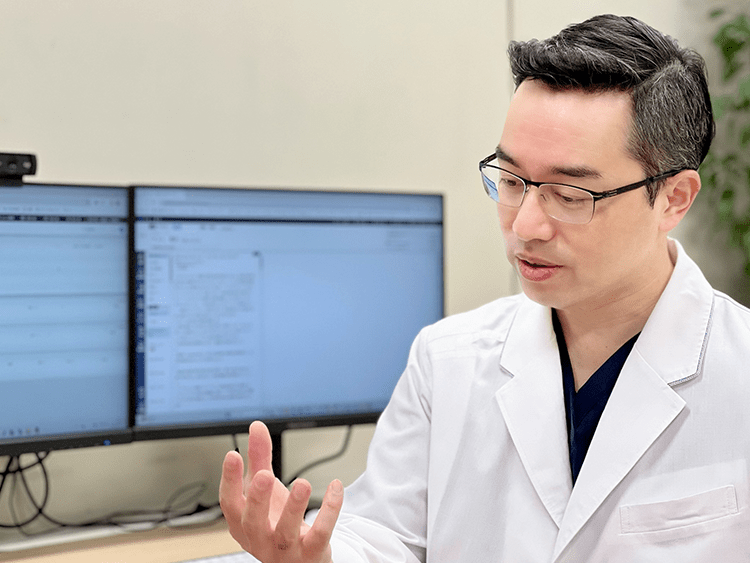CLIUSの口コミがきっかけで
問い合わせをしました
電子カルテCLIUS導入のきっかけを教えてください
2020年にびやじま内科医院・大島駅前を継承開業し、2021年に街のクリニック 立川・村山、街のクリニック日野・八王子を展開しました。もともと、各クリニックの診察状況が分かるようにしておきたいと思っていたため、インターネット環境さえあれば操作等が可能なクラウド型電子カルテを検討していました。
カルテのリサーチを始めた当時、私が参加する開業医コミュニティーで「どの電子カルテが良いか」という話題が出ており、小児科の先生が「CLIUSがすごく良かった」と書き込んでいました。自分でも調べつつ、CLIUSに問い合わせて説明を聞かせてもらいました。

CLIUSのどんな点に魅力を感じましたか?
使い勝手とUIが優れている点はさすがだと思います。 バックオフィス支援システムのジョブカンや、UIにこだわったゲームを作ってきただけあって、他のクラウド型電子カルテより使いやすかった印象です。
また、月額費用や初期費用などの料金面が安かったことも導入を後押ししました。
連携については、自分の想定しているシステムと連携しているかどうかを確認しました。具体的には、コニカミノルタさんのCRと、検体検査のSRLさんとの連携がクリアできていたため、問題なく運用できると想定しました。
▶︎製品資料を無料ダウンロード
経営状況、診察の詳細がグラフ等で一目瞭然
自身の感覚とのギャップに気づかされました
CLIUSならではのおすすめの機能は何ですか?
診察に必要な機能はどのカルテメーカーさんも開発されていると思いますが、クリニックの経営状況を確認できる「経営分析ツール」は診察の合間によくチェックしています。

※経営分析ツール:画像はダミー情報によるもの(CLIUS作成)。月次サマリで各月の大まかなグラフを一覧で見られるほか、診療区分、傷病統計、傷病分析などが可能。
お世話になっている税理士さんからは、経営状況を毎月資料化してもらっていますが、その資料とは内容や切り口が異なるので非常に参考になっています。自分の感覚との違いも確認できて、便利に使わせていただいています。
私が主に見ている項目は「傷病分析」です。患者さんの疾病の比率を見て、診察時の感覚とのすり合わせをしています。

※経営分析ツール:画像はダミー情報によるもの(CLIUS作成)。赤枠にあるように、選択した期間内の傷病件数が多い順に上から表示される。
また、「医師別処方統計」では自分が診療を行わない曜日に担当している医師ごとの、診察件数や処方の癖も見ています。当院は院内薬局なので、発注の目安に使っています。
「年齢別統計」で患者さんの年齢構成を確認することもあります。当院は急性疾患が多いこともあり、経営分析ツールでも20代〜40代の患者さんの割合が高いとの結果が出ています。ただ、60代以上の患者さんには、まだあまり来ていただけていないこともグラフで分かるため、このような年代のバランスをどのように改善すべきか、経営面からも考えています。
▶︎無料のオンラインデモをエントリー
クラウド型電子カルテという面で、実際に感じるメリットはありますか?
どこにいてもカルテ操作が可能な点は良いですね。
先述したように、私は3クリニックを運営しています。そのため、例えばAクリニックにいながら別のBクリニックの診察状況を把握できます。場合によってはBクリニックのスタッフと連絡をとって診察を助けることも可能です。
紙カルテや他のオンプレミスカルテを使っていたら、ここまで柔軟に複数医療機関の情報を追えなかったのではないかと思います。
ORCA連動型のカルテならではの
メリットを感じています
医事会計システムがクラウドORCAと連携している点はどのように考えていますか?
CLIUSが、クラウドORCAと連動していることは良いと思います。特に当院は院内処方なので、ラベルプリンターや薬剤情報印刷システムを導入していますが、カルテとレセコンが一体型になっているものだと、カルテメーカーがそれらシステムとの連携処理を行わなくてはならず、システムの選択肢が狭まってしまう可能性があります。
数々のシステムとの実績が多いORCAであれば対応可能なシステムも多く、新たな連携費用を払ってシステム構築をしていただく必要もありません。
その他自動精算機も導入していますが、全て希望する機器とレセコンとを連携することができました。
上記のようなメリットがあることと、レセコンを扱うスタッフが使う上で問題なければ、一体型でなくても十分スムーズに診察しうるのではないでしょうか。