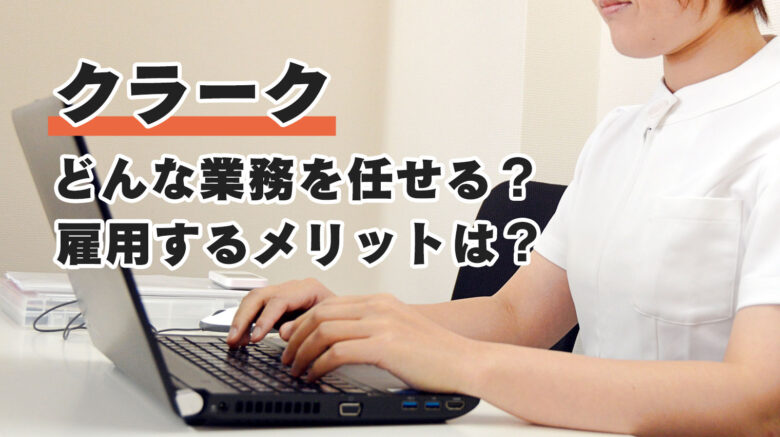
電子カルテに診療録をつけるのは医師です。看護師などの医療従事者が代行入力することは認められていません。ただし、医師事務作業補助者に限っては、代行入力することが認められています。医師事務作業補助者とはどんな職種で、どんな仕事を担当するのかを説明していきます。
電子カルテの代行は違法?
医師法第24条において、「医師は、診療をしたときは、遅延なく診療に関する事項を診療録に記録しなければならない」と定められています。この主語が医師であることから、もともと法的に診療録は医師本人がつけるべきものとされていたことがわかります。
しかし、2008年度の診療報酬改定において「医師事務作業補助者加算」が創設されたことによって、医療事務作業補助者による代行入力に限っては認められることとなりました 。つまり、代行は違法ではないということになります。
医師事務作業補助者加算とは
医師事務作業補助者加算とは、医師の負担の軽減および処遇の改善に対する体制を確保することを目的に、医師、医療関係職員、事務職員等との間での業務の役割分担を推進して、医師事務作業補助者を配置している体制を評価するものです。
前述の通り、この加算が創設されたことによって、医療事務作業補助者による代行入力が認められることになりました。
医師事務作業補助者加算が創設された背景
医師事務作業補助者加算が創設された背景には、医師の長時間労働があります。カルテ入力のほかにも、患者の診療・治療、診断書作成をはじめ仕事が山積みで、残業や休日出勤を余儀なくされている医師が多いことから、2024年4月には、「医師の働き方改革」がスタートして、医師の長時間労働の上限規制が適用されることとなりました。これに伴い、医師本来の診療業務に専念できるよう環境を整備する動きが促進されていますが、それ以前から、カルテ入力業務にかかる負担が大きいことが課題であったことから、医師事務作業補助者加算が創設されるに至ったのです。
医師事務作業補助者とは?
医師事務作業補助者とは、医師の事務的な業務をサポートする職種です。「医療クラーク」「医療秘書」「メディカルアシスタント」「ドクターズクラーク」の名称を適用している医療機関もあります。なお、医師事務作業補助者は特別な免許は必要としませんが、医師事務作業補助者として配置された職場において、6か月間のOJTを積み、厚生労働省が定める32時間以上の研修を受けることが必要とされています。
医師事務作業補助者と医療事務の違いは?
医師事務作業補助者と医療事務は、どちらも事務作業をメインにおこなう職種ですが、担当する業務は異なります。前者は、職種名の通り、医師の事務作業をサポートする役割で、医療事務は、窓口・受付業務やレセプト業務が主な仕事です。
医師事務作業補助者の仕事とは?
医師事務作業補助者に任される「医師の事務的な業務のサポート」とはどのような業務かというと以下の通りです。
それぞれ詳しく解説していきます。
電子カルテの代行入力
ここまで説明してきた通り、電子カルテの代行入力は、医師事務作業補助者の代表的な業務です。医師事務作業補助者がカルテ入力を担当してくれることによって、医師は患者の診察・治療に集中できます。ただし、入力内容に関する最終的な責任は医師にあり、医師の指示に沿って入力することが求められます。
診断書や主治医意見書などの文書作成補助
診断書や主治医意見書、処方箋、紹介状、入院診療計画書、退院療養計画書、患者と家族への説明文書、特定疾患等の申請書、損保会社等に提出する診断書といった書類の下書き・仮作成をおこなうこともあります。
診察前の予診
医師事務作業補助者は、定型の予診表を用いて、診察前の予診をおこなうことが認められています。ただし、予診といっても、医師のように患者の状態をみて病状などを判断するのではなく、予診表をもとに現在の病状や病歴などを患者にヒアリングして、その回答をそのまま入力することしかできません。
診察や検査の予約・説明
医師の具体的な指示があれば、次回診察や各種検査の予約もおこなうことが認められています。診察や検査の予約管理のためにオーダーシステムを活用している場合、患者の診察後、次回検査や検査予約をその場で代行入力することも可能です。併せて、検査のオーダーの代行入力や簡易的かつ定型的な説明、同意書受領も担当可能です。ただし、検査などに関して患者から質問があった場合、医師事務作業補助者が回答することはできません。質問があった場合には、医師や看護師に取り次ぎます。
医療行為以外に関する各種書類の説明・同意書の受領
入院に関する書類など、医療行為以外に関する各種書類の説明および同意書の受領を担当できます。
その他
他にも、医師の当直表作成、研究申請書作成などの事務作業、カンファレンスの準備などを担当することができます。また、行政上の各種システムへの入力やガン登録をはじめとするデータ入力も可能です。
医師事務作業補助者が禁止されている業務
医師事務作業補助者は、以下の業務に関してはしてはいけないことになっています。
電子カルテの代行入力による3つの利点
続いては、電子カルテの代行入力によって得られるメリットをみていきましょう。電子カルテの代行入力を利用することで得られる主なメリットは次の通りです。
詳しくみていきましょう。
医師の業務負担軽減
カルテ代行入力に加えて、先に解説した業務なども任せることができるため、医師の業務負担が軽減します。パソコンのタイピングが苦手で入力が遅い医師に関しては、特に負担の軽減度合いが大きくなることでしょう。
医師が診療・治療に集中できる
診療や治療に付随する事務的作業をおこなわなくてよくなるため、そのぶん、診療や治療に集中することができます。診療中にパソコン画面やキーボードに目を向ける必要がなくなることから、患者とのコミュニケーションの質の向上も狙えます。その結果として、患者満足度が上がる可能性も高いといえます。
患者の待ち時間短縮
医師本人が診察しながらカルテを入力すると、自ずと一人ひとりの診察時間が長くなります。タイピングが速く、ひとりあたり2分で入力していたとしても、患者10人につきタイピング時間が20分発生していることになります。これを短縮できたら患者の待ち時間が減るので、場合によっては、そのぶん多くの患者を診療できることにもなります。
医師事務作業補助者を配置するにあたってのポイント
続いては、自院に医師事務作業補助者を配置するにあたって気を付けたいことを説明していきます。
それぞれ詳しく解説していきます。
医師事務作業補助者に任せたい業務内容を考える
前述の通り、医師事務作業補助者が手掛けてよしとされている業務はいくつかありますが、そのうちどれを任せるかを事前に決めて、業務内容に関しての合意を得ておくことが大切です。
業務内容を考えるにあたっては、どの業務を任せれば医師事務作業補助体制加算をとれるかを確認することも大事です。
現場の体制の見直し
医師事務作業補助者を採用することによって、自院全体の業務の流れが変わります。そのため、現状の体制を見直して、どこがどんなふうに変わるのかをイメージしておくことが大切です。また、体制が変わることについてスタッフに周知しておくことも重要です。
教育体制を整える
前述の通り、医師事務作業補助者には特別な資格は不要です。しかし、医師事務作業補助者として配置された職場において、6か月間のOJTを積み、厚生労働省が定める32時間以上の研修を受けることが必要とされていることから、OJTの体制を整えておくことが不可欠です。とはいえ、医師事務作業補助者を採用するのが初めてであれば、医師事務作業補助者の先輩は存在しません。そのため、医師自身が、医師事務作業補助者には何が求められるのかを学び、その知識を習得できる環境を用意してあげることが大切だといえるでしょう。
医師事務作業補助者に働き続けてもらうための施策を考える
看護師や医療事務などの他のスタッフ同様、職場が合わないなどを理由に離職する可能性は否めないため、「長く働き続けてもらうには?」を考えることはとても大切です。もちろん、自院との相性がよくないスタッフに関してはその限りではありませんが、基本的には、働いてくれるスタッフに「ここで長く働きたい」と思ってもらえる環境作りを心がけることはとても大切です。
また、看護師などとは異なり、特別な資格が必要ではないことから、良くも悪くも突発的にチャレンジする人もいる可能性も考えると、医師事務作業補助者として働く誰もがモチベーションが高いとはいいきれないため、医師事務作業補助者という仕事自体にやりがいを感じてもらうために何ができるかを考えることも重要だといえます。
マニュアルの整備を検討する
先に述べた理由から、医療業界で働くこと自体が初めてというケースもあることが考えられるため、マニュアルを整備しておくと、「何をすればいいかがわかって助かる」と思ってもらえる可能性が高いといえます。
まとめ
本記事で述べてきた通り、医師事務作業補助者を導入することによって得られるメリットはいくつか考えられますが、医師自身のタイピングスキルが高い場合や、現状、クリニック全体としてそこまで多忙ではない場合などは、却って人件費がかさむ場合も考えられます。そのため、導入すべきかどうかは慎重に考えることが大事ですが、「医師事務作業補助者加算がとれる」というプラス要素もあるので、“総合するとどちらが得か?”の視点を持って検討することをおすすめしますよ。
この記事は、2021年6月時点の情報を元に作成しています。

執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
他の関連記事はこちら




