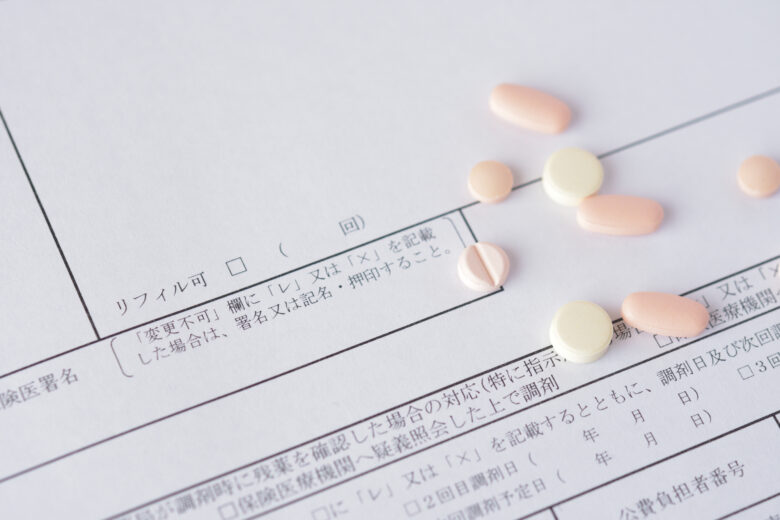
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料は、2024(令和6)年の診療報酬改定で変更があった診療報酬のうちのひとつです。どんな変更があったのか、また、そもそも在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とはどのような診療報酬であるのかを解説していきます。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とは
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料とは、入院中ではない睡眠時無呼吸症候群の患者に対して、持続陽圧呼吸療法に関する指導管理をおこなった場合に算定できる診療報酬です。
持続陽圧呼吸療法は、別名「CPAP(シーパップ)療法」といい、専用の機器で圧力をかけた空気を鼻から気道に送り込むことによって、気道を広げて、睡眠中に無呼吸となることを防ぐ治療法です。機器は、15~20cm程度の本体と、あらかじめ設定した圧力で空気を送るチューブ、鼻に当てるマスクで構成されています。
なお、圧力の設定は、常に一定に保つパターンと、無呼吸のときに自動的に圧力を大きくするパターンの2つにわけられ、どちらのパターンに設定するかは患者の症状に応じて医師が決めますが、前者をCPAP(連続陽圧呼吸器)、後者をASV(自動起動圧力装置)と呼び分けることがあります。
参照:一般社団法人日本呼吸器学会「CPAP(シーパップ)とはどのような治療法ですか?」
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の対象患者とは
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定するためには、患者が、対象患者の条件を満たしていなければなりません。対象患者の条件は、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1」と「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2」で異なります。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者
以下の2項目に当てはまる患者は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象となります。
①慢性心不全患者のうち、医師の判断により、NYHA III度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間あたりの無呼吸数および低呼吸のこと)が20以上であることが、睡眠ポリグラフィー上において確認されているもの
②CPAP療法を実施したにもかかわらず、無呼吸低呼吸指数が15以下にならない者に対してASV療法を実施したもの
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者
以下の3項目に当てはまる患者は、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象となります。
①慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHA III度以上であると認められ、睡眠時にチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上において確認されているもので、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1の対象患者以外にASV療法を実施した場合
②心不全である者のうち、日本循環器学会・日本心不全学会によるASV適正使用に関するステートメントに留意したうえで、ASV療法を継続せざるを得ない場合
③次の(イ)から(ハ)までのすべての基準に該当する患者。ただし、無呼吸低呼吸指数が40以上である患者に対しては、(ロ)の要件を満たせば対象患者となる
(イ)無呼吸低呼吸指数(1時間あたりの無呼吸および低呼吸をいう)が20以上である
(ロ)日中の傾眠、起床時の頭痛などの自覚症状が強く、日常生活に支障をきたしている症例である
(ハ)睡眠ポリグラフィー上、頻回の睡眠時無呼吸が原因で、睡眠の分断化、深睡眠が著しく減少または欠如し、持続陽圧呼吸療法によって睡眠ポリグラフィー上、睡眠の分断が消失、深睡眠が出現して、睡眠段階が正常化する症例である
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の算定要件は
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定するためには、以下の要件を満たしている必要があります。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の点数は
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の点数は次の通りです。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の加算とは
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の対象患者に対しては、2種類の加算点数を算定できる場合があります。
遠隔モニタリング加算
在宅で持続陽圧呼吸療法をおこなっている睡眠時無呼吸症候群等の患者に対して、情報通信機器等を使用して遠隔での指導管理をおこなった場合に算定できる診療報酬です。ただし、当該医療機関は、情報通信機器を用いた診察をおこなうために十分な体制が整備されており、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保健医療機関である必要があります 。
【算定要件】
【点数】
150点/月
【注意点】
遠隔モニタリング加算は、対面で診療をおこなった翌月から次回対面での診療をおこなう前月までの期間に、遠隔での指導管理をおこなった場合に算定できます。なお、遠隔モニタリングをおこなう場合、オンライン診療料は算定することができません。
情報通信機器使用時の加算
厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局等に届け出た保健医療機関において、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定すべき指導管理を、情報通信機器を用いておこなった場合に算定されます。なお、情報通信機器を用いた場合の加算は、2024年診療報酬改定によって新設されたもので、外来診療をオンラインでおこなった際に加算することができます 。
【算定要件】
【点数】
218点
【注意点】
情報通信機器を用いた指導管理については、CPAP療法を開始したことによって睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを、対面診療で確認した場合に実施することが必要です。また、通常の対面診療で確認するCPAP管理に係るデータについて、情報通信機器を用いた診療において確認することや、睡眠時無呼吸症候群に合併する身体疾患管理の必要性に応じて対面診療を適切に組み合わせること、情報通信機器を用いた診療を開始したあとに症状の悪化などが生じた場合は、速やかに対面診療に切り替えることが求められます。
また、当該診療に係る初診日およびCPAP療法を開始したことによって睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを、対面診療で確認した日を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する必要があります 。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に関するよくある質問
続いては、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料に関するよくある質問とその回答をみていきます。
Q:遠隔モニタリング加算について、「療養上必要な指導」を医師以外がおこなった場合も加算することができるか?
A:看護師など、医師以外のスタッフが指導をおこなった場合は、算定することができません。
Q:遠隔モニタリング加算について、遠隔モニタリングで療養上必要な指導をおこなった場合、情報通信機器を用いた診療に係る基本診察料を別途算定することができるか?
A:できません。当該診療に係る基本診療料は、なぜかというと、遠隔モニタリング加算に包括されているためです。
Q:遠隔モニタリング加算について、モニタリングをおこなった結果、その時点で急を要する指導事項がなかったことから、療養上の指導をおこなわなかった場合にも加算することができるのか?
A:遠隔モニタリング加算は、あらかじめ作成した診療計画に沿ってモニタリングをおこない、それによって得られた臨床所見に応じて、療養上の指導などをおこなった場合の評価であるため、モニタリングをおこなっても、療養上の指導をおこなった場合には算定することができません。
Q:遠隔モニタリング加算について、ビデオなどのリアルタイムの資格情報を含まない、電話などの情報通信機器を用いた指導も対象になるのか?
A:原則としては、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いたものであることが求められます。ただし、遠隔モニタリング加算が、あらかじめ作成した診療計画にとって、モニタリングによって得られた臨床所見に応じて、療養上の指導などをおこなった場合の評価であることを十分に理解して実践しており、かつ、患者から事前に合意を得ている場合に限っては、電話などの情報通信機器を用いることも認められています。
Q:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2は、医師の診察がない月は算定できないのか?
A:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2は、医師の診察がない月は算定することができません。ただし、前述の通り、情報通信機器等を使用して遠隔で指導管理をおこなった場合も、「医師の診察があった」ということになるため加算可能です。
Q:在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定がない月でも、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算と在宅持続陽圧呼吸療法材料加算は算定可能であるか?
A:まず、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算とは、名称から想像できる通り、在宅持続陽圧呼吸療法をおこなっている患者に対して、両方をおこなうための専用機器である「経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器」を使用した場合に加算できる点数です。また、在宅持続陽圧呼吸療法材料加算には、装置に必要な回路部分やそのほかの付属品などに係る費用が含まれます が、いずれも、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2の算定がない月には算定することができません。
ただし、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定する月に、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2を算定できなかった月のぶんの在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算と在宅持続陽圧呼吸療法材料加算を算定することはできます。
なお、CPAP療法に関する算定をとるためには、原則として毎月診察する必要があります。ただし、やむを得ない場合、3か月に1回の診察で認められることもあります。
つまり、たとえばCPAP装置を継続的に使用している患者に対して、1月2月に診察をおこなわず、3月に診察をおこなった場合、3月に算定できる点数は以下の通りです。
なお、在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算の点数は、2024年の診療報酬改定によって1,000点から960点に改定されています 。
Q:情報通信機器を用いた指導管理について、「CPAP療法を開始したことによって睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを、対面診療で確認した場合に実施することが必要」とされているが、他の医療機関でCPAP療法を開始した患者が紹介された場合はどうすればいいのか?
A:当該指導管理を実施する医療機関において、CPAP療法を開始したことによって睡眠時無呼吸症候群の症状である眠気やいびきなどの症状が改善していることを対面診療で確認できた場合に限り、情報通信機器を用いた指導管理に対する加算を算定することができます。なお、症状が改善していることを確認した日を診療録および診療報酬明細書の摘要欄に記載することが必要です。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料をしっかり算定するにも、患者とのコミュニケーションを大事にしよう
先に述べた通り、医師による診察がない月は、CPAP療法に関する加点は何もとれませんが、診察の有無は、医師の都合だけによるものではありません。そのため、患者にきちんと受診してもらうためにも、患者とのコミュニケーションも大切にすることは不可欠。もちろん、これは在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料以外の診療報酬についてもいえることなので、あらためて患者とのコミュニケーションを見直してみることもおすすめですよ。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2025年3月時点の情報を元に作成しています。





