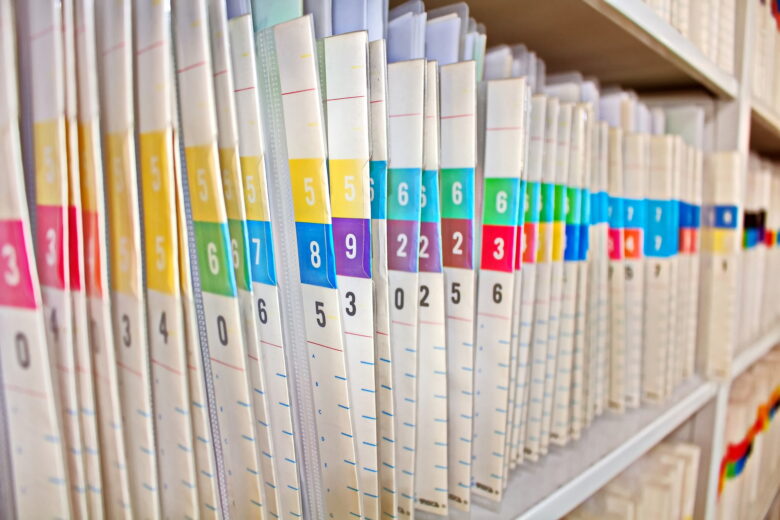
医療機関で作成した書類は、一定期間にわたって保存することが必要です。また、保存が必要とされる期間は書類によって異なるため、保存期間を正しく理解しておくことが大切です。そこで今回は、医療機関で作成するさまざまな書類の保存期間を説明していきます。
医療機関で作成した書類は、なぜ保存期間が定められているのか?
まずは、医療機関で作成した書類は、なぜ保存期間が定められているのかを解説していきます。医療機関で作成する書類には、医師法や医療法などの法律によって保存期間が定められています。つまり、「保存義務がある」ということになります。定められた期間が終わっていないのに、紛失したり破棄したりした場合、法律違反とみなされます。場合によっては罰則も科されるので注意が必要です。
医療機関が書類の保存期間に関して違反した場合の罰則は?
医療機関が書類の保存期間に関して違反した場合、どんな罰則が科されるかというと、その書類にもよりますが、たとえば書類の保存期間が医師法で定められていた場合、医師法に違反することになり、3年以下の懲役または100万円以下の罰則が科される可能性があります。
そのほか、医療法に基づいて業務停止命令を受けることや、個人情報保護法に基づいて勧告・命令・罰金などの対象となる可能性もあります。
こうした事態を防ぐためにも、コンプライアンス遵守の観点からも、適切に書類を管理することは極めて大切であるといえます。
医療機関の書類の保存期間の起算日は?
医療機関で保存期間が定められている書類において、その起算日はいつとすればよいかに関して、たとえば保険医療機関および保険医療養担当規則 第9条では、「保健医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿および書類その他の記録をその完結の日から3年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から5年間とする」と定められています。つまりこの場合、「診療が終わった日」が起算日ということになりますが、その後、再診があった場合はもちろん、起算日がずれることになります。
このように、起算日は多くの場合『その書類に係る業務が完了した日』となりますが、具体的にいつを指すかは書類の種類や根拠法によって異なります。たとえば、診療録は一般的に『最終診療日』、歯科技工指示書は『歯科技工が終了した日』、検査記録は『検査日』や『結果報告日』などが考えられます。自院で扱う各書類について、どの時点が起算日とされているか明確にしておくことが重要です。
医療機関の書類は、保存期間が過ぎたら捨てていい?
医療機関で作成した書類を保存期間が過ぎたら破棄することは、法律的には問題ありません。しかし、書類を破棄するリスクはゼロではありません。
たとえば、適切な医療行為をとっていたにも関わらず医療ミスで訴えられたとして、訴えられたのがカルテの保存期間終了後でカルテを破棄していれば、自院に非がないことを証明できず不利になる可能性もあるかもしれません。そのため、保存期間終了後の書類の破棄は法律的には問題がないとしても、できる限り長く保存しておくことが望ましいといえます。
また、過去の診療情報が患者自身の健康管理や将来の診療に役立つ場合や、医学研究・公衆衛生の向上に寄与する可能性も考慮すると、可能な限り長期で保存することが望ましいといえます。
医療機関の書類の保存は、書類の種類によっては20年以上が望ましい
「できる限り長く保存」とは具体的にどのくらいの長さかというと、カルテに関しては「20年」もしくは「永久」と考えられます。なぜかというと、損害賠償請求権の消滅時効が、損害および加害者を知ったときから3年、不法行為がおこなわれたときから20年とされているためです。
さらに、カルテが紙カルテではなく電子カルテの場合、日本医師会は、次の3つの理由から永久保存を目指すべきであるとしています。
① 電子データの保存にかかるコストが紙カルテと比較して低い
② 過去の診療情報が将来の医療の質向上に役立つ
③ 遺伝性疾患など、世代を超えて参照が必要となるケースに対応できるため
上記理由をみると、訴訟のリスク軽減のためであれば最低20年であっても、永久的に保存するほうがより確かな意義があるということがよくわかります。
また、紙カルテから電子カルテに切り替えておけば、少なくともカルテの保存に関しては手間がかからないので、電子カルテへの切り替えがまだの医療機関は、早めに切り替えることをおすすめします。
医療機関で保存期間が定められている主な書類の保存期間
続いては、医療機関で保存期間が定められている主な書類の保存期間をみていきましょう。
主要な書類の保存期間一覧
| 書類の種類 | 保存期間 | 根拠法等 | 保存義務者(主な例) | 起算日(主な例) |
| 診療録(カルテ) | 5年 | 医師法、歯科医師法 | 管理者、作成医師・歯科医師 | 診療完結の日 |
| 助産録 | 5年 | 保健師助産師看護師法 | 管理者、作成助産師 | 助産完結の日 |
| 処方箋(※1) | 3年 (5年) | 薬剤師法 | 薬局開設者 | 調剤済みの日 |
| 調剤録 | 3年 | 薬剤師法 | 薬局開設者 | 調剤済みの日 |
| 麻薬処方箋(調剤済み) | 3年 (院外) / 2年 (院内) | 麻薬及び向精神薬取締法 | 薬局開設者 / 麻薬管理者 | 調剤済みの日 |
| 麻薬帳簿 | 2年 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 麻薬管理者 | 最終記入の日 |
| 施術録 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師) | 5年 | 各関連法規 | 施術者 | 施術完結の日 |
| 救急救命処置録 | 5年 | 救急救命士法 | 指定機関の長、救急救命士 | 記載の日 |
| 病院日誌、各科診療日誌、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、退院サマリ等 | 2年 | 医療法施行規則 | 管理者 | 各記録の作成・完了日等 |
| 歯科技工指示書 | 2年 | 歯科技工士法 | 管理者 | 歯科技工終了の日 |
| 紹介状(控え) | 2年 | 医療法施行規則(※2) | 管理者 | 作成日 |
| 診断書(控え) | 5年 (推奨) | (法令上の明確な規定はないが、診療録に準ずる) | 管理者、作成医師 | 作成日 |
| 同意書 | 5年 (推奨) | (法令上の明確な規定はないが、診療録に準ずる) | 管理者 | 同意取得日/関連診療完結日 |
| 診療報酬明細書(レセプト)控 | 3年 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 保険医療機関 | 診療完結の日 |
| 療養費支給申請書等(帳簿) | 3年 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則 | 保険医療機関 | 完結の日 |
| 労働者名簿、賃金台帳等 | 5年 | 労働基準法 | 使用者 | 最終記入日等 |
| 会計帳簿、計算書類等(医療法人) | 10年 (会社法) / 7年 (税法) | 会社法、法人税法等 | 医療法人 | 事業年度末等 |
※1 処方箋: 2025年4月現在、保存期間は3年ですが、厚生労働省は5年への延長を目指し、2025年の通常国会で薬剤師法改正案の提出を予定しています。
※2 紹介状(控え): 医療法施行規則第21条の5に定める「診療に関する諸記録」に含まれると解釈されます。
注意: 上記は主な例であり、個別のケースや他の法令(条例を含む)により異なる場合があります。必ずご自身の状況に合わせて関係法令をご確認ください。
診療録(医療機関):5年
医師法第24条において、次のように定められています。
「医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
その2:前項の診療録であって、病院または診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院または診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、5年間これを保存しなければならない」
保存義務者は、病院または診療所の管理者、作成医師とされています。
診療録(歯科):5年
歯科医師法第23条において、次のように定められています。
「歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
その:前項の診療録であって、病院または診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院または診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、5年間これを保存しなければならない」
保存義務者は、病院または診療所の管理者、作成歯科医師とされています。
助産録:5年
保健師助産師看護師法第42条において、次のように定められています。
「助産師が分べんの介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
その2:前項の助産録であって病院、診療所または助産所に勤務する助産師がおこなった助産に関するものは、その病院、診療所または助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産師において、5年間これを保存しなければならない」
保存義務者は、病院、診療所または助産所の管理者、作成助産師とされています。
病院、診療所または歯科技工所でおこなわれた歯科技工に係る指示書:2年
歯科技工士法第19条において、次のように定められています。
「病院、診療所または歯科技工所の管理者は、当該病院、診療所または歯科技工所で行われた歯科技工に係る前条の指示書を、当該歯科技工が終了した日から起算して2年間、保存しなければならない」
保存義務者は、病院、診療所または歯科技工所の管理者とされています。
救急救命処置緑:5年
救命救急士法第46条において、次のように定められています。
「救急救命士は、救急救命処置をおこなったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。
その2: 前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものはその機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその救急救命士において、その記載の日から5年間、これを保存しなければならない」
保存義務は、病院、診療所の管理者、消防機関の長、救急救命士とされています。
照射緑:作成の義務のみで保存期間の定めなし
診療放射線技師法第28条において、次のように定められています。
「診療放射線技師は、放射線の人体に対する照射をしたときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を記載した照射録を作成し、その照射について指示をした医師または歯科医師の署名を受けなければならない」
処方箋:5年に延長する方針
処方箋の保存期間は、これまで3年とされていましたが、2025年の通常国会で薬剤師法の改正を目指し、5年に延長する方針であることが、厚生労働省によって発表されています。
予防接種:5年
厚生労働省は、新型コロナウイルスなどのワクチン接種記録の保存期間の延長期間に関して、2026年度にも、5年に延長する方針であることを公表しています。
病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者・外来患者の数を明らかにする帳簿:2年
医療法施行規則第21条の5において、次のように定められています。
「診療に関する諸記録は、過去2年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする」
医療機関における特殊な書類の保存期間
続いては、医療機関における特殊な書類の保存期間を確認していきましょう。
麻薬処方箋:3年または2年
調剤済みの麻薬処方箋は、院外処方箋の場合は3年、院内処方箋の場合(麻薬管理者が保管)の場合は2年間の保管が義務付けられています。
労働災害に関する書類
労働災害に関する書類は、労働基準法第109条によって、5年間の保存が定められています。条文は次の通りです。
「使用者は、労働者名簿、賃金台帳および雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を5年間保存しなければならない」
医療機関における書類の保存に関するよくある質問は?
続いては、医療機関における書類の保存に関するよくある質問とその回答を紹介していきます。
Q. 紙の書類を効率よく、かつ適切に保存するコツはある?
A.紙の書類を効率的かつ適切に保存するために、外部の文書保管サービスの利用を検討するのも一手です。外部のサービスを利用すれば、セキュリティ対策が万全かつ、自院で保管スペースを確保する必要がないため、長期間の品質保持にもつながります。
Q.書類保管をクラウドサービスまたは倉庫などの外部委託にする場合の注意点は?
A. 委託先が個人情報保護法や医療情報ガイドラインを遵守しているか確認することが不可欠です。また、契約時には、セキュリティ体制、責任範囲、データの取り扱い(アクセス権限、バックアップ、災害時対応)、契約終了時のデータ返却・削除方法などを明確にして、契約書に記載することが重要です。
Q. 書類を保存するにあたっての注意点は?
A.電子データの場合、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1半」によると、「データを触った人の記録を取ること・データが改ざんされていないこと」(真正性)「いつでもすぐ書面に出力して管理できるようデータを整理しておくこと」(見読性)「期間中、確実に保存されていること」(保存性)のほか、「データ破損や漏洩などを防げるシステムを完備すること」(セキュリティ対策)などが特に大切であるとされています。
参照:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1版(令和3年1月)」
Q. 保存期限切れの書類の適切な廃棄方法は?
A.保存期限切れの書類の適切な廃棄方法は主に2つ考えられます。書類が紙の場合、自院にてシュレッダーで処理する方法と、機密文書処理業者に委託する方法があります。後者の場合、溶解処理などを施すことになりますが、確実な廃棄を約束してくれる、廃棄証明書を発行している業者を選ぶと安心です。
また、どちらの方法を選択する場合も、個人情報や診療情報が含まれている書類であるため、万全の情報漏えい対策が不可欠です。電子データに関しては、電子署名やタイムスタンプを付与した電子データ自体は廃棄することなくとっておくことがおすすめです。もし廃棄する場合は、復元不可能な状態にもっていくために、専用ソフトによる完全消去や物理的破壊が推奨されます。
書類の作成は原則電子、保存期間は原則永久がおすすめ
医療機関において大切な書類を作成する場合、基本的には電子データで作成することがおすすめです。紙で作成した場合、後々、廃棄に手間やコストがかかる場合もありますし、保管スペースの確保も必要になります。一方、電子データは保管スペースの確保が必要でないばかりか、後世の医療従事者がデータにアクセスすることで医療の発展に役立てられる可能性も高いので、視野を広く持てば、「これからの時代はデータの保存は電子一択!」という結論に至るはずですよ。
ただし、すべての書類をすぐに電子化・永久保存することが難しい場合もあるでしょう。重要なのは、自院で扱う書類の種類ごとに、根拠となる法律に基づく保存期間、院内での保存期間(法定期間より長く設定する場合)、保存方法(紙・電子、院内・外部)、起算日、廃棄ルールを明確に定め、マニュアル化して、全スタッフに周知を徹底することです。定期的にルールを見直して、運用状況を確認することも忘れないでください。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。





