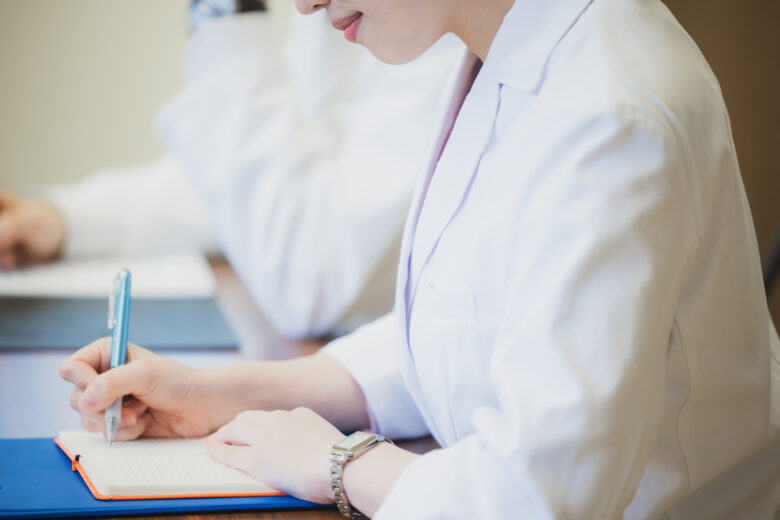
医療は日々進歩しています。それに伴い、臨床の場で求められることも更新され続けています。そのニーズに応え続けるためにも、看護師としてのキャリアをスタートしてからも学び続けることが大切です。
さもなければ、同期からも後輩からも、知識面・スキル面で大きな差をつけられてしまいます。そうとわかっていても、なかなか勉強する時間を捻出できない人も多いのかもしれません。
一方で、同じように忙しく働いているなかで、勉強する時間を確保している人がいるのも事実です。
そこで今回は、勉強時間の確保術や学ぶべき内容などを解説していきます。
看護師は日常的にどれくらい勉強している?
まずは、一般的に看護師は、日常においてどのくらい勉強しているのかをみていきましょう。
『株式会社Donuts』が独自に行ったアンケートの結果、勉強時間は多い人で、週換算で3~5時間程度、もしくは1日あたり30分~1時間程度であることがわかっています。
また、机について勉強する習慣はないものの、「わからないことがあったときにはタブレットなどで調べる」という人はとても多く、そういう人は、新しい部署に異動になった際などには、できないこと・わからないことがないようにと、事前に空き時間に専門誌を読むなどして知識を吸収している傾向にあるようです。
ただし、知識の吸収に熱心な人がいる一方で、「新人のころはそれなりに勉強していたものの、ある程度経験を重ねてからは勉強の時間は取らなくなった」という人も大勢いました。
なお、総務省統計局が2021年に実施した「令和3年社会生活基本調査」によると、社会人全体の勉強時間の平均時間は1日あたり13分となっていますが、看護師と同様に2割強の人が勉強の習慣がある一方で、8割弱の人がほとんど勉強していないことから、平均をとると短い時間となっていることが推測されます。
参照: 総務省統計局「令和3年社会生活基本調査」1日の生活時間の配分
看護師の勉強内容は?
続いては、看護師は具体的にどんなことを勉強しているのかをみていきましょう。看護師が日々、勉強していることとしては、主に次のようなことが考えられます。
- 日々の業務でわからなかったこと、復習
- 新たに配属される診療科、受け持ちする患者の症例に関する予習
- 資格取得のための学習
- 転職・キャリアアップのための学習
それぞれ詳しくみていきましょう。
日々の業務でわからなかったこと、復習
日々の業務でわからなかったことを調べたり、うまくできなかったことを復習したりしている看護師はもっとも多いでしょう。わからないことをわからないままにしておくと、その後の業務で差支えがあるためです。
新たに配属される診療科、受け持ちする患者の症例に関する予習
新たな配属先、これから担当する患者の病態などについて、事前にしっかり勉強しておくことも、業務上、必要な勉強といえます。
資格取得のための学習
認定看護師や専門看護師などの資格取得を目指している場合、必要な単位を取得して、試験に合格しなくてはならないため、勉強することが不可欠です。
転職・キャリアアップのための学習
転職やキャリアアップのために、今の自分にはない知識や技術を身に着けたいなら、資格試験のため以上に勉強しなくてはならないこともあります。
現役看護師の勉強時間と効率的な学習法ツール活用の実例も紹介
医療の進歩や自身の成長、多岐にわたる処置に対応するためなど、看護師は日々勉強を行う必要があります。
しかし、日常の業務が忙しく、勉強時間を確保するのが大変……という方も多いのではないでしょうか。そこで『株式会社Donuts』では現役看護師に独自アンケートを行い、実際にどう勉強時間を確保しているのか?またその際に使用しているツールは何か?などを調査しました。以下でその結果をご紹介していきます。
SNSやアプリで隙間時間に学習
「本とInstagramでの情報収集、アプリを使って勉強しています。インスタやアプリは気になったときにすぐに調べられる手軽さがあります。勉強時間は週に3時間程度です」(すー/30代前半・女性)
「インスタやYouTubeで学んでいるほか、看護技術の専門書も読みます。家事や育児で余裕がないため、月に15分×3回程度です」(pon/30代後半・女性)
SNSやYouTubeは短時間で最新情報を収集でき、動画で処置の方法などを視覚的に理解できる点が人気です。
特にInstagramの看護系アカウントでは、よく間違えやすいポイントをピンポイントで紹介してくれるため、効率的に知識を補えます。
タブレットでまとめて印刷、自分用メモとして活用
「覚えたいことをタブレットでまとめて、まとめたものは印刷して自分の仕事用のメモに貼っています。勉強の頻度は週に1回程度です」(のりか/20代後半・女性)
「わからない単語や初めて実践する技術があるとき、タブレットで検索して習得しています。夜勤の休憩時間を活用することが多く、勉強時間は週1~2時間程度です」(とも/20代後半・女性)
タブレットを使えば、電子カルテに慣れた現場でもスムーズに情報整理が可能です。重要事項は付箋に書き写して目に見える位置に貼ると、さらに効率的に復習できます。
eラーニングやオンライン研修で体系的に学習
「『ナーシング・スキル』を活用して勉強していました。動画で視覚的に学べる点がとてもわかりやすく役立ちました」(ナースしずく/50代後半・女性)
「体系立てて書籍で学ぶことは今はやっていません。業務に必要なことをその都度ネットで調べることが多く、オンライン研修は平日夜に受けられるものがあれば申し込んでいます。勉強時間は研修があれば1〜2時間、それ以外は週1〜2時間程度です」(なこまる/40代後半・女性)
eラーニングやオンライン研修は、場所や時間に縛られず学習できるため、忙しい看護師に向いています。動画で手順を視覚的に理解できることも大きなメリットです。
書籍を使った集中学習
「現在はネットで調べる程度ですが、新人時代は『はじめての〇〇』などの参考書や、自分の診療科関連の参考書を使ってチーム内の処置について調べていました。勉強時間は勤務後30分〜1時間程度で、疲れて何もできない日も多かったです」(とも/30代後半・女性)
「参考書を購入して業務で使用するノートに必要事項や勉強内容をまとめ、見返せるようにしています。勉強時間は1日3時間程度です」(penguimm/20代後半・女性)
書籍は情報の正確性が高く、スマホやネットの通知に邪魔されず集中して学習できる点がメリットです。
勉強時間を確保するための工夫
現役看護師の体験談から見えてくるのは、忙しい日常でも勉強を継続するための工夫です。
- SNSやアプリで最新情報を手軽に取得
- タブレットや印刷で自分用のメモを作成
- eラーニングやオンライン研修で時間と場所を選ばず学習
- 書籍で集中して深く学ぶ時間を確保
新しい環境や処置に対応するため、学習スタイルをキャリアや状況に合わせて変えることも大切です。これらの方法を参考に、自分に合った勉強方法を見つけることが、現場力アップにつながります。
勉強時間が取れない・忙しい看護師のための対策
上記で紹介した勉強方法以外にも、忙しい中でも勉強できるようになるためのポイントをいくつかご紹介します。
- まずは「1日5分」を続ける
- 仲間と一緒に勉強する
- 月単位などでテーマとゴールを設定する
- 学習ハードルを下げるツールを活用する
それぞれ詳しくみていきましょう。
まずは「1日5分」を続ける
「毎日勉強しなくては」と思うと、「疲れていて一刻も早く寝たい日があるのに、絶対無理……」とそれだけで気持ちが萎えがちです。
しかし、「1日5分でOK」ということなら、隙間時間にも実践できるため、「私にもできるかもしれない」と思える人が多いのではないでしょうか?
たとえば、「毎日、1つの疾患について掘り下げる」などテーマを決めて、就業前の5分、寝る前の5分などを活用します。
なお、「1日5分」を続けるうえで大切なことは、「5分以上はやらないこと」です。たとえば寝る前の5分を勉強時間に充てるなら、「5分経ったら勉強の途中であっても、続きは明日ということにして就寝する」ということにしたほうが、却って長く続けられるのです。
「今日は5分以内で終わらないから15分やろう」などを繰り返していると、結局長時間勉強しないといけない日が増えてしまい、その結果として続かなくなる可能性が高いためです。もちろん、「1日15分」と決めている場合は15分までは勉強してOKです。
また、25分間の作業セッション「ポモドーロ」の後に5分間の休憩をとることを4回繰り返した後、30分程度の長めの休憩と取る「ポモドーロテクニック」と同じ原理で、中断となってしまうと、「あしたは続きからやろう」という気持ちが働くため、翌日、スムーズに勉強に入りやすいと考えられます。
1日〇分を習慣づけるには、同じ時間に勉強することも大切です。
朝の10分間で「復習+今日使う知識を予習」
朝型の人は、これまでより10分早く出勤することを習慣づけて、就業前に、前述に覚えたことを確認して、当日必要なことを調べて知識をアップデートさせるのも一手です。
夜の15分間で「その日の気付きをメモ+調べもの」
夜の時間帯の勉強なら、その日の気付きを忘れないようにタブレットやノートに書き出したり、その日わからなかったことを調べたりするといいでしょう。
仲間と一緒に勉強する
一緒に勉強する仲間がいれば、切磋琢磨し合うことができるため、「みんなに負けないように自分もがんばろう」という気持ちになれます。
ただし、「決まった時間に決まったメンバーで勉強する」などのやりかただと、続けられないどころか、予定が合わずに、はじめることさえできないので、「LINEグループなどを作ってその日の勉強内容を報告し合う」「月に一度程度はZOOMなどでつながり問題を出し合う」などの方法でお互いを励まし合うことがおすすめです。
月単位などでテーマとゴールを設定する
8月は「糖尿病」、9月は「感染管理」、10月は「在宅医療」などとテーマを決めて、テーマごとに勉強のゴールを決めるとモチベーションがアップしやすくなります。
学習ハードルを下げるツールを活用する
先に紹介した通り、InstagramやYouTube、看護師向けアプリなどを活用して、SNSをチェックするような感覚で学びを続けている人は多いです。この勉強法だと、通勤時間や休憩時間に自発的にスマホでチェックしたくなるため、「勉強している」という感覚なしに学び続けられるでしょう。
なお、おすすめのツールについては、このあと続けて解説していきます。
看護師の勉強に役立つアプリやサービスとは?
続いては、看護師の勉強に役立つアプリやサービスを紹介していきます。
臨床現場で役立つ知識が身につくアプリ
まずは、臨床の現場で役に立つ知識が身につくアプリを紹介していきます。
120年以上の歴史がある医学事典のアプリ版「MSDマニュアルプロフェッショナル版」
医師の利用者が多い医学事典をアプリ化した「MSNマニュアルプロフェッショナル版」は、完全無料で、医学ニュースやコラムなどの多彩なコンテンツを提供しています。ただし、掲載されている動画や計算ツールのなかには、英語表記しかないものもあるため、わからないことがあれば自分で調べる必要があります。
参照: App Store「MSDマニュアルプロフェッショナル版」 Google Play「MSDマニュアルプロフェッショナル版」
わからない略語をすぐに調べられる『医療略語がわかる!医療略語辞書アプリ「ポケットブレイン」』
臨床の現場などでわからない用語が出てきたとき、その用語を直接入力して検索することができるアプリです。また、診療科別の用語検索もできるため、業務に入る前に予習したいときなどにも活用できます。
参照: App Store『医療略語がわかる!医療略語辞書アプリ「ポケットブレイン」』 Google Play『医療略語がわかる!医療略語辞書アプリ「ポケットブレイン」』
「心電図シミュレーター」
動く心電図波形を見ながら、その波形の特徴、他の波形の鑑別、対応の方法などを学べる勉強用アプリです。
次々と出現するさまざまな心電図波形から、制限時間内に正しい波形を選ぶ「チャレンジ」のほか、初心者向けのモードである「教科書モード」や「復習モード」なども搭載しています。
また、全国での自分の実力がわかる「ランキング」も搭載しています。
これらのほかにも、Google PlayやApp Storeで「看護師」などのキーワードで検索するとさまざまなアプリがヒットするので、自分にぴったりなアプリを見つけたい人はキーワード検索がおすすめです。
看護師の経験年数別勉強のポイント
忙しい中でも貴重な時間をあまり無駄にせず、効率的に勉強をしていくために、看護師キャリア別の勉強のポイントをみていきましょう。
1年目~5年未満の新人・若手看護師の勉強のポイント
1年目~5年未満の新人・若手時代は、初めての経験も多く、そのぶん、覚えなければならないことがたくさんあるので、自ずと日々の業務の復習が勉強の中心となってくるでしょう。
この時期に勉強の精度を上げるためには次のすべての点をおさえることが大事です。
- 仕事中にわからないことがあればその場で医師や先輩看護師に質問する
- 業務が立て込んでいるなどの状況でその場では質問すべきでない場合、ネットや本を活用して自分で調べる
- 調べてもわからないことがあれば、タイミングを見計らって先輩看護師などに教えてもらう
- 学んだことをタブレットやメモに残して、新しい知識と技術を吸収できるよう復習する
5年目以降の中堅看護師の勉強のポイント
5年目以降の中堅またはベテラン看護師になってくると、看護の知識や技術には自信が持てていることが多いですが、その先のキャリアアップを見据えているなら、資格取得や転職などの具体的な目標を掲げて勉強を重ねていくことが大切です。
また、新人教育やリーダー業務を任される機会が増えてくるため、マネジメントについても勉強しておきたいところです。特に、主任や師長などの管理職を視野に入れている場合、マネジメントの勉強会や研修に参加して、より高いレベルのマネジメント能力を身に着けたいところです。
休職明けのブランクのある看護師の勉強のポイント
出産や子育て・介護などのために、数か月~数年のブランクがある看護師が現場に復帰する際には、採血や清潔ケアなどの基礎的なことからすべて復習しておくと安心です。
インターネットや書籍を活用して自分で復習することももちろん可能ですし、ひとりでの学習だと不安な気持ちを拭いきれないなら、都道府県ナースセンターが実施する研修に参加することもおすすめです。
参照: ナースセンター「子育て中・離職中の看護職への復職をサポート」
まとめ|看護師の勉強は「時間の長さ」より「質と継続」
社会人になっても勉強し続けることは決して簡単なことではありませんが、一度習慣づけてしまえば、続けることはそんなに難しいことではありません。しかも、日々の努力が積み重なって将来のキャリアの選択肢が広がっていくので、「勉強しておいてよかった」と思える日が必ずくるはずです。
なお、継続のためには、ここまで解説してきた通り、「続けやすい方法」を見つけることが大切ですし、1日5分や週に1回30分でもいいので、とにかく続けることがなによりも大切です。
最初のうちは、「明日もまた勉強しなきゃだなんてしんどいな……」と思うこともあるかもしれませんが、「継続は力なり」であることは間違いないので、まずは1週間続けることを目標に掲げて、少しずつ慣れていってくださいね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
他の関連記事はこちら





