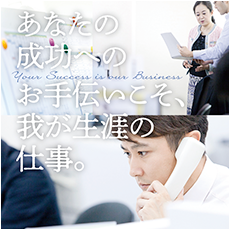クリニックを開業するにあたっては、標榜科目を決める必要があります。その際、自院について正しくつたえることはもちろん、ルールを守ることも大切です。具体的にどのようなことを考慮しながら標榜科目を決めればいいのかを解説していきます。
標榜科目の意味とは
標榜科目とは、医療機関が看板やホームページに標榜している(掲げている)診療科名のことです。なぜ標榜する必要があるかというと、クリニック名だけでは、患者が自分にとって必要な医療機関を選ぶことができないからです。つまり、医療機関側は、自院の専門とする分野、得意とする分野を正しく標榜することが大切ということになります。
診療科名と標榜科目の関係性を解説
標榜科目は、「内科」「外科」などの一般的な診療科名から選ばなくてはいけないわけではありません。また、外科として研鑽を積んできたから、「外科」を標榜しないといけないというわけでもありません。外科として医療機関に勤務してきた医師が、独立にあたって、外科以外の診療科を標榜してもいいということです。資格に関しても、基本的には問われません。
ただし、麻酔科に関しては、麻酔科標榜医の資格を取得しなければ標榜することができません 。
標榜科目の決め方についての基本ルール
標榜科目を決めるにあたっては、基本的なルールを踏まえておくことが必要です。標榜科目に関するルールは、2008(平成20)年に厚生労働省によって見直されています。
具体的には、以下の4つのパターンのいずれかであれば認められるとしています。また、4つのうちいくつかのパターンを併用することも可能です 。
(イ)内科
(ロ)外科
(ハ)内科または外科と以下の各事項を組み合わせたもの
a. 部位、器官、臓器、組織またはこれらの果たす機能
b. 疾病、病態の名称
c. 患者の特性(性別、年齢など)
d. 医学的処置
(ニ)単独の名称をもって診療科名とするもの。a~dの各事項との組み合わせも可能
ただし、標榜科目に関するルールが見直された2008年以前に掲げられている診療科名に関しては、4パターンのいずれかに当てはまらない場合も、そのまま標榜し続けることが認められています。そのため、街中やネット上に、この4パターンに当てはまらない医療機関を見つけたとしても、一概に「ルールを守っていない」と言い切れないので注意が必要です。なお、2008年以前に診療科目を標榜している医療機関が新しく看板を設置する場合などは、標榜科目の変更手続きをおこなったうえで、新しいルールに則った診療科名を標榜しなくてはなりません。なお、標榜科目の変更手続きについては後述します。
(ハ)のa~dの詳細は以下の通りです。
a) 部位、器官、臓器、組織またはこれらの果たす機能
頭頸部、頭部、頸部、胸部、腹部、呼吸器、気管食道、気管、気管支、肺、消化器、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、循環器、肛門、血管、心臓血管、心臓、腎臓、脳神経、脳、神経、血液、乳腺、内分泌、代謝、脂質代謝、肝臓、胆のう、膵臓
b) 疾病、病態の名称
感染症、性感染症、腫瘍、がん、糖尿病、アレルギー疾患
c) 患者の特性
男性、女性、小児、周産期、新生児、児童、思春期、老人、老年、高齢者
d) 医学的処置
整形(内科との組合せは不可)、形成(内科との組合せは不可)、美容、心療(外科との組合せは不可)、薬物療法、移植、光学医療、生殖医療、不妊治療、疼痛緩和、緩和ケア、ペインクリニック、漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡
なお、a~dのうち異なる分類に属する事項であれば、2つ以上の事項を組み合わせても構わないとされています。たとえば、cの「小児」、dの「心療」を使って、「小児心療内科」を掲げることが可能です。
a~dのうち同じ分類に属する事項を2つ以上使いたい場合は、2つの事項の間に「・」を入れるなどして言葉を区切れば問題ないとされています。たとえば、aの「大腸」「肛門」をつなげて「大腸肛門外科」はNGですが、「大腸・肛門外科」であればOKということになります。
(ニ)は具体的には以下の通りです。
精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科
“不合理な組み合わせ”は標榜不可
(イ)~(ニ)に当てはまったとしても、医学的知見および社会通念に照らし合わせて不合理である組み合わせは、標榜できないとされています。具体的には、以下の組み合わせは標榜不可とされています。
| 診療科名 | 不合理な組み合わせとなる事項 |
| 内科 | 整形または形成 |
| 外科 | 心療 |
| アレルギー科 | アレルギー疾患 (「アレルギー疾患アレルギー科」) |
| 小児科 | 小児、老人、老年または高齢者 (例:「高齢者小児科」など) |
| 皮膚科 | 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳 (例:「呼吸器皮膚科」など) |
| 泌尿器科 | 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳 (例:「頭頸部泌尿器科」など) |
| 産婦人科 | 男性、小児または児童 (例:「男性産婦人科」など) |
| 眼科 | 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓 (例:「腹部眼科」など) |
| 耳鼻いんこう科 | 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓 (例:「消化器耳鼻いんこう科」など) |
診療科目は複数標榜できる
また、厚生労働省は「広告可能な診療科名の改正について」と題した通知において次のように記していることから、診療科目は複数標榜できることがわかります。
「医療機関においては、当該医療機関に勤務する医師又は歯科医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して
表記することが望ましいものとする」
標榜科目の変更手続きについて
前述のとおり、2008年の標榜科目に関するルール見直し以前に診療科目を標榜している場合も、新しく看板を設置する場合などは、標榜科目の変更手続きをおこなったうえで、新しいルールに則った診療科名を標榜する必要があります。
診療科名を変更するためには、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長)に対して届出が必要です。具体的な届出の方法は届出先によって異なるため、各都道府県などの担当部局に確認する必要があります。具体的には、「診療科名 変更 (エリア名)」などで検索するとヒットします。たとえば、東京都中央区の場合、下記ページの「診療所・歯科診療所の変更」について記した箇所から、「診療所、歯科診療所又は助産所開設許可事項一部変更許可申請書」のPDFをダウンロードすることができます。
参照:中央区「診療所・歯科診療所の開設・変更・廃止等(法人(医療法人など)開設)」
標榜科目を決める際は集患も意識しよう!
標榜科目を決めるにあたっては、「ルールを守ること」「自院の得意とする診療、自院の専門とする診療についてわかりやすく伝えること」が大切なのは前述の通りですが、それに加えて、「いかに集患につなげるか」を意識することもとても大切です。もちろん、「自院の得意とする診療、自院の専門とする診療についてわかりやすく伝えることが、=集患対策」であるともいえますが、いくつかの候補のうちからひとつに絞る際などには、「どの標榜科目だとより多くの患者に来院してもらえるか」を基準に判断してもいいかもしれませんね。
特徴
対応業務
その他特徴
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。