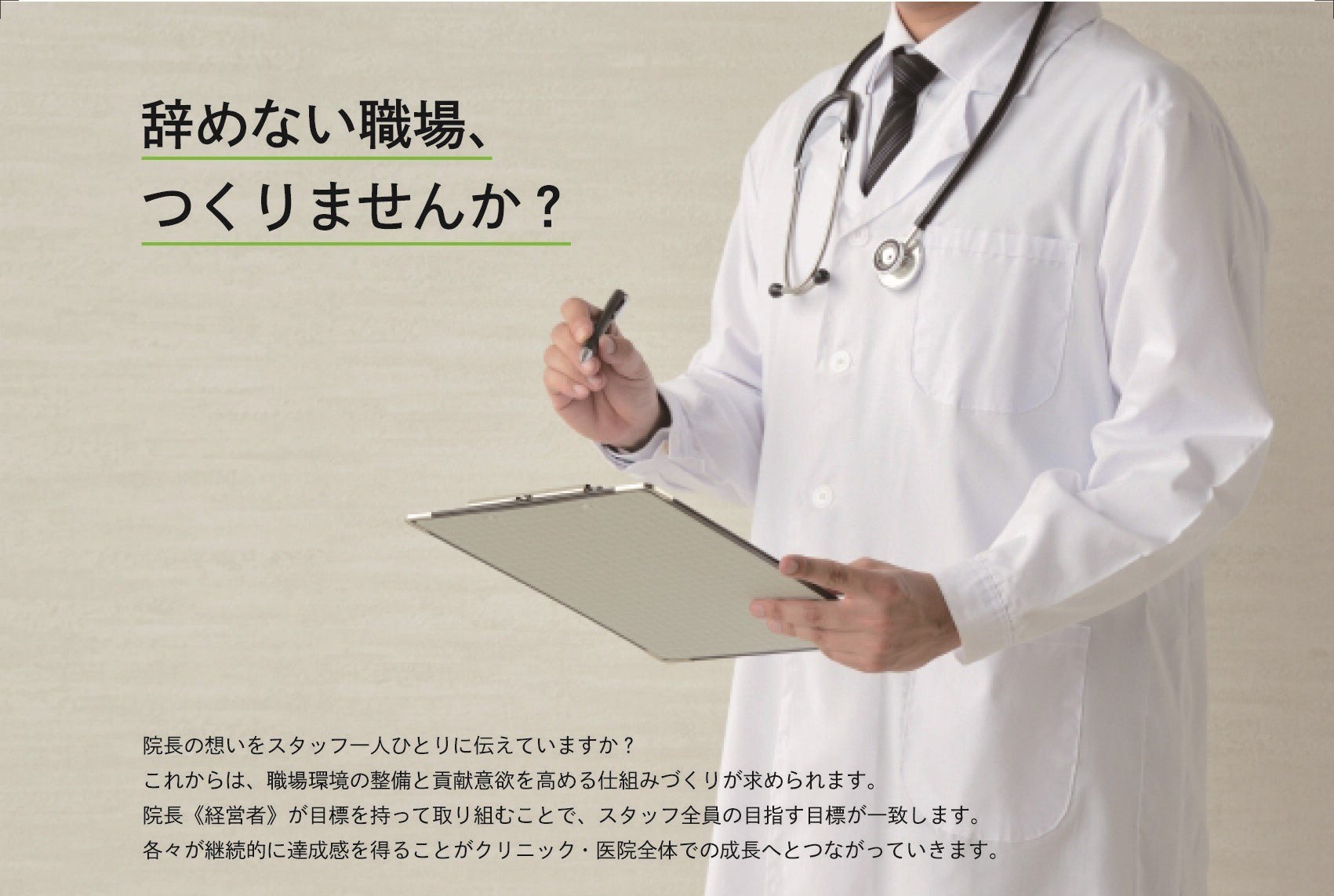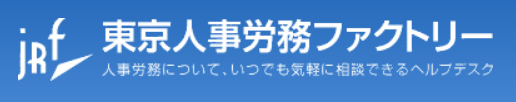クリニックの経営において、重要でありながら見落とされがちな課題に「人材育成」があります。この記事では、経営者からは見えにくい人材育成の落とし穴と、その解決策についてご紹介します。
いざという時に頼りになる相談先もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
人材育成が診療に影響する?!
良い診療を行うには診療の質を高めることはもちろん、人材育成もが大きく影響してきいます。
ところが、クリニックの人材育成に関しては、次の3つの視点が抜け落ちてしまっているケースがよく見られるのです。
- 「条件がよければ良い人材が集まる」は間違い
- 「人材育成」は、クリニックの経営でも最重要ポイントである
- 人材育成を阻む存在について
今回はこの3つの視点について、医療事務を18年務めた筆者の経験談も交えながら解説していきます。
クリニックで陥りがちな人材育成の問題点
クリニックの人材を募集する際によくあるのが「条件がよければ良い人材が集まる」という考え方。
これは18年間医療機関に従事していた筆者の経験からしても、あるあるといえるほど間違っています。
その理由は、優秀な人材は今働いている職場で重宝されており、なくてはならない存在となっているからです。つまり、「優秀な人材」は、現状に満足しているケースが多く、そもそもより待遇の良い職場や新しい環境を求めていないことも多いということ。
その中で、どれだけ良い人材で体制を整備しようとしても、結局は他のところで結果を残せなかった人だけが集まってしまう可能性も高いのです。そのため、外から優秀な人材を集めるよりも、、今働いているスタッフを優秀な人材に育成する視点が大切です。
人材育成はクリニックの経営に直結する課題
人件費は固定費として重要なコストマネジメントが求められます。
経営の根幹である売り上げを生み出すのは診療であり、それができるのは医師である院長自身です。
しかし、その診療時間を最大化するためには、診療の流れを把握して適切なサポートができる人材が必要不可欠です。
さらに、行われた診療を適切に診療報酬として請求できるように整えるのも人です。いずれも医療事務が関わりますが、参入障壁の低い医療事務だから変えが効くと思っていると、バランスが崩れてしまい、診療に時間がかかったりミスが起きたりと患者さんに負担を強いるリスクもあります。
このように人材育成はクリニック経営の根幹となる診療に直結する課題だと認識し、備える必要があります。
人材育成を阻む意外な原因
クリニック経営に直結する人材育成を拒む意外な原因の中でも、をご存知でしょうか?
それは給料やシステムよりも大きなものが「人」です。人を育てるのも人ですが、人の育成を阻むのも人です。
多くの場合、新しく医療事務のスタッフを採用した場合、その教育担当になるのは仕事を知っている先輩が行うと思います。
経営者としては、「人が増えて、より効率的にクリニックを運営できる」と期待が膨らむところですが、実際には、先輩スタッフによる教育のパワハラやモラハラが起き、新人スタッフが辞めてしまうケースも少なくありません。
こういったケースでとくに難しいのは、先輩スタッフ本人にパワハラやモラハラを行っている自覚がなく、自然な振る舞いが新人スタッフにとっては辛い場合もあります。
新人教育を担当者1人に任せてしまうのではなく、経営者である院長も適宜気に掛けるといった配慮が必要です。しかし現実的に難しい場合もあろうかと思います。
そこで問題が起きた場合に、すぐに院長へ相談ができるルートを予めスタッフに周知し、スタッフから気兼ねなく声をかけてもらう仕組みを作っておくと、そこまで負担を増やさずに運用が可能となるでしょう。
人材育成で押さえておくべきコツ

これまでお伝えしてきた人材育成の問題点を解決するために、押さえておくべき3つのコツをご紹介します。
問題点の解決と聞くと、「難しそう」「面倒」「コストがかかる」といったイメージをもたれるかもしれませんが、これからお伝えする内容はちょっとした意識と行動で可能になるものばかりです。
とはいえ、どれか1つだけやれば確実に効果が出る訳ではありませんので、1つひとつ実践し、自院にとっての最適解を見つけてください。
コミュニケーションのコツ
ここでいう「コミュニケーション」とは、普段の診療上のやりとりではなく、1対1の話し合いの場をイメージしていただくと良いです。
1対1が重要な理由として、周りの目を避け本人の率直な気持ちを確認できるメリットがあります。実際に1対1で話をすると、ミーティングでは出てこなかったような不安や疑問が飛び出すのは珍しくありません。
働く上での不安解消は気持ちを整える上で重要ですし、その後のキャリアプランをポジティブにする役割も持っています。
日々の忙しい診療の中で大変だとは思いますが、組織の基盤づくりとしてスタッフ一人ひとりへの配慮とコミュニケーションはクリニック経営において外せない要素の1つです。そのためにも、日々の診療の中で信頼関係を構築しておくことが重要になります。
教育の仕組みのコツ
施設ごとの違いはあれど、スキルマップやキャリアプランニングなど、教育体制・評価制度が充実している職場ほど人材育成のスピードが早い傾向があります。
人材育成のスピードが早ければその分、効率的な診療の運用が可能になり、結果的にスタッフの満足度が上がります。スタッフの満足度が上がれば比例して患者満足度も上がり、クリニック自体の評価も高まります。
教育の仕組みを作る具体的なコツとしては、ツールを使ったヒアリングと適正な評価が挙げられます。
例えば、課題目標達成度として目標を予め設定し、半年・1年と定期的に目標を振り返り、スタッフと一緒に達成度合いを確認する方法があります。
教育は人と人との間で行われるため、定性的な評価になりがちです。そのため、誰もが同じ認識で取り組めるツールの導入は、評価する側・される側の時間をムダにせず、有効活用できます。
労務管理のコツ
かねてよりクリニックをはじめ、医療機関では労務管理のずさんな点が取り沙汰され、時にはニュースにもなりました。
その背景にあるのは、診療や看護のプロはいるものの、労務に関するプロがいない点が挙げられます。
総合病院や大学病院など規模の大きな施設であれば、総務担当の部署がありスタッフの労務管理を行ってくれることも多いですが、クリニックで同じような体制を組むのは現実的ではありません。
「労務管理をどのように行えば良いのか?」という疑問に関する答えとしては、経営者である院長が基礎知識を理解し、必要な場合に助けを求められる相談先の確保が必要だといえます。
私が勤務していた施設の院長は、各施設の院長が一同に介する情報交換の場に出向き、そこで仕入れた情報を自院の状況に照らし合わせて指示出しをするような取り組みをしていました。
人材育成の課題に対応するには
人材育成はクリニックの経営において重要なポイントでありながら、問題があったとしても表面に出てきにくい側面があります。
そして、表面化された時には経営を揺るがすほどの大きな問題に膨れ上がっている場合もあるのです。
そのような問題を解決するには、コミュニケーションや教育など、内政的に対処できるパターンもありますが、必ずしもうまくいくとは限りません。
限られたリソースの中で課題を解決するには、専門企業への相談も有効な方法です。問題が顕在化する前の早めの相談が、クリニックを上向きにさせるきっかけにもなります。ぜひ現状を整理し、対応方法についてご相談ください。
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、2022年9月時点の情報を元に作成しています。

執筆 医療ライター 武田 直也
フリーランスWebライター。18年間医療事務として合計3つの医療機関に従事。診療報酬をはじめ、診療情報管理士の資格を活かし、カルテ監査やDPCデータ、クリニカルパスなど医療情報の活用に精通している。
他の関連記事はこちら