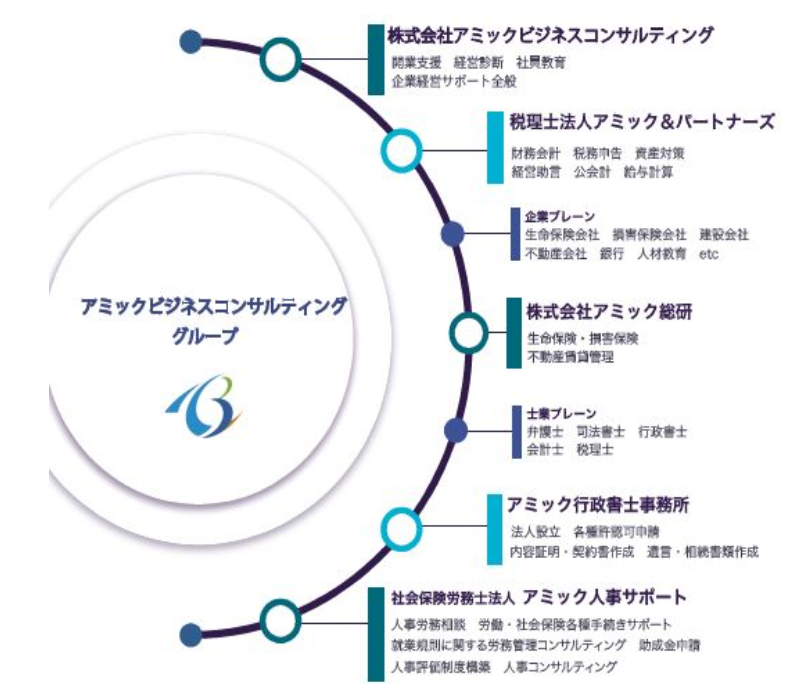「2022年度の診療報酬改定でどんな影響があるのかな?」「必ず対応しないといけない内容なのかな?」「算定漏れになるような事態は避けたい」と多くのクリニック経営者が腕組みをしていることでしょう。
改定内容は重要だと分かってはいるものの、直感的には内容が掴みにくい部分があります。
そこでこの記事では、2022年10月の診療報酬改定でクリニックが今後対応すべきICTについて解説します。
2023年4月より義務付けられる内容のため、具体的な準備事項をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
今回の診療報酬改定での変更点
2022年10月の改定では、オンラインによる資格確認が明確に推進される形となりました。具体的には、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されました。
この加算は従来の「電子的保健医療情報活用加算」の後継という位置付けで、オンライン資格確認システムの導入を義務化という形で推し進めるものです。
具体的な点数設計は以下の通りです。
- 施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合:4点
- 1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合:2点
算定に必要な施設基準として、カードリーダーなどのオンライン資格確認に必要な設備の導入や、院内掲示・患者説明などがあり、2023年4月までに準備が必要です。
(参照:厚生労働省「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関向けポータルサイトより)
2023年4月までに導入すべきオンライン資格確認の全貌
それでは、2023年に導入が義務化されるオンライン資格確認の内容について、詳しく見ていきます。
まず施設基準が見直され、マイナンバーカードによる情報の取得が必須となりました。2022年8月23日に総務大臣が発表した資料によると、マイナンバーカードの交付率は全人口の50.1%となっており、医療と紐付けることで交付の促進を図る狙いもあるものと推測します。
マイナンバーカードを使ったオンライン資格確認は、患者の医療情報を用いた医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の基盤とすることが、基本的な考え方として打ち出されています。
そのため、オンライン資格確認をきっかけとして、今後さらなるオンラインの活用に向けた準備は加速する方向となるのは想像に難くありません。
オンライン資格確認導入に向けた準備事項
ここからは、2023年4月のオンライン資格確認に向けて、どのような準備が必要なのか具体的にご紹介します。
主に内部の準備であるマイナンバー対応機器への対応と、患者さんに向けた院内掲示準備の2つが挙げられます。どちらも導入に向けた準備期間と導入後の対応に苦慮する可能性が高い内容です。
1日2日で対応できる訳ではないからこそ、余裕を持ったスケジューリングが必要となるため、詳しく中身を見ていきます。
マイナンバーカード対応機器の導入
設備面の準備としてメインになるのが、マイナンバーカード対応機器の導入です。具体的には、顔認証付きカードリーダーが必要となります。
そこで、カードリーダー導入に必要な費用について補助金の申請が可能です。クリニックの場合、1台無償提供が可能となっているほか、2022年12月31日まで申請すると上限額が42.9万円に増額しています。(詳細は下図参照)
そのため、これから設備面を整える場合には、積極的に利用すべきです。
院内掲示
次に患者さんに向けた院内掲示が必要です。対応方法自体はこれまでの掲示と大きく変わらず、目に見える形で対応すれば問題ありません。
院内掲示に載せる内容としては、初診患者さんが対象となります。そのため、これまでの投薬歴や健康診断結果のほか、診療に必要な情報を資格確認と合わせて収集すると分かるようになっていれば施設基準はクリアできるでしょう。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算への準備事項
ここからは、実際に初診料の加算として算定できる「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」の準備事項をご紹介します。
この加算は、従来の「電子的保険医療情報活用加算」に変わって設定された新しい加算です。これまでは、初診・再診ともに算定ができていましたが、初診のみに変更されました。また、初診の点数も7点から4点と下がっており、「特別なもの」から「一般的なもの」への移行とも取れる点数設計になっています。
そんな「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定するために3つのポイントを解説します。
システム更新
まずはオンラインによる資格確認を可能とするために、院内のシステムを更新する必要があります。
ここで最も注意しなければいけないのは、ベンダーの確保です。なぜなら、加算に向けた準備期間が迫ると、ベンダーの取り合いが始まるからです。すでに始まってきている、という話も耳にしています。
この加算はクリニックだけではなく病院も含まれます。すると、対応が必要な母数が増えるため、必然的にベンダーを求める声も増え、希望通りのスケジュールで対応してもらえない可能性が出てきます。
そのような事態を避ける方法が、先にベンダーの担当者から対応マニュアルを入手しておく方法です。この方法のメリットは自分たちの手で対応できる可能性があるほか、対応マニュアルという共通言語を通じて、担当者との関係構築を深めることが可能な点です。
担当者も人のため、コミュニケーションが取れていれば優先して対応してもらえる場合もあります。
いづれにしても早めの行動が吉のため、事務スタッフとのすり合わせでスムーズな対応を心がけるとよいでしょう。
すでに対応に動いている医療機関も多くなっているため、依頼可能なメーカーを下記にてご紹介します。
初診時問診票の更新
施設基準の1つである患者さんからの情報収集のため、初診時問診票に標準項目を設けた形に更新する必要があります。ここでいう標準項目とは、厚生労働省が定める問診票で入れるべき質問内容を指します。
具体的には「処方されている薬」「特定健診の受診歴」などです。
すでに質問項目として設けているクリニックも多数あるため、あまり大きな影響はないかもしれません。
しかし、今回の診療報酬改定はICTを活用した医療のDXの基礎作りです。そのため、今後さらなる追加要望がくることは十分予想されます。
継続対応が必要なものとして扱っておくと、後々の管理も容易になります。
患者への説明方法の周知
院内の準備が整ったあとは、患者さんへどのように説明するのかをスタッフに周知する必要があります。
よくあるのが、周知が十分でないためにスタッフによって説明内容が異なり、患者さんが混乱し、クレームに繋がるケースです。
クレームは患者さんからの信用がなくなるほか、スタッフの士気も下がり、メリットはどこにもありません。避けるためには、資料の回覧で済ませるだけで終わらせず、理解度チェックのための簡単なテストを作成し、点数が低いスタッフには個別対応をとる方法もあります。
余裕があれば、運用スタート前後に予習・復習しておくのがベストですが、マンパワーがもったいない場合には、e-Learningの活用も有効です。
まとめ
2022年度10月の診療報酬改定では、ICTの活用・促進が1つの大きなテーマとなっています。これまで努力義務だった部分が、原則義務化されるなど、今後より一層の推進が図られることになるでしょう。
今回のオンライン資格確認導入は、そんなICT活用の1歩とも言える内容です。だからこそ乗り遅れることなく、十分な対応をとっておく必要があります。
改定対応は院長をはじめ、スタッフの方々の意識合わせが重要です。ポイントをおさえた改善へのアクションには思っていたよりもマンパワーが取られることもあります。
そのような場合には、外部に助けを求めるのも1つの手です。まずは資料請求から始めてみてはいかがでしょうか。
特徴
対応業務
その他の業務
診療科目
特徴
その他の業務
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 医療ライター 武田 直也
フリーランスWebライター。18年間医療事務として合計3つの医療機関に従事。診療報酬をはじめ、診療情報管理士の資格を活かし、カルテ監査やDPCデータ、クリニカルパスなど医療情報の活用に精通している。
他の関連記事はこちら