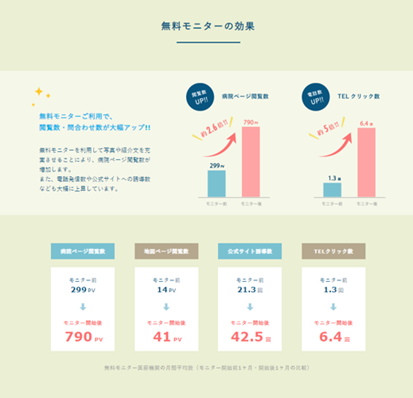職員に対する患者さんのクレームが続いていたり、Googleなどに辛らつなコメントがあったりして困っている院長は少なくないようです。
クリニックの経営者としては、同じ院内の人間関係や、それらがもととなったクレーム等は避けたいことでしょう。
そのような事態にならないようにするためにも、スタッフの患者さんに対する接遇への対処・改善は常に意識したいところです。
本記事ではクリニックの評判を向上させるためにも重要になってくるポイントとして、職員に接遇研修を行うメリットと、その具体的な実施方法について紹介します。
クリニックの経営に接遇研修が必要な理由は?
接遇研修だけで本当にクリニックの経営がよくなるのか?このように疑問に思う経営者は多いと思います。ただ結論として、職員の接遇研修はクリニックの安定した経営に大きく関わります。
ここではその具体的な理由について紹介します。
ネガティブな口コミを防げる
クリニックの収益を上げるには、基本的に「患者数を増やすこと」「患者一人あたりの診療報酬を上げること」が重要ですが、その妨げとなってしまうのが「ネガティブな口コミ」です。ネガティブな口コミが増えてしまうと、その口コミを見た他の人も、クリニックに対して良くない印象を持ち、結果的に集患できなくなっていくでしょう。
最悪の場合、しっかりとした診療や接遇をしていたとしても、満足してもらえない可能性もあります。特によくある「ネガティブな口コミ」につながりやすい事例としては、以下のようなものがあります。
- 職員の身だしなみ(服装、髪型、匂いなど)が乱れている
- 院長含むスタッフの接し方が不適切(あまり話を聞いてくれない、言葉遣いが悪い など)
- 待ち時間が長くなってしまっている
- 検査や処置の順番の入れ替えが頻繁にある
筆者の経験からも、受付の態度が悪くて、ネガティブな口コミを書き込まれたクリニックはたくさん見てきました。ネガティブな口コミの中には「職員同士が受付で少し雑談をしているところを見た」だけの事例もあります。
口コミだけでもネガティブなイメージがついてしまいますが、院内でのクレーム対応にまで発展してしまうと、20、30分と診療が滞ってしまうケースも考えられます。他の患者の待ち時間が増え、悪い口コミにつながる悪循環が生まれてしまうでしょう。
自由診療への理解が得られやすくなる
クリニックの安定した運営・経営を行っていくためにも、自由診療での収益アップは視野に入れておきたいと考える医師は多いでしょう。
しかし、患者にとって自由診療は「治療費が高い」「治療効果が曖昧」などのイメージが先行しているのも事実。患者からすると、クリニックの利益を優先してすすめてくるのかな?と感じることもあるようです。
実際に、医療接遇に適した言葉遣いが苦手だと案じている医療事務や看護師も多いようで、もし間違った言葉遣いをしてしまえば、患者クレームのトラブルにつながってしまう可能性があります。そのような状況では自由診療への理解は到底されないでしょう。
接遇研修では、患者への言葉遣いについても教えてくれるため、医療に適した丁寧な応対をすることで、トラブルを避けるだけでなく、患者との信頼関係を築くことでき、自由診療への理解や受け入れにもつながるでしょう。
たとえば眼科では、白内障手術で使用する眼内レンズの種類によって、自由診療の選択肢がでてきます。自由診療で行う白内障手術は、保険診療で行う白内障手術の費用負担と比較し、約10倍近くにもなります。当然、患者も費用分の効果や快適性を期待します。
日頃から患者への丁寧な応対で信頼関係ができていれば、自由診療の受け入れも容易で無駄なトラブルも発生しにくくなります。
医療事故を未然に防げる
接遇研修と聞くと「患者対職員の応対スキルの研修」をイメージして、医療事故とは関係ないように思うかもしれません。
しかし医療接遇の研修には、患者対職員だけではなく、医師対職員のかかわり方、コミュニケーションのとり方、心構えが研修内容に含まれることが多いです。
実際に、医師から職員へ伝えた ”つもり” が原因で発生した医療事故を題材にケーススタディをする研修を取り入れている専門業者もあります。
医療事故は発生してからでは取り返しがつきませんので、接遇研修を実施することで未然に防ぐことができるのならば、そのメリットも大きいのではないでしょうか。
職員のモチベーションアップにつながる
接遇研修を実施するとなると、職員からは「そんなことをしなくても」「時間が取られるのはイヤ」と心配になるかもしれません。
しかし接遇研修を行った結果として、職員のモチベーションがアップすることも少なくないようです。
接遇研修では、職員が能動的に患者へとかかわり、丁寧に応対するスキルを身につけられます。高いレベルの接遇が実践できれば、日々の仕事の中でも、患者から感謝の気持ちや言葉を受け取る場面も増えてきます。その気持ちが職員のモチベーションへとつながるのです。
来院患者が多く、とても人気のあるクリニックの経営者からは、医療接遇には強くこだわっていることをよく聞きます。ホテルのような接遇を目指しているようで、職員も前向きにイキイキと働いている様子でした。
職員のモチベーションが上がれば、より良いサービスを提供したいと自発的にも取り組んでくれるので、クリニックの患者満足に貢献することが期待できるのでしょう。
クリニックで接遇研修を実施する方法は?
次は、実際にどのように接遇研修を実施すればいいのか?について、具体的な方法をご紹介します。
クリニック主導で実施する
院長や事務長など、経営者が主導で実施する方法です。
経営者の中に医療接遇の知識やスキルに詳しい人がいれば実施は容易でしょう。
しかし、医療接遇の専門知識がなく、本格的な研修を実施するのが難しいクリニックも少なくないようです。
とはいえ、接遇の基本については、YouTubeなどでも情報を得られますので、経営者自ら学び講義をすることもできます。職員を集めたミーティングの中で供覧するのもいいでしょう。
接遇研修の専門業者に外注
手間をかけず、安心して任せたいと考える経営者にとって有力な選択肢となるのがこちらの方法です。
実際にクリニックの院長に話を伺ってみると、接遇研修の結果として、
- 手術や治療の急なキャンセルがほぼゼロになった
- 患者からのクレームがなくなって効率が上がった
- 診療患者数が20%増えた
などの声が上がっていました。
研修形式には、1日限りの完全講義型から、クリニックの課題に合わせた講義にロールプレイングまでと、さまざまな形式でサービス提供がされています。以下では、それぞれのタイプで代表的なサービスをご紹介していきます。
1日研修
1日だけの参加で、医療現場における接遇の基本的な心構えや知識、スキルを学べる研修があります。
1日研修の形式は、外部のセミナー会場での受講や、クリニックに講師を招いて受講する方法などさまざまです。たとえば、ANAビジネスソリューション株式会社では、「ベーシックマナーコース」として、キャビンアテンダントにも行われている研修と同等のレベルの研修を医療現場に即した形に変えたものを実施しています。
このような外部研修を最大限有効に活用する方法は、主任の職員に代表で参加をしてもらい、研修内容をクリニックで再び講義させることが有効です。
外部研修の参加では、研修日その場だけでの学習になってしまいがち。クリニック内で継続して意識していくためには、研修以外での工夫も必要でしょう。
また1日研修のメリットは比較的手頃な費用から始められることでもあります。
- いきなり接遇研修に大きなコストをかけるのではなく、まずは小さいところからでも始めてみたい
- 職員の中にリーダーシップのある人材がいる
このようなクリニックにとってはおすすめの方法です。
ロールプレイング形式
画一的な研修内容ではなく、クリニックの課題に合わせて講義にロールプレイングを行い、徹底的に接遇改善に取り組みたい。そう考えるクリニックにおすすめなのが、コンサルティング形式の接遇研修です。
たとえば、ラ・ポール株式会社は日本全国の医療機関、200件以上のコンサルティング研修の実績を有しており、成果に直結するコンサルティングを看板サービスとし、フォローアップまでしてくれることが魅力です。コンサルティングを受けたクリニックでは、患者数が対前年で200%にまで増加した脅威の実績もあります。経験豊富な実績から安心して依頼できる企業の一つと言えるでしょう。
コンサルティングから実践形式のロールプレイング研修は、時間をかけてアフターフォローまでしてくれるので、1日研修と比べて必要なコストは大きくなることが多いです。新規開業のクリニックでは、接遇以外にも準備することが多いため、時間とコストをかけてまで実施することは難しいでしょう。
開業して少し落ち着た状態のクリニックが、今よりもう一段階、患者を増やしてクリニックを大きくしたいと考えるなら取り入れてみることがおすすめです。
普段から付き合いのある業者に相談
医薬品代理店、製薬会社のMRや医療機器メーカーなど、普段から付き合いのある業者に相談してみることも選択肢のひとつです。
いずれの会社にも共通していることは、たくさんの医療機関を訪問しているため、クリニックの良し悪しを見る目が肥えていること。受診患者が多いクリニックの共通点、院内でこだわって取り組んでいることなど、情報を豊富に持っているので、そこからなにかヒントをもらえるかもしれません。
また各社には開業や経営コンサルティングを専門に行う組織を持つ場合もあります。例えば、医薬品代理店のSUZUKENでは開業支援サービスを行う組織もあります。開業地区の選定から開設に必要な届出。職員の募集、教育とクリニックの開業に関わるノウハウを持って総合的な支援をしてくれます。
製薬会社の中には積極的に診療サポートに関わる会社もあります。神経疾患、がん領域の治療薬を専門にするエーザイ株式会社では、サービスの一つとして接遇研修の動画配信を行っています。
まとめ
昔のように、なにも対策を取らなくても患者は受診してくれる。医院の経営に特に心労をかけることはない。このような時代ではなくなったと感じるクリニックの院長・経営者は多いことかと思います。
今も昔も変わらないのは、患者の口コミが集患に大きく影響すること。その口コミを左右するのは、診療内容だけでなく、医院の雰囲気や職員の接遇にかかってきます。
口コミについては、記事下にも推奨のサービスをご案内しています。将来の安定的な医院経営のためにも、本記事を参考に、接遇研修の実施のきっかけになれば幸いです。
特徴
その他特徴
対応業務
診療科目
特徴
その他特徴
対応業務
診療科目
この記事は、2023年2月時点の情報を元に作成しています。

執筆 医療ライター ミナト
製薬会社MRとして営業職を経験。その後は営業組織の管理職となり、マネジメントやマーケティングを行う。
数多くクリニックの開業サポートをしてきた経験から、経営に役立つ情報をたくさんの人に広めたいとの想いを持つ。「医療×経営」の記事を中心に執筆活動中。
他の関連記事はこちら