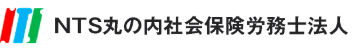クリニック運営に限りませんが、安定的な企業としての運営を行うためには規律(ルール)が必要になってきます。ルールが組織化を促し、トラブルを防止や生産性を向上させ、企業としての信頼とレベルを上げるものとなります。それら企業のルールをまとめたルールブックとしての存在が、就業規則です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を雇用する企業は必ず作成・提出の義務が課されています。逆に言えば、10未満の労働者しか雇用していない企業には、作成の義務はありません。クリニック開業時、労働者が10人未満で事業を開始しようと思われている方もおられるでしょうが、筆者の考えでは義務でなくても、企業に規律を作るために就業規則を作成する必要があります。
今回は就業規則の作り方について社労士の先生に執筆いただきましたので一緒に見ていきましょう。
どうして就業規則を作成したほうが良いの?
例えば、従業員が何か職務において違反をしたとします。それについて、懲戒処分をしたいと思ったときに、就業規則に懲戒処分の項目が記載されてなければ行うことができません。
もちろん減給等の処分も、就業規則がなければ無効とされる可能性があります。
その他、就業規則の記載があれば取り入れられたはずの制度が、就業規則がないためにその制度が使えず、結果としてクリニック経営にとって損になることもあるので、義務でなくても作成するほうが良いと考えます。
就業規則を作成する際のポイント
就業規則にも、労働条件明示の際に合ったような必要的記載事項(絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項)と任意的記載事項があります。
必要的記載事項
※④〜⑩に関しては任意項目なのですが、是非作成していただきたい項目を後述いたします。
上記が必要的記載事項であり①〜③が絶対的必要記載事項、④〜⑩が相対的必要記載事項となっています。
絶対的記載事項作成時に気を付けるポイント
①始業及び就業事などの事項
診療開始9時の場合、その前の時間で準備などを命じた場合は、原則的に労働時間になり残業代が発生します。また、開始前に10分程度の朝礼を行うところもありますが、その場合も厳密には労働時間となり、またそのことに不満を持つ従業員も少なくありません。もし、それらの業務に出た場合の勤務時間はどうなるのか?賃金はどうなるのか?などの項目も明記しておきましょう。
クリニックでの勤務時間については1か月変形性労働時間制という柔軟な勤務形態を使用しているところも多いです。しかし、通常の勤務形態より複雑な制度運用となってしまうことになりますので、その際は専門家の意見を聞きながら、最適な労働時間の制度を検討することをお勧めします。
【ポイント】変形性労働時間制を使う場合は、複雑な運用を行う必要があります。
②賃金の支払日
賃金について、開業後よくあるケースは賃金締日と支払日が近すぎるという事があります。規則を作成する際に、少しでも早く給与を渡してあげたいという思いがあるかもしれませんが、締日と支払日の間隔は少し空けてください。
通常、締日から従業員の勤怠を集計して給与計算を行うのですが、締切日から支払日までの日にちが少なければ、勤怠を集計する時間が少なくなります。また、実際には従業員の勤怠が間違っていたり、人数が多くなってくると勤怠集計が大変になります。余裕を持つためにも締日と支払日には10日以上日にちを空けることをお勧めします。医療機関の収入源である、診療報酬の支払いが毎月21日前後なので、給与を25日支払いにするところも多いようです。
また、給与計算をアウトソーシングする際にも、締日・支払日が近いと追加料金を取られる場合もあります。
【ポイント】給与計算は毎月発生する業務。作業時間にはゆとりを持ちましょう。
②−2残業代の決め方
賃金を決定するこの項目はとても重要です。時々耳にする、他のクリニックの就業規則をそのまま事業所名だけ変更して使用するといったことがあります。これは大変危険なことなのでやめておきましょう。筆者が経験したことですが、残業代の計算を決める部分で、通常は法定労働時間(原則1日8時間週40時間)を超える場合に、その超えた時間の給与に1.25倍以上支払うというのが労働基準法で定められています。
しかし他のクリニックから貰った就業規則では所定労働時間を超える場合に1.25倍支払うと記載されていました。これは、1日7時間勤務と定められた(所定労働時間7時間)人が1時間分残業した場合、通常の法律では残業した1時間に1.00倍した給与で良いのですが、その就業規則を使うと残業1時間分に1.25倍の給与を支払うということになります。つまり、法律以上の残業代を支払うことになってしまうのです。法定労働時間・所定労働時間という1文字の違いですが大きな違いが生じることも起きる項目ですので、慎重に作成しなければなりません。
【ポイント】他院の就業規則は、自院の実態に合わないこともある。
※②賃金の支払日②−2残業代の決め方は、どちらかまたは両方を採用していただければと思っています。
③退職に関する事項
退職の規程については、定年や再雇用、退職願の出す時期、退職時の引継ぎなどを記載します。その際に、トラブルとなりやすいのが退職願の出す時期と引継ぎについてです。
よく見られる退職願を出す時期は退職の1-2か月前としている就業規則が多い傾向が見られます。ただ、無期雇用契約の場合は退職の時期を定めても、民法の決まりである契約解除申し込み後2週間経過すれば、労働契約は解除されるという法律が優先されます。もし従業員の有給休暇が余っていて、それらすべて使うことをクリニック側は拒否することもできません。そうなれば、引継ぎをおこなうことは難しいでしょう。
最近では、弁護士などを利用した「退職代行」というものが広まってきており、いきなり弁護士等の代理人から連絡があって、「〇〇日で辞めるので、今日から退職日まで有給休暇を使わせてもらいます」といったような連絡が来ることも増えてきています。
退職に関することは、ある意味労働者の最大の武器であるので、これらを就業規則で完璧にフォローするのは難しいのですが、あえて言うなら、退職の規程にしたがってくれるような関係性を従業員と築くことが、退職時期や引継ぎをスムーズにするために重要なのだと思います。
【ポイント】退職に関しては完全にコントロールできない。
相対的記載事項についてクリニックで注意すべき項目
ここからの項目は任意事項なのですが、トラブルを避ける意味でも作成をおすすめする事項のみポイントを紹介します。
⑥表彰及び制裁に関する項目
従業員数が増えてきたり、長く経営していると、いわゆる「問題社員」と呼ばれるような従業員も雇い入れてしまうことがあります。
これは筆者の経験談なのですが、いわゆる問題社員と働いたことがあります。規則は守らない、任された仕事はしない、当日欠勤や無断欠勤をするようなこともありました。周りの従業員がその穴埋めのために疲弊してしまい、経営側に訴えましたが、就業規則に懲戒処分の項目がなく、軽い口頭注意程度しか行えませんでした。
それでも問題行動は大きくは改善されませんし、訴えた従業員からすると、何も制裁を課さない経営陣への不満も溜まっていき、最終的には退職していきました。
もし制裁で定められた項目を規則通りに運用し、なにかしらの懲戒処分などを行っていれば、問題行動が改善されなかったとしても、従業員も辞めなかったかもしれないと思ってしまいます。
表彰についても明確に規程して、規則通りに頑張っている従業員を表彰することで、職場の風紀と従業員の定着につながるのではないかと考えます。
【ポイント】懲戒は就業規則に根拠がある場合に実施できる。
クリニックに取り入れたい服務規程
就業規則には任意的記載事項というものがあり、法令、公序良俗、または労働協約に違反しない限り、いかなる事項についても自由に就業規則に定めることができるとされています。
この記載事項で就業規則に、経営理念や服務規律、副業の規程、整理整頓を行う、報告連絡相談を密にするなど細かなルールを記載し、職場に合ったルールとすることもできます。
特にクリニックで取り入れたい服務規律の項目として以下のようなものがあります。
職員の服務
これらは、医療者としての越権行為や、患者を不安がらせないための条文になります。筆者の経験上で、医者の指示を仰がず、独断で行為を行う人に遭遇したことがあり、また不用意に患者を不安がらせるようなことを言う人もいますので、このような服務規律を従業員内で浸透させておくことは重要だと考えます。
衛生管理
うがい、手洗い、消毒及び疾病のり患防止、並びに安全衛生に関する事項を守ること。また、自身の他、家族・同居人の健康状態に十分留意し、感染症流行時は、感染者が多い地域又は感染可能性が比較的高い地域・場所への渡航・旅行、不要不急の外出を避けるとともに、職員及び家族・同居人等の体調不良時には別途定める基準に従い法人に申告すること。
この条文は新型コロナウイルスやインフルエンザなどの対策の為の条文であり、感染症に特に注意しなければならない医療機関においては必要な項目だと考えます。
一例になりますが、上記のようなことも記載可能なので、クリニックの方針に合わせた服務規律を作成していきましょう。
必ず作りたい休職規程
休職とは、従業員の私傷病により仕事を休む事になった場合、労働義務を免除することです。最近では、精神的に不安定になって休職をする人が増えていますので、規程を作ることが重要でしょう。
休職に対する規程は、法律で定められているものではなく、企業ごとに規則を作成することができます。
休職中の給与は支払う必要はありません(ノーワークノーペイ)が、社会保険料の支払いは、従業員分の保険料をクリニック負担分と併せて支払う必要があり、休職中は支払うべき給与がないため、クリニックが一度すべて負担して支払います。休職規程に、建て替えた分の保険料の徴収方法など細かく記載することでトラブルを未然に防ぐことが可能です。
休職の期限も規程に記載することができます。休職の期限を定めて置き、その期限が過ぎても服務に従事することができない場合、自然退職となります。一般的に自然退職は会社都合退職ではなく、自己都合退職と解釈されることが通常です。
自然退職する前段階から、休職者の為に体調確認のための連絡や病院受診を勧めたりなど、休職中から求職者の体調をいたわることに最善を尽くすことがトラブル防止になります。
就業規則のあるあるポイント
就業規則には、実はもう一つ義務があります。【就業規則の周知義務】です。
簡単に説明すると、労働者が見たいときにいつでも見られる状態にしていなければならないということです。
「就業規則はあるけど見せていない」「従業員に見られると困る」という方も、しばしば見受けられます。
しかし、周知がしっかりされてないと懲戒や休職などの規程を定めていても、効力を発揮しないといった事になりかねません。
また作成した側が、就業規則の内容を理解していないことも多く、就業規則の記載内容に疑問を持った従業員からの質問に答えられないといった事もあり、就業規則の内容を理解しておく必要があります。
経営者側と労働者側とで周知・理解し、規則を運用していくことが、健全なクリニックの風紀・規律が育ち、運営していくことが可能となると考えます。
いかがだったでしょうか?外部の社労士の先生に依頼、またはご自身で就業規則を作る前に、ポイントを押さえておくだけでも進捗が違うと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 HR-Style社会保険労務士事務所 | 藤井 健文
HR-Style社会保険労務士事務所代表/社会保険労務士/理学療法士
代表が理学療法士という医療系国家資格を持つ、全国でも数少ない社会保険労務士。
医療介護現場で技師長を含める経験は10年を超えており、その経験を活かし独自の医療・介護現場サポートも行っている。医療介護福祉業界の関与先が多数を占める。
他の関連記事はこちら