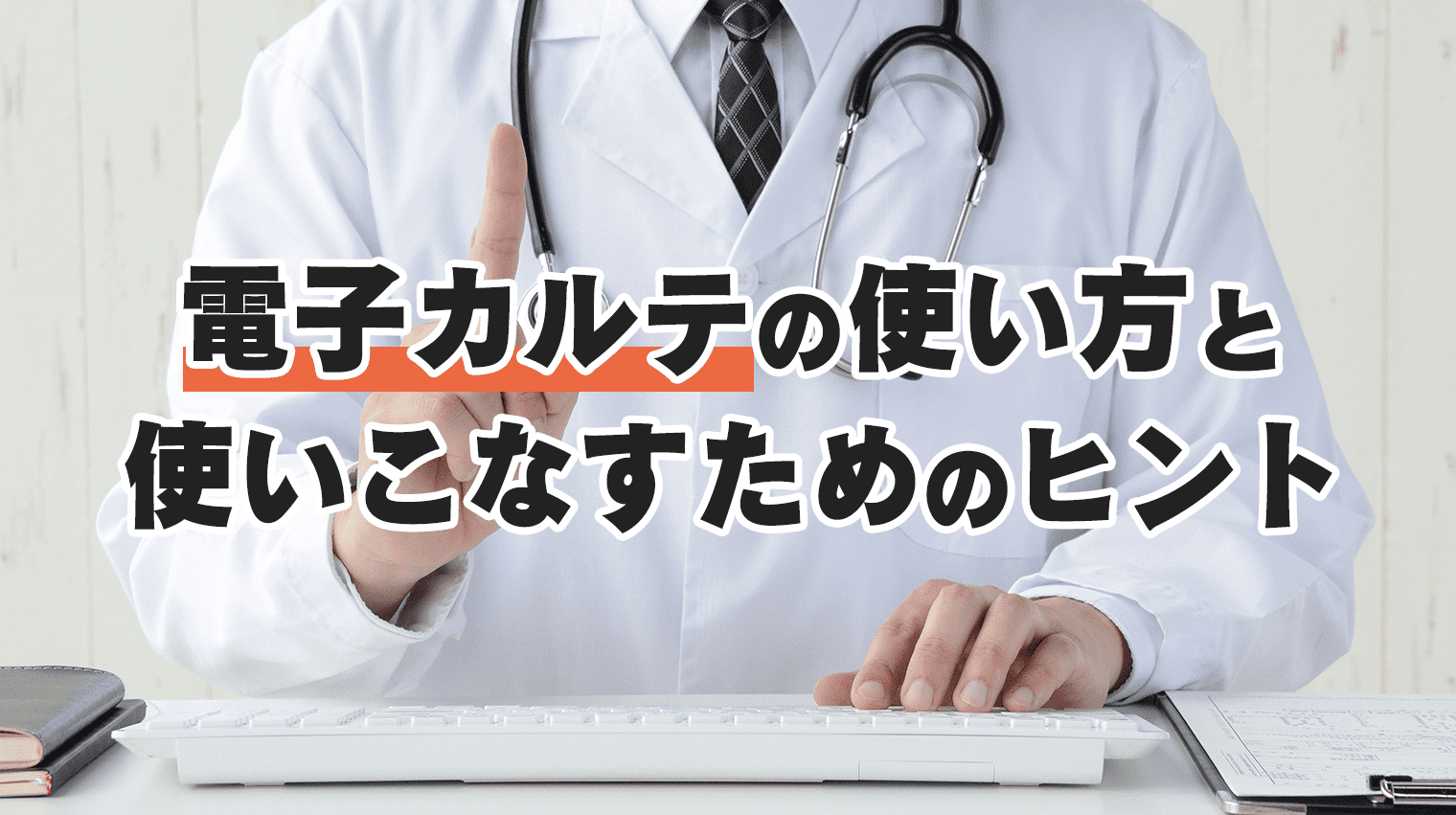
電子カルテの導入を躊躇しているクリニックのなかには、「うまく使えそうにない」と考えているクリニックもあるのではないでしょうか。また、導入してはいるものの、せっかくの便利な機能を使いこなせていないクリニックも多いかもしれません。そこで今回は、電子カルテを有効活用する方法を紹介していきます。
電子カルテをスマートに使いこなすために必要なこととは?
電子カルテをスマートに使いこなすためには、まず、「現状のままでいいや」という姿勢を改めることが大切です。これまでのやりかたを変えるためには、業務の見直しや改善、学習が必要なため、「面倒くさい」と思ってしまうかもしれませんが、少しの努力によって、その後の業務効率が何倍にもアップします。では、これまでのやりかたを変えるためには何が必要かというと、主に以下の4つのアクションが有効です。
研修や操作説明会の機会を設ける
電子カルテの使い方は、基本的には操作説明書を読めばわかります。しかし、「必要なときに読めばいいや」と思っていると、読まなくてもどうにかなる限り読むことがないので、知識がアップデートされません。そのため、電子カルテの使い方に関する研修や操作説明会の機会を設けるのが得策です。
電子カルテの導入がまだである場合は、導入時に研修や操作説明会を設けるのが一般的ですが、導入後であっても、知識のアップデートのために研修の機会を設けたい旨をカルテベンダーに相談してみるといいでしょう。
定期的に業務の棚卸をおこなってカルテ運用の改善を図る
定期的に業務の棚卸をおこなえば、研修や操作説明会の機会を設けるきっかけが生まれやすくなります。「業務の棚卸」とは、院内の業務を洗い出して整理する取り組みのことで、スタッフ全員で取り組んでいることから、一人ひとりの担当業務まですべてを可視化して、改善点を見出すことが必要となります。
電子カルテの運用を可視化する際には、「電子カルテを操作するにあたって不便に感じていることはないか」「操作方法がわからず解決していないことはないか」「カルテベンダーに質問したいと思っていることはないか」などを書き出して、一つひとつの課題の解決を目指しましょう。
電子カルテの操作を得意とする人材の雇用・育成
医療現場のDXは年々進んではいますが、実際のところ、IT、IoTに対して苦手意識がある人は一定数います。なかには、スタッフのほとんどがアナログ人間というクリニックもあるでしょう。その場合、電子カルテの操作を得意とする医療クラークの雇用や育成を検討してもいいかもしれません。
マニュアル、操作方法説明動画、FAQが充実している電子カルテを選ぶ
電子カルテの乗り換えを検討中なら、マニュアル、操作方法説明動画、FAQが充実している電子カルテを選べば、業務効率化に役立つさまざまな機能を上手に使えるようになる可能性が高いといえます。
電子カルテの基本機能情報
続いては、電子カルテの機能についてみていきます。
電子カルテとは、患者に関する基本情報や既往歴、身体所見、検査結果、投薬指示、治療方針など、従来、紙カルテに記載していた情報をデータとして記録するものです。そのため、これらの情報を電子データとして管理・編集できる機能が、基本の機能となります。
電子カルテの便利な機能
また、電子カルテには、医師や看護師、医療事務の業務を効率化してくれる便利な機能も多彩に備わっています。そのなかから、特に役立つ機能をピックアップして紹介していきます。
「テンプレート」「セット登録機能」の活用方法
電子カルテのスムーズな入力を実現してくれる機能としては、「テンプレート」「セット登録機能」が挙げられます。
テンプレート
電子カルテには、さまざまな「テンプレート」が備わっています。たとえば、「□頭痛 □鼻水 □咳 □発熱〇〇℃」「血圧〇〇/〇〇mmHg」のように、□の部分にチェック、〇の部分に数字を入れるだけで患者の状態を入力できるようになっているテンプレートがあります。
また、患者のスマホ、もしくは院内で用意しているタブレットを使って患者自身で問診表に入力してもらった結果を、そのまま電子カルテに落とし込むことで医師や看護師の入力負担を軽減する「セルフ入力テンプレートシステム」もあります。
そのほか、紹介状や診断書作成用のテンプレートが備わっている電子カルテもあります。テンプレートを活用すれば入力の手間が大幅に削減されるので、業務効率が上がることは間違いありません。
セット登録機能
「セット登録」とは、よく使う診療行為、主訴、所見、病名などを組み合わせてセットで登録しておくことです。セット登録自体にはある程度時間がかかりますが、一度登録してしまえば、使用頻度の高いオーダーや患者所見、療養指導内容などをすぐに呼び出すことができるため、カルテ入力時間が短縮されます。
また、最近では、セット登録をしておかなくても、使用頻度の高いオーダーなどをAIが学習して、自動的にセットが生成される機能を備えた電子カルテも増えています。
「予測機能」の使い方
「予測機能」は、スマホでいう「予測変換」と似た機能です。カルテに処方や処置などを入力すれば、推測される病名がいくつかサジェストされるため、そのなかから該当する病名をクリックして選択することで、スピーディに入力できます。入力しようとしていた言葉を選択する仕様であることから、「選択機能」と呼ばれることもあります。手入力ではなくリストから選択することによって、入力ミスや漏れを防ぐことにもつながります。
よく使う病名やオーダーが、ランキング順に表示されて、そのなかから選択する仕様のものもあります。
「検索機能」「付箋機能」の活用法
「検索機能」は、Google検索などと同じく、キーワードを入力することで該当箇所に一瞬で辿り着くための機能です。
また、これと似た機能として、重要な情報にタグをつけておくことで、後々取り出しやすくするための「付箋機能」もあります。これらの機能をうまく活用することで、必要な情報をスピーディに取り出すことができます。
「Do処方」の入力方法
「Do処方」とは、“前回と同じ処方”を意味します。なお、「Do」とは、“前回と同じ”という意味のラテン語である「Ditto」の略語です 。
電子カルテの「Do処方」機能を使えば、前回の処方内容が今回のカルテにコピーされるため、入力の手間が省けます。
「経営分析機能」の活用法
カルテに保存された診療データをもとに、傷病名のランキングや患者リピート率、患者の年齢層ごとの割合、居住地域などを把握することで、経営戦略に活かすことができる機能です。また、個々の患者の分析に活用して、よりよい医療の提供を目指すこともできます。
直感的な入力方法
電子カルテは基本的に直感的に操作できるものがほとんどですが、日ごろ、Microsoft Officeなどを使う習慣がない人にとっては、シンプルにデザインされたUIでも操作が難しく感じることがあるかもしれません。その場合は、「手書き入力」「タッチパネル入力」が可能な電子カルテを選べば、直感的に入力しやすいでしょう 。
電子カルテの基本的な使い方
続いては、電子カルテの基本的な使い方を説明していきます。
カルテ画面の操作方法
カルテ画面のデザインは電子カルテメーカーによって異なりますが、過去のカルテや検査結果などもタブで表示されている場合がほとんどで、必要なタブをクリックして内容を確認しながら、その日のカルテを入力することができます。
薬剤チェックの手順
カルテに処方内容を入力すると、食物アレルギーや個々人の禁忌、相互作用・副作用・重複投与などがないかどうかが自動でチェックされます。
病名チェックの方法
カルテに入力された処方や処置内容から推測される病名が表示されます。表示された一覧のなかから該当するものを選んでクリックするだけで入力できるので、操作が簡単なうえ、病名の漏れによる返戻・査定を防ぐことができます。
紙カルテから電子カルテへの移行の手順は?
紙カルテから電子カルテに移行するにあたっては、これまで紙カルテに入力してきた情報を電子カルテに取り込む必要があります。しかしもちろん、すべての手書き文字を電子カルテに転記するというわけにはいきません。そんなことをするためには膨大な時間が必要です。そのため、必要な作業と不要な作業にわけて、さらに優先順位を考えながら移行作業を進めていくことが大切です。具体的には以下のような手順で進めるといいでしょう。
患者の基本情報を電子カルテに移行させる
患者の住所や名前、既往歴などの基本情報を電子カルテに入力します。これには一定の時間がかかりますが、一度入力しておくと、必要なときに必要な情報をすぐに呼び出せるので便利です。
なお、レセプトコンピューター(レセコン)を含めて一新する場合、オンライン請求に使用しているレセプトデータを用いて、患者の基本情報や診療行為にかかったコストなどの情報を移行することができます。ただし、メーカーによって移行方法などに違いがあるため、担当者に相談することが必要です。
紙カルテに記載している診療情報をスキャンして電子カルテに取り込む
基本情報以外の診療情報に関しては、文字を打って転記するのではなく、スキャンして電子カルテに取り込みます。ただし、すべての紙カルテの基本情報を移行させるとなるとかなりの時間がかかるので、再診の患者がくるたびに、その患者の紙カルテの情報を電子カルテに移していくという方法もおすすめです。
もしくは、「1日何枚」と決めてスキャンする方法や、「今月は3か月以内に通院記録のある患者のぶん」と現在から遡りながらスキャンしていく方法もおすすめです。
スキャンする際の注意点として、精度は00dpi、PGB各8ビット以上のスキャナでスキャンすることが鉄則です。なぜかというと、手書きの文字や画像は、電子化した際に潰れてしまって判読できなくなる場合があるためです。また、電子化にあたってのフォーマットに指定はありませんが、PDF形式での保存が一般的なので、PDF形式を選択することをおすすめします。
なお、スキャンデータを移行し終えた紙カルテは廃棄して構いません。廃棄したぶん、保管スペースが不要となって空間を広く使えるので、できるだけ早く広い空間を確保したい場合は、スキャン作業をまきで進めていくといいでしょう。
電子カルテの操作方法を覚える
データの移行と並行して、電子カルテの操作方法を覚えるためのマニュアル作りや研修を実施していくことも大切です 。
クリニックでのカルテ活用方法
電子カルテの使用方法は、基本的にはクリニックと病院とで違いがありませんが、利用目的、活用方法には違いがあります。
クリニックでは、業務効率化目的はもちろん、電子カルテを上手に活用することによって、より質の高い医療を提供することを目指すことができます。なぜかというと、先に紹介したような機能が備わっているため、電子カルテがあれば、できることが増えるからです。つまり、クリニックでの理想的な活用方法は、「電子カルテに備わっている便利な機能を使いこなす」であるといえます。必要最低限の機能しか使っていないクリニックは、そのことを意識したうえで運用を見直してみるといいかもしれません。
病院でのカルテ活用方法
一方、病院では、電子カルテを活用する重要な目的として、他部門とのデータ共有が挙げられます。紙カルテで他部門に情報を共有するとなると、大病院では移動距離も相当なものですし、同時に2つ以上の部門で中身を確認することができないため不都合が生じます。その点、電子データの共有であれば、スピードが速いうえ、渡すカルテを間違えるなどの人的ミスも防げます。
病院の場合、クリニック向けの電子カルテのように、「すべてのシステムが電子カルテに集約されている」ということはなく、検査やオーダーのシステムは独立しているため、それぞれのシステムを電子カルテと接続して使うことが必要になります。
まとめ
昨今は、電子カルテを一度も使ったことがないという人は少ないと考えられますが、業務効率化を後押しする便利な機能や最新の機能を積極的に使っているという人は少ないのではないでしょうか。そうした機能を使わなくてもこれまで通り診療できるとしても、新しいことにチャレンジしてみることで、よりよい医療を提供するコツが掴めるということもあるかもしれません。クリニックから患者に提供できることがひとつ増えるたびに、患者の満足度が向上すると考えたら、いろいろ試してみて損はないと思えそうですね!
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。

執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
他の関連記事はこちら





