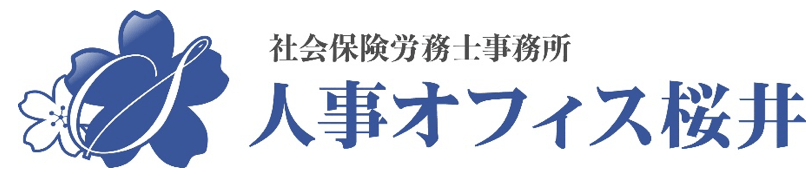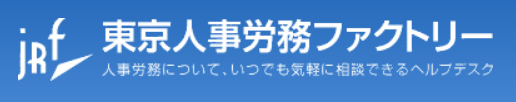多くのクリニックにとってスタッフはとても大切な存在です。人手が足りなければ業務が回らなくなることもあるので、退職したいとの申し出が急だと困ってしまう場合もあるでしょう。
しかもそれが集団退職ともなれば最悪。これまで通り、診察を続けながら採用にも時間を割かなければならないとなると、音を上げてしまいたくなって当然です。そうした事態を防ぐためにも、日ごろから、集団退職を防ぐ努力を怠らないことが大切です。
具体的には、一番大事なのは「スタッフを大事にする」こと。これに尽きます。スタッフ一人ひとりが「大事にされている」と実感できていれば、誰もがみんなで一斉に辞めようなどと言い出しません。そこでまずは、スタッフを大事にしないクリニックにはどんな特徴があるのかを考えていきたいと思います。
スタッフを大事にしないクリニックの特徴
まずは本題である「スタッフを大事にしないクリニックの特徴」をみていきます。
クリニックの理念を共有できていない
理念の共有は、スタッフを大事にできているかとは関係ないのでは? と思う人もいるかもしれません。しかし、これはもっとも大切なこと。
理念を共有しないまま、「こうしてほしい」と伝えたところで、伝えられたほうは「なぜそうしてほしいのか」が理解できないので、働いていてストレスが溜まる一方です。また、そもそも理念を共有できていないということは、スタッフを「一緒に理念を形にしていく仲間」だとみていないといえます。
スタッフが意見を発信しづらい雰囲気がある
経営者側が、「意見や要望があれば積極的に教えてほしい」といくら伝えたところで、院長がいつも忙しそうにしていて話しかける隙をみせなかったり、仕事に忙殺されてイライラしていたりすると、スタッフは意見を伝えることを難しく感じてしまい、結果的に「ちゃんと働き手の話を聞いてくれるクリニックに転職したい」と考えるようになって当然です。
問題があるスタッフをきちんと叱らない
連絡なしの遅刻や欠勤が多いなど、問題があるスタッフに対して甘い態度をとっていると、他のスタッフは、「真面目に働いている自分たちがバカみたい」と思ってしまいます。
場合によっては、「あの子だけ何をしても許される」「あの子だけ可愛がられていて癪に障る」と、特定のスタッフを依怙贔屓しているととらえられることもあります。
仕事ができるスタッフに仕事が集中してしまっている
仕事ができるスタッフに頼りすぎているパターンの場合、該当スタッフがストレスを抱えるのはもちろんのこと、その他のスタッフが「自分たちはお荷物だしよそに転職しても問題ないだろう」と思ってしまうことが考えられます。
また、人の何倍もの仕事をこなすスキルがあるがために、多くの仕事を抱えてしまっているスタッフは、「みんなの尻拭いばかりじゃなくて、もっと自分の能力を活かせる仕事をしたい!」と不満を抱えるでしょう。
給与水準が低い、福利厚生が充実していない
エリア内の競合と比べて給与水準が低すぎたり、福利厚生が充実していなかったりすると、「これだけがんばっても評価されないのか……」とガッカリしてしまうスタッフが出てくる可能性は極めて高いといえます。
福利厚生が充実し過ぎている
反対に、福利厚生が充実し過ぎているのもよくありません。どういうことかというと、給与や賞与が高くないのに、福利厚生の充実度が高いケースがあるということです。誰も活用していないものに多額なお金をかけられているとなると、「そんなことにお金をかけるくらいなら基本給を上げてほしい」と思うスタッフが出てきます。
一から十まで指示される
ひとつの仕事をやり終えると、「じゃあ次はこれをやって」だとスタッフの自主性が育ちません。仮採用期間ならともかく、いつまでたっても指示出しが多いようでは、スタッフらは、「自分たちはただのコマなんだな」「信用されていないんだな」と感じるものです。
全員参加の懇親会の開催頻度が高い
「若い世代は職場の人との飲み会はできるだけ参加したくないものだ」という話を聞いたことがある人は多いと思いますが、実際は若い世代に限ったことではなく、飲み会の場を苦手としている人も多いものです。
とはいえ、新入社員が入った際の歓迎会や、誰かが辞めるときの送別会などは、感謝の意味も込めて開催したいと考えるドクターもいるでしょう。その場合は、自由参加にしたり、スタッフみんなに行ってみたいお店を選んでもらったりと、気軽に参加してもらうための工夫を考えるといいでしょう。
スタッフ満足度を向上させるにはどうすればいい?
続いては、スタッフみんなに「ここで働き続けたい」と思ってもらえるよう、スタッフ満足度を向上させるにはどうすればいいかをみていきます。
業務マニュアルを作成する
特定のスタッフの負担が大きくならないよう、スタッフ一人ひとりが自分で確認して業務を進めるためのサポートとなる業務マニュアルを作成することは大変有効です。
業務マニュアルが整備されていると、余計な質問が飛び交わないことから全員が仕事しやすくなるだけでなく、「さらに仕事の質を上げるためにはどうすればいいか?」などの改善ポイントもみえてくるので、マニュアルを定期的に刷新すればみんながさらに働きやすくなります。
「おはよう」「おつかれさま」「ありがとう」などの言葉を意識的に使う
スタッフ腹を割って話しやすいようにと飲み会やイベントを積極的に開催したところで、院長が話しづらい雰囲気を醸し出していたら、働き手としては心のうちにある思いを打ち明けにくいものです。
それよりもまずは、「おはよう」「おつかれさま」「ありがとう」といった挨拶や労いの言葉、感謝の言葉を積極的にかけていくことで、スタッフも次第に心を開いていくものです。
1対1で話す場を設けたいなら、終業後ではなくランチタイムなどを利用するのも一手
スタッフ一人ひとりとしっかり話すために1on 1などの機会を設けることは大切ですが、プライベートを大事にしたいスタッフの場合、「今日は仕事が終わってもすぐに帰れないのか……」と憂鬱な気持ちになってしまうことも考えられます。
しかし、ランチタイムを利用してスタッフと話すのであれば、帰りの時間は変わらないだけでなく、「いつもと違っておいしいものを食べられそうだ」とそれだけで喜んでもらえることも多いはず。また、それによって、「ここまで自分たちのことを考えてくれるのはありがたいな」と心を開いてくれることも考えられます。
スタッフ一人ひとりの目標や理想の働き方を改めて確認する
クリニックに対する要望はなかなか伝えづらいとしても、自分の目標や理想の働き方を口にすることはさほど難しくはないはずです。一人ひとりの目標などを改めて確認すると同時に、それを叶えるためにクリニックとして何ができるかを一緒に考えていけば、スタッフは「このクリニックでなら自分は成長していける」と思ってもらえるはずです。
また、大きな夢や目標を叶えるために必要な小さなゴールにたどり着くたびに、「よくがんばっているね」と労いの声をかけることもお忘れなく!
福利厚生を見直す
スタッフのニーズを確認しながら福利厚生を見直せば、スタッフの満足度が高まるだけでなく、無駄な出費を抑えられるというメリットもあります。
スタッフルームなどの環境を改善する
スタッフルームなどの環境が改善されると、居心地のよさが増すため、スタッフは気持ちよく働くことができます。休憩中は靴を脱いでリラックスできるよう畳のスペースを設けたり、毎日重たい荷物を持ち歩かなくて済むよう、ロッカーを人数分用意したりと、できることはいくつかあるはずです。
人事労務の専門家に相談する
十分に対策をとってきたつもりでも、不意打ちをかけるように退職希望を出してくる人がいます。
理由を聞いてびっくり「そんなことを考えていたのか」「何も言わないから不満はないと思っていた」なんてこともありえます。こうした事態を防ぐためにも、人事労務の専門家に定期的に相談することで、自院のスタッフ教育などに問題がないかどうかを確認してもらうのもいいでしょう。
クリニックの集団退職リスクを減らすために
今の時代、より自分に合った職場への転職は珍しくはありません。コロナ感染症の影響で、安定していると思われていた大学病院でさえ、数百人もの医師・看護師が一斉に退職した事例があります。また、働き方改革の推進によって、今後の働き方について考え直す人も増えています。そうした状況下では、
経営者が離職を食い止めようと気を付けてもどうにもできないケースも多々もありますが、予期せぬ離職を少しでも防ぐために今すぐにできることがあるとすれば、まずはやはり「一緒に働いてくれる仲間を大切にすること」だと思います。
その「大事にしていること」をどうやって伝えていくのかは、クリニックそれぞれに合わせて考えていけるとよいですね。
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、2022年10月時点の情報を元に作成しています。

執筆 医療ライター 山野 成子
2児の母。看護師として20年以上、総合病院、透析クリニック、保育園、通所介護施設などを経験する。
主任看護師として人事採用・新人教育を担当した経験を活かし、現在は医療者向けの記事を執筆するライターとして活動中。
他の関連記事はこちら