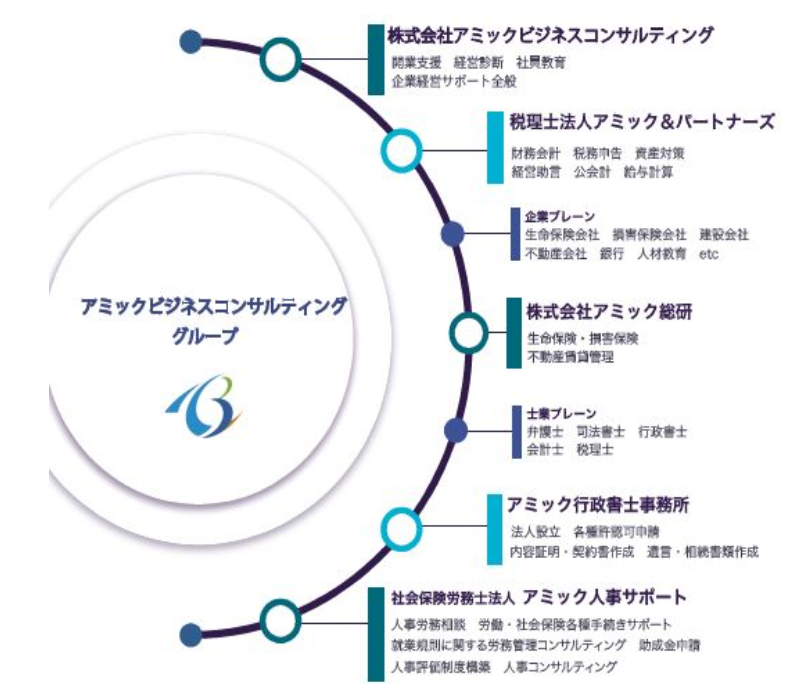ゆくゆくはクリニックを医療法人化させたいと考えている医師は多いはず。しかし、タイミングを図ることなく医療法人化すると、失敗に終わってしまう確率が上がります。では、医療法人化するのにベストなタイミングとはいつなのでしょうか? 早速解説していきます。
医療法人とは?
医療法人とは、病院、医師または歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設の開設を目的として、医療法の規定に基づいて設立される法人です。医療法人は、「財団法人」「社団法人」の大きく2種類に分けられます。といっても大半が社団法人で、厚生労働省によると、平成22年3月末時点においては、全医療法人のうち99.1%以上が社団法人です。
財団法人と社団法人の違いは?
財団法人と社団法人は何が違うのかというと、まず成り立ちが違います。財団法人は、個人や法人が無償で寄付した財産を使って設立される法人である一方、社団法人は複数人が集まって設立する法人です。
また、もともとの大きな違いとしては、社団の場合、出資持分のある法人を設立することができた点にありましたが、平成19年の法改正以降、出資持分のない法人しか設立できなくなりました。ただし、それ以前に設立された社団法人が大半を占めているため、現在でもほとんどの社団法人は出資持分がある法人ということになります。一方、財団法人設立に使われたお金は、法人が寄付したものであるため、後々解散となったとしても、返ってくることはありません。
つまり、開業医がこれから医療法人を設立するとしたら、基本的には医療法人社団を設立することになります。
医療法人化に最適なタイミング
続いては、医療法人化するのに最適なタイミングをみていきます。医療法人化にベストなタイミングは、何をもってベストというかにもよっても違ってきますが、大きく以下のケースが考えられます。
年間の所得が1,800万円を超えた
開業医は個人事業主ですが、個人事業主の場合、年間の事業所得が1,800万円を超えると、累進課税によって税率が40%になります。これに対して、医療法人の法人税は15~23.2%なので、医療法人化によって大きく節税することができます。
年間の社会保険診療報酬が5,000万円を超えた/自由診療報酬と併せた報酬が7,000万円を超えた
年間の社会保険診療報酬が5,000万円を超えた場合、もしくは自由診療報酬と併せた報酬が7,000万円を超えた場合、「概算経費」が使えなくなります。概算経費とはなにかというと、医業もしくは歯科医業を営む個人が、社会保険診療報酬にかかる費用を必要経費に算入する際に適用される特例措置のことです。概算経費を適用すると、実際の経費より多めの額で経費計上することが可能です。
| 年間の社会保険診療報酬 | 概算経費の計算方法 |
| 2,500万円以下 | その年の社会保険診療報酬×72% |
| 2,500万円超~3,000万円以下 | その年の社会保険診療報酬×70%+50万円 |
| 3,000万円超~4,000万円以下 | その年の社会保険診療報酬×62%+290万円 |
| 4,000万円超~5,000万円以下 | その年の社会保険診療報酬×57%+490万円 |
たとえば、社会保険診療報酬が4,000万円で実際の経費が2,000万円だったとして、上記の表に当てはめて概算経費として計算すると、4,000×57%+490万円=2,770万円となるので、770万円多く経費計上できるということになります。
これだけお得なシステムですが、「社会保険診療報酬が5,000万円以下」かつ「社会保険診療報酬と自由診療報酬を合わせて7,000万円以下」の事業主にしか適用されないと制限されているため、いずれか一方の条件から外れたタイミングは、法人化を考えるひとつのタイミングといえます。
分院展開など、事業拡大を検討している
分院展開、もしくは介護老人保健施設や看護師学校などの運営を検討しているなら、早い段階で法人化することをおすすめします。個人の開業医は、1か所以上の施設を開設することができないうえ、開設できるとしたらクリニックまたは病院となるので、医療法人化なくして事業拡大は不可能です。
事業継承したいと考えている
個人事業主として運営しているクリニックをゆくゆくは子どもや第三者に継承してもらいたいと考えている場合も、早い段階で法人化しておくことがおすすめです。なぜかというと、個人事業主のままだと、事業継承にあたって多額の相続税がかかるからです。一方、ドクターが財産権を持たない医療法人であれば、相続する財産がないとみなされるため、相続税が発生することなく、理事長を変更するだけで事業継承することができます。ちなみに、医療法人の財産は法人のものになりますが、自身の退職金額を設定すれば、お金を回収することは可能です。
開業時に投資した医療機器の償却期間が終わった
医療機器の償却期間は、開業から6年目が経過するまでに設定されています。その6年間に減価償却費を割り振るので、たとえば設備投資に6,000万円かかっていたとしたら、毎年1,000万円ずつ経費計上することになります。しかし、開業時に投資した医療機器に関しては、7年目からは減価償却費がゼロになるため、全体の経費が減るぶん、利益が増すことになります。これによって多額の税金が発生するのを避けるために、医療法人化するのも一手です。
“ベストなタイミング”はひとつの目安
上記に紹介したタイミングは、あくまでひとつの目安。特に、所得や診療報酬の数字だけに着目して法人化した結果、節税効果を十分に得られないこともあるでしょう。医療法人化することによって何がどう変わるのか、自分はどうしたいのかをよく考えたうえで、最終的な決断を下してくださいね。
特徴
対応業務
その他の業務
診療科目
特徴
その他の業務
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。