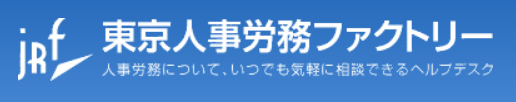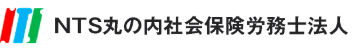クリニックのために働いてくれるスタッフはありがたい存在ですが、採用した結果、「何度も同じ失敗をしがち」「トラブルメーカーである」などが発覚した場合、他のスタッフへの影響を考えても、辞めてもらったほうがいい場合があります。しかし、クリニック側の「辞めてほしい」という願望に反して、当該スタッフは長く働きたいと思っている場合もしばしば。そこで今回は、問題があるスタッフに辞めてほしいときにはどういった対応が考えられるかをみていきます。
退職には2種類ある
労働者がその職場で働くことを辞める「退職」は、大きく2パターンに分けられます。
自主退職(=自己都合退職)
労働者自らの意思や都合による退職は、自主退職、または自己都合退職といいます。よくある理由は、結婚、妊娠、出産、家族の転職や転勤に伴う引っ越し、転職、体調不良などです。
会社都合退職
会社の都合で、労働者に辞めてもらうのがこのパターンです。「合意退職」「解雇」がこれに該当します。
ただし、合意退職は、「当該スタッフに退職をすすめて、納得したうえで自ら退職してもらう」という方法であるため、うまくいった場合、結果的には自主退職というかたちになります。
会社都合退職を進めるための正しい手順は?
当該スタッフが自主退職する見込みがなく、会社都合退職を進めたい場合、まずは「合意退職」を促します。そこで本人に納得してもらえない場合、退職してもらうことを諦めるか、もしくは解雇にするのが一般的な流れです。なぜかというと、たとえ100%当該スタッフに非があったとしても、スタッフ側に問題があったことをきちんと記録することなくいきなり解雇したら、解雇されたスタッフから「不当解雇だ」として訴えられる可能性が高いからです。
しかも、解雇されたスタッフの訴えをもとに、労働基準監督署から事情徴収されることになったり、助成金の申請に支障をきたしたりする場合もあります。しかし、まずは合意退職を目標に、当該スタッフに対して、どういう点が問題だから辞めてほしいと思っているのかを伝えて、「今後も改善されなければ辞めてもらう」と伝えて記録をとっていれば、後々、労働基準監督署から事情聴取されることになったとしても、指導したのに改善されなかった証拠を示すことができます。
また、問題行為が改善されず、「退職勧告したけど変わらなかったから解雇するしかない」と判断した場合、当該スタッフにたいして解雇通知することになります。
退職勧告した結果、訴えられないためにしておくべきこと
退職勧告した結果、スタッフに訴えられて慰謝料を払うハメにならないよう、日ごろから気を付けておくべきことがあります。
試用期間を設ける
まず、退職勧告しなくてはいけない事態に陥ることを極力避けるためにやっておくべきことがあります。それは、本採用の前に試用期間を設けることです。同時に、試用期間中に一定の基準に達していないと判断した場合、採用しないことを伝えておくことも不可欠。何を一定の基準とするかはクリニックによって異なるので、経験の有無などは問わないクリニックもあるかもしれませんが、最低限、遅刻や欠勤を含む「勤務態度」、クリニックの働きやすさを左右する「協調性」などは厳しくチェックすることをおすすめします。
問題行為、指導内容、改善の度合いを記録する
退職勧告を検討しているスタッフに対して、問題行為を注意すると同時にやっておくべきことは、「いつ、どんな問題行為があったか」を記録しておくことです。また、それに対してクリニック側でどんな指導をおこなったかも記録して、その後、改善されているかどうかも記録します。このすべてを日付とともに記録しておくことで、結果的に解雇した結果、労働基準監督署から事情聴取された際、クリニック側の正当性を訴えることができます。指導において、「改善されなければ辞めてもらう」と本人に伝えた旨もきちんと記録しておきましょう。
退職勧告のポイントは?
続いて、問題があるスタッフに対して、「問題点が改善されなければ辞めてもらう」と伝える際のポイントをみていきます。
何が問題であるかを本人に伝える
本採用後に問題があることが発覚して、退職を促したい場合、まずは本人に、何が問題であるのかを伝えることが必要です。「無断欠勤が多い」「他のスタッフと衝突しがち」「患者からクレームが入っている」など理由はさまざまですし、複数の理由がある場合もあるでしょう。それを本人にきちんと伝えて、「このまま改善されなければ辞めてもらう」とクリニック側の意思を示しましょう。
伝え方に工夫する
結果的に辞めることになるとしても、問題行為が改善されて働き続けることになったとしても、退職勧告の際の言葉遣いや態度に相手への尊重がなければ、あとあとまで相手がクリニックに対してマイナスの感情を抱き続けることになります。場合によっては、元従業員という立場から悪い口コミを書かれることもありえるので、極力相手にイヤな気持ちを与えないような伝え方が望ましいといえます。具体的には、「仕事熱心であることはありがたいが……」「先輩の態度にカッとなった気持ちもわかるが……」など、相手を肯定する前置きをしたうえで本題に入るなどと配慮するといいでしょう。
退職勧告を受け入れてもらいやすいような条件を提示する
問題行為が改善されるかどうか見守る気にもなれないほど、できるだけ早期に辞めてもらいたい場合などは、退職勧告を受け入れてもらいやすいよう、当該スタッフにとってメリットが大きい条件を提示するのも一手です。よくあるのは、「退職金に一定額上乗せ」「消化していない有給休暇を買い取る」などです。ただし、先方にとって有利な条件を提示したからといって辞めてもらえるとは限りません。また、好条件を提示したことは、後々、“前例”となって、それ以降に辞める人から同じ条件を求められる可能性が高いため注意が必要です。
退職勧告の注意点
退職勧告をすすめるにあたっては、注意したいこともあります。どんなことかというと、「本当に問題行為があったのか」「当該スタッフだけに問題があったのか」をしっかり見極める必要があるということです。特に、クリニック内の人間関係がよくない場合は、スタッフ同士で責任をなすりつけあっている可能性や、パワハラが起きている可能性も考えられます。それによって、実際はミスしていないスタッフがミスしたことになっていることなどは大いに考えられるので、問題が起きた時点で個別面談を設けることが大切です。
退職勧告を成功させるコツは?
退職勧告において大事なポイントを押さえていたとしても、当該スタッフのクセが強い場合など、スムーズに退職してもらえないことが考えられます。そこで続いては、退職勧告を成功させるためのコツを紹介します。
まずは「懲戒処分」を下して、その事実を残す
問題行為があるスタッフをいきなり解雇することは難しいですが、減給、出勤停止、降格などの懲戒処分を下すことができます。処分を下されたことでそのまま辞めてしまうパターンもありますし、自ら辞めることがなかったとしても、その後も問題行為が繰り返された場合、「処分を下したけど、その後も問題行為が繰り返された」との主張に活かすことができます。
懲戒処分は7種類
懲戒処分は、減給や出勤停止を含めて全部で7種類あります。処分が軽い順に、「①戒告 ②けん責 ③減給 ④出勤停止 ⑤降格 ⑥諭旨(ゆし)解雇 ⑦懲戒解雇」となります。「戒告」とは口頭で注意することで、「けん責」とは、同様の行為を繰り返さないよう、始末書を提出させることです。また、諭旨解雇とは、従業員と雇用主が話し合って、双方納得のうえで解雇処分を進めること、「懲戒解雇」は、雇用主が一方的に労働契約を解消することです。
懲戒処分は同じ理由で2度以上下せない
懲戒処分は、同じ理由では1度しか下すことができません。これは、憲法39条によって、同じ罪で2回処罰できない「一事不再理」が定められているためです。たとえば、「何度注意しても遅刻を繰り返す」との理由で降格の処分を下した場合、その後、問題行為が改められなかったとして、再度降格の処分を下せないのはもちろん、「遅刻を繰り返すから」の理由では、戒告、けん責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇のすべての処分を下すことができません。そのため、当該スタッフが退職勧告しても辞めそうにない場合、最後の切り札として「懲戒解雇」を残しておいたほうが賢明なため、なかなか懲戒処分は下せないということになります。
当該スタッフに、「辞める選択は自分にとってもベスト」と思ってもらう
当該スタッフに、「あなたにはもっと合う職場がある」と伝えることは、退職勧告成功の大きな秘訣です。「そんな働きぶりじゃどこに行ってもうまくいかないよ!」などは絶対に禁句。相手を逆上させてしまうだけでなく、いつまでも根に持たれる場合が多いので、「あなたのよさを活かせる職場のほうがいいと思う」など、相手を気遣うそぶりを見せましょう。実際に、相性のいい職場に移ることで、水を得た魚のように生き生きと働けるようになる人も一定数います。
解雇には3種類ある
続いては、解雇の種類について説明します。
懲戒解雇
先に説明した通り、7種類の懲戒処分のうち、もっとも重い処分が「懲戒解雇」です。クリニックの規律に違反した場合などに適用されます。ただし、「当該スタッフに弁明の機会を与えていない場合」「クリニックに実損が生じていない場合」「懲戒解雇処分を下さなくても秩序の回復が可能な場合」は、懲戒解雇が認められないことがあります。
整理解雇
クリニックの経営が悪化して、今まで通りの人数を雇うことができずに解雇する場合、「整理解雇」となります。整理解雇は、以下の4つの要件を満たしていなければ合法だと認められません。
1. 客観的にみて整理解雇の必要性がある
2. 解雇を回避するために最大限の努力をおこなった(おこなったが避けられなかった)
3. 解雇の対象となる人選の基準、運用が合理的におこなわれている
4. 雇用主と従業員との間で十分に協議を重ねた
普通解雇
「懲戒解雇」「整理解雇」以外の解雇は、基本的に「普通解雇(または「解雇」)」となります。ただし、正当な理由がなければ解雇はできません。「問題行為を注意しても改善されない」「健康上の理由で職場復帰が見込めない」「著しく協調性に欠ける」などが“正当な理由”に該当します。
退職勧告、解雇においては忍耐が必要
退職勧告から合意退職に至る場合も、合意退職にもっていくことができず解雇の手続きをとることになる場合も、一日で決着がつくものではないので、クリニック側もスタッフ側も疲弊することは間違いありません。しかも、その間はお互い心にモヤモヤを抱えているので、クリニックの雰囲気も少なからず悪くなるでしょう。そうなったとき、不平不満を口に出したり表情ににじませたりすると、クリニック側の分が悪くなることもあります。なかには、「クリニックの悪いところをすべて記録して労働基準監督署に報告しよう!」と考えているスタッフもいるかもしれないので、精神的にきつくても、いつも通り業務をこなすよう心がけてくださいね。
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。