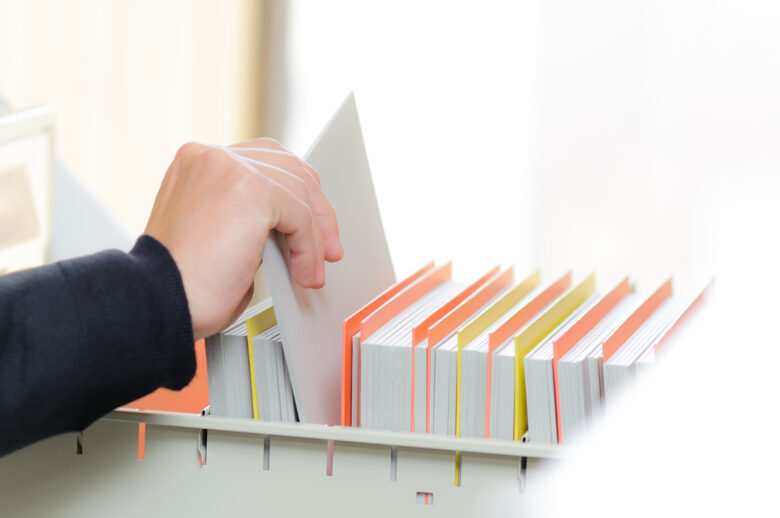
医療法人の承継について考えるうえで、必ず理解しなければならない用語のひとつが「出資持分」です。医療法人の形態は、全体の99%以上を占める「社団法人」と1%未満の「財団法人」の2つに分類され、さらに社団法人の医療法人は、「出資持分あり」と「出資持分なし」の大きく2種類にわけられます。では、「出資持分あり」と「出資持分なし」とでは何が違うのでしょうか? また、承継とどのように関連しているのでしょうか? 詳しく解説していきます。
医療法人の出資持分とは?
医療法人の出資持分とは、医療法人に出資した人が、個々の出資額に応じて払い戻しを受けたり、残余財産の分配を受けたりする権利のことです。株式会社において株主が持つ財産権に似ていますが、株主は議決権も与えられる一方、医療法人においては、議決権を行使できる構成員である「社員」は出資している必要がないため、「社員であるが出資者ではない」または「出資者ではあるが社員ではない」というケースがあり得ます。ただし、実際のところは、「社員であって出資者でもある」というケースがほとんどです 。
クラウド型電子カルテ「CLIUS」
クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。
詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。
出資持分あり医療法人とは
「出資持分あり医療法人」とは、出資者に対する財産の分配および返還に関して、定款に定めている医療法人を指します。医療法人が解散する場合や、出資者が退社する場合に、定められている通りの権利を行使できることになります。
なお、「出資持分あり医療法人」は、2007(平成19)年の医療法改正によって新規設立が禁止されました。理由は、医療法人の非営利性を徹底させて、医療提供を安定させることが重要だと考えられるようになったためです。つまり、社員が死亡もしくは退社した場合などに、出資持分の払い戻しが要求されたことによって、医療を安定的に提供できなくなることを防ごうというわけです。
ただし、法改正前に設立された「出資持分あり医療法人」は現在も存在します。該当する医療法人は、「経過措置型医療法人」と呼ばれており、一定期間、その形態を維持できることとなっています。具体的にいつまでの期間、形態を維持できるのかについては定められておらず、将来的に「出資持分なし医療法人」に移行することが推奨されています。
なお、詳しくは後述しますが、2026(令和8)年12月31日までに、「出資持分なし医療法人」に移行する申請手続きをとった場合、相続税・贈与税の納税が猶予されるなどのメリットがあります。
出資持分なし医療法人とは
「出資持分なし医療法人」とは、定款において出資持分に関する規定が定められていない医療法人を指します。2007年の医療法改正以降に設立された医療法人は、すべて「出資持分なし医療法人」です。なお、出資持分がないということは、法人の財産はすべて法人自体が管理して、法人の目的達成のために使っているということになります。
「出資持分なし医療法人」では、解散時に財産が分配されることがないため、相続税や贈与税の問題が生じにくいといえますが、「出資持分なし医療法人」に分類される「基金拠出型医療法人」の場合、解散時または「基金返還請求権」が行使された際に、医療法人は拠出された資金を変換する必要があります。この変換条件に関しては、定款に明記しておく必要があります。
なお、「基金返還請求権」とは、拠出した財産や金銭を変換してもらうよう請求する権利のことですが、いつでも変換可能というわけではなく、法人に余剰財産があるときのみ返還請求に応じなければならないとされています 。
基金拠出型医療法人とは?
前述の「基金拠出型医療法人」についてもう少し詳しく説明すると、法人の活動の原資となる資金の調達手段として、基金制度を採用している医療法人を意味します。基金拠出型医療法人は、「出資持分なし医療法人」の“一類型”とされていますが、これは平成19年に施行された第五次医療法改正によって導入された類型で、この法改正後に新設された医療法人の多くが、基金拠出型医療法人です。
参照:厚生労働省「医療法人の基礎知識~医療法人の類型~基金制度を採用した医療法人」
「出資持分あり医療法人」「出資持分なし医療法人」比較
続いて、「出資持分あり医療法人」「出資持分なし医療法人」の違いを改めて確認しましょう。
| 区分 | 出資持分あり医療法人 | 出資持分なし医療法人 |
| 財産権 | あり(=出資者は、医療法人の財産に対して、出資額に応じた権利を有する) | なし(=出資者は、医療法人の財産に対する権利を有していない) |
| 解散する際の権利(残余財産) | あり(=出資者には出資割合に応じて残余財産が分配される) | なし(=出資者に財産が分配されることがない) |
| 払戻請求権 | あり(=出資者は持分を買い取るよう医療法人に請求できる) | なし(=出資者は持分を買い取るよう医療法人に請求することはできない) ※ただし、基金拠出型医療法人の場合、設立時に拠出した金額の返還を請求できる |
| 相続の対象となるかならないか | 対象となる(相続税の課税あり) | 対象とならない(相続税は発生しない) |
| 売却(M&A)のスキーム | ・事業譲渡 ・持分の譲渡 ・合併 ・法人格の売買 |
・事業譲渡 ・合併 ・法人格の売買 |
財産権
前述の通り、「出資持分あり医療法人」の出資者は、医療法人の財産に対して出資額に応じた権利を持っており、返還も請求することができますが、「出資持分なし医療法人」の出資者は、医療法人の財産に対して権利を有していません。
解散する際の権利
「出資持分あり医療法人」が解散する場合、残余財産は出資者ごとの出資割合に応じて分配されます。たとえば、2名の医師が3,000万円ずつ出資して設立した「出資持分あり医療法人」の解散時に5,000万円の財産が残っていた場合、各医師は2,500万円ずつ受け取れるということになります。
一方、「出資持分なし医療法人」が解散する場合、残余財産は出資者に分配されることがありません。その場合、残余財産はどうなるのかというと、国庫に帰属することになります。
払戻請求権
「出資持分あり医療法人」において、出資した医師の一人が医療法人を離れる際に「払戻請求権」を行使した場合、医療法人を離れる医師の持分を残りの医師が買い取る必要があります。これに関して注意したいのが、出資額を買い取るのではなく、「持分を買い取る」必要があるという点です。
持分とは、それぞれの人が持つ権利の“割合”のことなので、医療法人の経営状況によっては、出資額を大きく上回る金額を払い戻しすることが必要になります。
一方、「出資持分なし医療法人」の場合、払戻請求権は、医療法人を離れる医師は基本的には払戻請求権を有していませんが、「出資持分なし医療法人」が「基金拠出型医療法人」であった場合、設立時に拠出した金額は返還請求できるということになります。
相続の対象となるかならないか
出資者が死亡した場合、「出資持分あり医療法人」は相続の対象となります。相続するためには、相続税を支払う必要がありますが、相続税は現金で支払わなければならないため、金額によっては、医療法人から財産の払い戻しを受けないと、相続税を納めることができないことがあります 。
一方、「出資持分なし医療法人」の場合、法人そのものは相続の対象とはなりません。ただし、「基金拠出型医療法人」の場合、「基金返還請求権」は相続の対象となります。被相続人が生前に基金返還請求権を行使する意志を示していた場合や、医療法人や相続人全員が同意している場合、相続人が「基金返還請求権」を相続することができます。
売却(M&A)のスキーム
「出資持分あり医療法人」の場合、出資持分を財産権として売却することができます。ただし、売却益とみなされる部分には、譲渡所得として所得税および住民税がかかることになります 。
一方、「出資持分なし医療法人」の場合、出資持分の売買によるM&Aはできませんが、事業譲渡、合併、法人格の売買といったスキームは実施できます。
それぞれの注意点について解説していきます。
「出資持分なし医療法人」のM&Aにおける注意点
「出資持分なし医療法人」の3つの売却方法についての注意点は次の通りです。
事業譲渡:
医療法人の事業の一部または全部を、別の法人に譲渡する形式です
メリット
買収側は必要な事業だけを選んで取得することができるため、負債や偶発債務を引き継ぐリスクを抑えられます。売却側は、法人自体は存続するため、清算等の手続きが不要となる場合があります。
デメリット
許認可の引き継ぎが必要になる場合が多く、手続きが煩雑になる可能性があります。個別の資産や契約を移管するため、手間がかかります。
合併
複数の医療法人が一つに統合する形式です。
メリット
医療法人自体が一体となるため、許認可の再取得が不要な場合が多く、手続きが比較的簡素です。シナジー効果を追求しやすいという利点もあります。
デメリット
合併に伴い、統合後の法人に統合前の法人のすべての権利義務が承継されるため、簿外債務などのリスクも引き継ぐ可能性があります。従業員の雇用条件の統一なども必要になります。
法人格の売買
これは実務上稀ですが、法人の理事長や社員の変更を通じて、実質的に法人を承継する形態です。
メリット
事業譲渡や合併よりも手続きが簡素化される場合があります。
デメリット
債務や偶発債務の引き継ぎリスクが大きく、M&Aの専門家による徹底したデューデリジェンスが不可欠です。また、医療法人の非営利性との兼ね合いで慎重な検討が必要です。
「出資持分なし医療法人」のM&Aにおいては、法人の評価額の算出方法が「出資持分あり医療法人」と異なる点に注意が必要です。出資持分がないため、純資産価額法などが用いられますが、買収側としては「将来の収益性」を重視した評価がなされることが一般的です。また、買収後の経営体制や、理念の継承なども重要な検討事項となります。
「出資持分あり医療法人」「出資持分なし医療法人」の割合は ?
前述の通り、2007(平成19)年の医療法改正によって「出資持分あり医療法人」の新規設立は禁止されましたが、2024(令和6)年時点での医療法人社団は、「出資持分あり医療法人」の割合のほうが多いことがわかっています。具体的には、この時点での医療法人社団の総数は58,508件で、そのうち「出資持分あり医療法人」は36,393件(約62%)、「出資持分なし医療法人」は22,115件(約38%)です。
また、先に述べた通り、「出資持分あり医療法人」は「出資持分なし医療法人」に移行することが推奨されていますが、実態としては移行が進んでいるとはいえません。理由はいくつか考えられますが、主なものとしては、理事長が持分を放棄したくないと感じていることや、医師ひとりの医療法人の場合、移行の必要性を感じにくいことなどが挙げられます。
2026年12月31日までに「出資持分なし医療法人」への移行計画を申請すると支援措置が適用される
そうした現状を鑑みて、厚生労働省は、「出資持分なし医療法人」への移行促進策を拡充中です。具体的には、2026年12月31日までに「出資持分なし医療法人」への移行計画を作成して申請することによって、厚生労働大臣の認定を受けられるというもので、認定を受けた医療法人には、相続税および贈与税の納税猶予や、低利での資金調達のための貸し付けなどの支援措置が適用されることになります。
「出資持分なし医療法人」への移行手続きの具体的な流れと注意点
「出資持分あり医療法人」から「出資持分なし医療法人」への移行は、単に定款を変更するだけでなく、さまざまな手続きが必要です。厚生労働省の認定を受けることで支援措置が適用されますが、その手続きは専門知識を要します。
1. 移行計画の策定と認定申請
まず、厚生労働大臣の認定を受けるための移行計画を策定して、申請します。この計画には、移行後の法人の運営方針や、出資持分の放棄に関する具体的な計画などが含まれます。
2. 定款変更と登記
厚生労働大臣から認定を得た後、定款から出資持分に関する規定を削除して、法務局で変更登記をおこないます。
3. 社員総会での決議
出資持分の放棄は、社員の重要な権利に関わるため、社員総会での特別決議が必要です。この際、出資者全員の同意を得ることが非常に重要になります。
4. 出資持分の評価と放棄
出資持分の放棄にあたり、現在の出資持分の評価額を算定する必要があります。この評価額は、税務上の課税対象となる可能性があるため、慎重におこなう必要があります。
5. 専門家への相談
移行手続きは、税務・法務・会計の専門知識が複合的に必要となるため、税理士、弁護士、司法書士などの専門家と連携して進めることが不可欠です。特に、出資持分の放棄に伴う税務上の影響は大きいため、事前に十分なシミュレーションをおこなうことが重要です。
「出資持分なし医療法人」への移行にかかる期間と費用
移行にかかる期間は、医療法人の規模や関係者の数、手続きの複雑さによって異なりますが、一般的には数ヶ月から1年程度を要する場合があります。また、専門家への報酬や登記費用など、数十万円から数百万円程度の費用が発生する可能性があります。
「出資持分なし医療法人」への移行に関する注意点
出資持分の放棄に伴い、放棄した出資者には課税が生じない一方、他の出資者に贈与税が課される可能性があるため、移行の際には、認定医療法人への移行による税制優遇措置(納税猶予等)を最大限活用できるよう、慎重な検討が必要です。
移行を検討する場合は、まず顧問税理士や専門機関に相談して、自院の状況に合わせた具体的なシミュレーションをおこなうことが最も重要です。
参照:厚生労働省「持分なし医療法人」への移行促進策 延長・拡充のご案内
「出資持分あり医療法人」のままでいることのデメリットは ?
「出資持分なし医療法人」への移行促進策が実施されていてもなお、「出資持分あり医療法人」のままでいることのメリットが大きいということのように思われますが、「出資持分あり医療法人」のままでいることにはデメリットもあります。具体的にどのようなデメリットがあるのかを解説していきます。
出資者が死亡した場合に相続税が発生する
「出資持分あり医療法人」の出資者が死亡した場合、持分は相続財産となるため、相続税がかかります。しかも、持分の評価によっては相続税の金額は数億円にのぼることもありますが、医療法人の持分は換金性がないため、相続人は、相続税を支払うための資金調達に苦しめられる場合があります。
出資者が持分放棄した場合に贈与税が発生する
出資者が自分の持ち分を放棄する場合、持分を放棄した出資者に税金が課せられることはありませんが、持分を放棄した出資者以外の出資者の持分価値が上昇することになるため、持分を放棄していない出資者らに贈与税の負担が生じることになります。
たとえば、医師Aと医師Bが同じ額を出資して2人で設立した医療法人の評価額が10億円になっていたとして、医師Aが持分を放棄するとなると、課税財産5億円に対して医師Bに贈与税が課せられることになります。
一方、「出資持分なし医療法人」へと移行することに決めて厚生労働省の認定を受け、医師A、医師Bともに持分を放棄した場合、医療法人に対して計10億円が贈与されたことになりますが、一定の条件を満たしていれば贈与税が非課税となります。
「出資持分なし医療法人」への移行がもたらす非税務的なメリット・デメリット
「出資持分なし医療法人」への移行は、税務上のメリットが大きいことは前述の通りですが、税務以外の側面でも、医療法人の運営や承継に影響を及ぼします。
「出資持分なし医療法人」に移行することによるメリット
事業承継の円滑化
出資持分がなくなることで、次世代への承継時に高額な出資持分の買い取りや相続税の問題が生じません。これによって、後継者選びの選択肢が広がり、スムーズな承継が期待できます。
経営の安定性
出資者の死亡や退社に伴う持分払戻請求によって、法人の資金繰りが悪化するリスクがなくなります。これによって、安定的な医療提供体制を維持しやすくなります。
非営利性の明確化
医療法人の非営利性がより明確になり、社会的な信用度を高めることにもつながります。
役員報酬設定の自由度
「出資持分あり法人」では、持分評価額への影響を考慮して役員報酬を低く抑えるケースがありますが、「出資持分なし医療法人」になれば、評価額を気にせず適切な役員報酬を設定しやすくなる場合があります。
「出資持分なし医療法人」に移行することによるデメリット
創業者のリターン喪失:
出資持分を放棄することによって、将来的な法人の資産増加に伴う財産的リターンがなくなります。創業者にとっては、これまで築き上げてきた法人の資産に対する権利を失うことになります。
資金調達の難しさ(一部)
出資持分がないため、新たな出資を募る形式での資金調達は困難になります。ただし、金融機関からの融資や基金制度の活用は可能です。
社員総会の合意形成
移行の意思決定には、社員総会での同意が必要であり、特に複数の出資者がいる場合には、合意形成に時間を要する可能性があります。
「出資持分なし医療法人」に移行する以外に税務上のリスクを減らす方法はある ?
「出資持分あり医療法人」のままでいることには、前述の通り、税務上のリスクが伴いますが、「出資持分なし医療法人」に移行する以外にも、リスクヘッジのためにできることはあります。
持分の評価を引き下げる
相続税は持分の評価が高ければ高いほど膨れ上がるので、持分の評価を下げることが有効です。具体的にどうすればいいかというと、まず考えられる方法が、建物の大規模改修や退職金の支払いなどによって利益を圧縮して、純資産を減らすという方法です。また、MS法人を有している場合、医療法人の利益をMS法人に移転させるという方法も考えられます。
持分以外の財産について適切な相続対策をおこなう
医療法人の持分以外の相続財産について適切な相続対策をおこなうことで、相続税全体としての負担が軽減されます。持分以外の相続財産とは、たとえば現金や不動産、株式などです。具体的にどのような対策をとればいいかというと、たとえば生命保険を活用すれば、生命保険の非課税枠に、相続税を支払うためのキャッシュをプールすることができますし、死亡退職金を相続人に渡すよう手配しておくこともキャッシュを増やすことにつながります。また、現金や不動産の生前贈与は、相続時の財産規模縮小につながります。
ただし、これまで解説してきた通り、医療法人の持分は換金性がないため、現金を減らしすぎると、いざ納税が必要なときに資金調達に奔走しなければならなくなるため、資産のバランスを考えて対策をとることが重要です。
医療法人の出資持分はM&Aや相続に大きな影響を及ぼす
医療法人の持分があれば、財産の分配や返還を求めることができるため、大切な資産として放棄したくないと考える人は多いでしょう。しかし、ここまで解説してきた通り、医療法人の持分はM&Aや相続に大きな影響を及ぼすこともあるため、デメリットやリスクについても考えておくことが非常に大切です。自院の場合、どういったリスクの可能性が高く、どんな対策をとっておけばいいのかについては専門家に聞くのが一番。顧問税理士がいる場合などは、まずは気軽に相談することからはじめてみてもいいかもしれませんね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。





