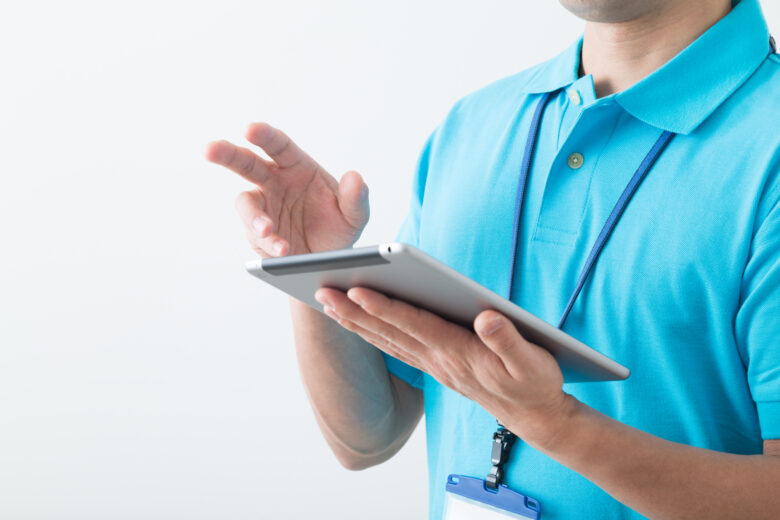
「電子カルテ情報共有サービス」とは、全国の医療機関や薬局などで患者の電子カルテ情報を共有するための仕組みです。2025年中にサービスが本格始動となることが決まっていますが、各医療機関や薬局はそこに向けて何か準備することがあるのでしょうか? 詳しく解説していきます。
そもそも電子カルテ情報共有サービスとは? 国の医療DX構想における位置づけ
電子カルテ共有サービスとは、医療DXを進めるうえでの骨子となる取り組みである「全国医療情報プラットフォーム」の仕組みの一つです。
では、「全国医療情報プラットフォーム」とは何かというと、医療機関、介護施設、公衆衛生機関、自治体でバラバラに保存・管理されている患者の医療関連情報を、一つに集約して閲覧共有・管理するための新しいシステムのことで、全国どこからでもリアルタイムで情報を共有できる状態を目指しています。
そのなかで、「電子カルテ情報共有サービス」によって提供されるサービスは、次の4つのサービスです。
1.診療情報提供書を電子で共有できるサービス(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付)
2.各種健診結果を医療保険者および全国の医療機関や本人などが閲覧できるサービス
3.患者の6情報を全国の医療機関や本人などが閲覧できるサービス
4.療養指導情報などを本人などが閲覧できるサービス
サービスの詳細については次の通りです。
| サービス | 詳細 |
| 診療情報提供書を電子で共有できるサービス(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付) | このサービスによって、紹介先医療機関は、すぐに診療情報提供書を閲覧することが可能となるため、医療機関間の情報連携が効率よくおこなえるようになります。また、診療情報提供書には必要に応じて退院時サマリーなどを添付することができます |
| 各種健診結果を医療保険者および全国の医療機関や本人などが閲覧できるサービス | 医療機関が電子カルテ情報共有サービスに健康診断結果報告書を登録すると、患者本人が健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。また、全国の医療機関や加入する医療保険者も、登録された健康診断結果報告書を取得・閲覧することができます |
| 患者の6情報を全国の医療機関や本人などが閲覧できるサービス | 患者に関する「アレルギー」「感染症」「薬剤禁忌」「検査」「処方」「傷病名」の6つの情報を全国の医療機関や患者本人が取得・閲覧できる仕組みです。他の医療機関において診断された傷病名やアレルギー、検査結果をスピーディに確認できることから、救急医療などの日常の診療に活用されるほか、災害時に避難先の医療機関などで病名やアレルギー情報などについて確認できます |
| 療養指導情報を本人などが閲覧できるサービス | 医師から患者に対して提供される療養上のアドバイスを、マイナポータルから閲覧することができる仕組みです。アドバイスに至った傷病名や検査結果、処方情報なども併せて確認することができるため、自身の健康状態についてしっかり把握できるだけでなく、アドバイスに基づいて生活習慣を改めることで、健康状態の改善を目指せます |
医療機関間で共有される「3文書6情報」とは?
前述の通り、電子カルテ共有サービスによって提供される4つのサービスのうちの1つが「患者の6情報を全国の医療機関や本人などが閲覧できるサービス」ですが、「6情報」は電子カルテ情報共有サービスを通じて標準化・共有される医療データセット「3文書6情報」として理解しておくことが大切です。
「6情報」の内訳は上記表に記した通りですが、「3文書」とは何かというと、「健康診断結果報告書」「診療情報提供書」「退院時サマリー」の3つです。
それぞれの具体的な内容は次の通りです 。
3文書
| 健康診断結果報告書 | 特定健診・後期高齢者健診・人間ドックなどの各種検診結果を記載した書類 |
| 診療情報提供書 | 特定の医療機関における診療内容を記載した書類 |
| 退院時サマリー | 患者の病歴・治療時の所見、ケアの履歴をまとめた書類 |
6情報
| アレルギー | 食品・飲料・環境など、診断をつけた薬剤以外のアレルギー情報 |
| 感染症 | 梅毒STS、梅毒TP、B型肝炎(HBs)、C型肝炎(HCV)の検査結果 |
| 薬剤禁忌 | 医薬品や生物学的製剤などでの薬剤アレルギーの情報 |
| 検査 | コレステロール値や尿蛋白、血糖値など臨床検査項目の基本コードセットの履歴 |
| 処方 | 患者に処方した薬の情報 |
| 傷病名 | 患者に診断した病気の名前 |
電子カルテ情報共有サービスが開始されることのメリットは?
電子カルテ情報共有サービスの本格始動は、医療機関にも患者にもメリットをもたらします。
【医療機関側】医療の質向上と事務コスト削減、働き方の改善
医療機関にとっての大きなメリットは、患者の病名・検査結果・アレルギー情報などをスピーディに確認できることから、患者に対して、より安全かつ的確な医療を提供できるようになることです。平時はもちろん、救急時や災害時などにも、質の高い医療を提供することができます。
また、診療情報提供書などの文書を電子データで共有できることから、書類の発行・送付コストが削減されます。さらに、6情報の共有によってアレルギーや薬剤禁忌なども把握できることから、問診が効率化されて医療事務の業務負担が軽減されます。
時間や手間は少なくして質の高い医療を提供できるようになれば、医師や看護師はより効率よく働くことができるようになります。このことは、医療の担い手の確保にも資することとなります 。
【患者側】迅速で質の高い医療へのアクセス
6情報の共有によって、各医療機関が過去の検査や処方を把握してくれるため、同じ検査を二度以上受ける必要がなくなるぶん、医療費を削減できます。
また、先に解説した通り、医師から患者に対して提供される療養上のアドバイスをマイナポータルから閲覧することができる仕ようになるため、自身の健康状態をきちんと把握できるうえ、アドバイスに基づいて生活を改善することで健康状態の改善を目指せます。
さらに、電子カルテ情報共有サービスを通してカルテ情報を得ることによって、医療・介護サービスの費用対効果や質の評価に関して分析することも可能となります 。
参照:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスについて」「電子カルテ情報共有サービスの想定される主なメリットについて」
電子カルテ情報共有サービスの導入・運用方法は?
電子カルテ情報共有サービスの本格始動に向けて、各医療機関が準備すべきことは次の通りです。
システム業者に見積依頼・発注
電子カルテ情報共有サービスに対応した電子カルテシステム・端末等に改修するか、もしくは新規で標準化対応の電子カルテを導入して、電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境を整備します。
“電子カルテ情報共有サービスに対応”とはどういうことかというと、電子カルテを導入していても、その電子カルテが“標準化された電子カルテ”でなければ、医療機関間で情報を共有することができません。「電子カルテの標準化」とは、医療機関ごとに異なる電子カルテシステムのデータ形式や内容を統一させることです。
現状、政府が主導で標準型電子カルテの開発を進めており、2025年度以降に本格導入が予定されているので、そのタイミングで導入するのでもOKですし、各ベンダーの電子カルテを標準化に向けて改修するか、電子カルテの標準規格である「HL7 FHIR」に対応した電子カルテを導入する方法もあります。
HL7 FHIRとは
HL7 FHIRの「FHIR」とは、Fast Healthcare Interoperability Resourcesの頭文字を並べた言葉で、医療情報の電子的な交換と相互運用性を実現するための国際標準規格です。HL7(Health Level Seven International)は、FHIRを策定した米国の標準化団体で、HL7 FHIRには、最新のweb技術が活用されています。
参照:厚生労働省「HL7 FHIRに関する調査研究一式最終報告書」
補助金の申請・交付決定・入金
電子カルテ情報共有サービスの導入にあたって補助金を活用したい場合、電子カルテ情報共有サービスの利用申請をおこなう前に、補助金を申請する必要があります。
補助金申請には、システム事業者から受領した領収書などが必要です。補助金申請は「医療機関等向け総合ポータルサイト」からおこないます。
参照:医療機関等向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金」
なお、補助金の上限は次の通りです。
【健診実施医療機関の場合】(健診部門システム導入済の医療機関)
補助率および補助上限(共有する電子カルテ情報が3文書6情報)
| 大規模病院 (病床数200床以上) |
中小規模 (病床数20床~199床) |
|
| 補助内容 | 6,579千円を上限に補助 (事業額の13,158千円を上限にその1/2を補助) |
5,457千円を上限に補助 (事業額の10,913千円を上限にその1/2を補助) |
【健診未実施医療機関の場合】(健診部門システム未導入の医療機関)
補助率および補助上限(共有する電子カルテ情報が2文書6情報)※2文書=診療情報提供書、退院時サマリー
| 大規模病院 (病床数200床以上) |
中小規模 (病床数20床~199床) |
|
| 補助内容 | 5,081千円を上限に補助 (事業額の10,162千円を上限にその1/2を補助) |
4,085千円を上限に補助 (事業額の8,170千円を上限にその1/2を補助) |
参照:厚生労働省「医療提供体制設備整備交付金の実施について」
電子カルテ情報共有サービス利用申請
補助金の交付が決定後、入金を確認したら、電子カルテ情報共有サービス利用申請をおこないます。利用申請は「医療機関等向け総合ポータルサイト」からおこないます。利用申請においては、運用開始日も入力します。なお、運用開始日前に本番環境への接続が完了している必要があります。
参照:医療機関等向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの利用申請」
現場の運用準備
運用開始日が決まったら、その日に向けて、院内でどのように運用するかを固めていきます。患者導線を含む業務フローや、これまでのフローからの変更点などを確認していきます。また、電子カルテ情報共有サービスについて患者に広く周知するために、患者向け提示物を用意することも大切です。
参照:医療機関等向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの導入・運用方法」
電子カルテ情報共有サービスに対応するために、どのベンダーの電子カルテシステムを選べばいい?
前述の通り、電子カルテ情報共有サービスに対応するためには、対応可能な電子カルテシステムを導入するか、もしくは現在利用している電子カルテシステムおよび端末をシステム事業者に回収してもらう必要があります。
そのため、各ベンダーは対応を進めているため、現状、対応がまだのベンダーも近いうちに対応可能となると考えられます。
電子カルテ「CLIUS」は2025年9月末に対応予定です。
なお、8月21日時点で既に対応しているベンダーは次の通りです。
【中小規模病院向け】総合型電子カルテサービスPrimeKarte
【大中規模病院向け】「MegaOak/iS」
【病院・クリニック・精神科向け】「クラウドカルテblanc」
【一般病院向け・オンプレミス型】「MI・RA・Is V(ミライズ・ファイヴ)」
【BCP対策や訪問診療にも対応したクラウド型】「MI・RA・Is V for Cloud(ミライズ・ファイブ・フォー・クラウド)」
【小規模医療機関向け】「MI・RA・Is/QS(ミライズ/キューエス)」
【中規模医療機関向け】「MI・RA・Is/AZ」「MI・RA・Is/AZ for Cloud」
【病院向けクラウド型電子カルテ】「NewtonsLight」
【大中規模病院向け】「HOPE LifeMark-HX Cloud」
【大中規模病院向け】「HOPE LifeMark-HX」
【大中規模病院向け】「HOPE LifeMark-Type G」
【大中規模病院向け】「HOPE EGMAIN-GX」
【中堅病院向け】「HOPE Cloud Chart II」
【中堅病院向け】「HOPE LifeMark-MX」
【透析用】「総合透析支援システム DIABRAINS(ディアブレインズ)」
【無床診療所向けオンプレミス型】「BrainBoxV4」
【無床診療所向けクラウド型】「BrainBox CloudII」
【中小規模病院向け】「電子カルテシステムER」
参照:中小規模病院向け(電子カルテ)電子カルテシステムERの特長
参照:医療機関等向け総合ポータルサイト「本サービスに対応しているシステムベンダ」※上記一覧は2025.8.21時点の情報です
電子カルテ情報共有サービスに関するFAQ
続いては、電子カルテ情報共有サービスに関するよくある質問とその答えをみていきましょう。
Q. 電子カルテ情報共有サービスの導入は義務化されますか ?
電子カルテ情報共有サービスの導入は、2025年8月時点においては義務化されていません。
ただし、今後、導入が義務化されていく可能性は高いといえます。なぜかというと、政府は全国医療情報プラットフォームの実現に向けて、「医療DX令和ビジョン2030」において、2030年には概ねすべての医療機関で電子カルテの導入を実現するという目標を掲げているためです。
義務化はされていないが診療報酬には影響がある
電子カルテ情報共有サービスの導入は義務化されていませんが、導入しないととれる点数が低くなります。なぜかというと、2024年度診療報酬改定によって新設された「医療DX推進体制整備加算」では、2025年9月までに電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制が施設基準として定められているためです。
さらに、2026年度以降の診療報酬改定においては、見直しも考えられるため、早めに対応しておくことが得策であると考えられます。
参照:厚生労働省「医療DX推進体制整備加算等の要件の見直しについて」「医療DX推進体制整備加算等に関する課題と論点」
Q. 患者の同意はどのように取得するのですか?
基本的な同意取得の流れは次の通りです。
①患者への説明
まずは、次の4点について患者にきちんと説明することが不可欠です。
②同意の形式
同意の形式は、現状、原則として 口頭または書面による同意が想定されています。
ただし、実際の運用では、マイナンバーカードによる本人確認と同時に電子的に同意を記録する仕組みも導入されています(例:薬局や医療機関の窓口端末で同意確認)
③同意の記録・管理
患者が同意した日時、方法、説明内容をカルテや専用システムに記録します。同意は、「包括的同意」(医療機関間の情報連携に同意)として取得されることが多いですが、今後「部分的同意」(特定情報は共有しない)への対応も議論されています。
Q. 導入にあたって、セキュリティが不安ですが…… 。
電子カルテ情報共有サービスを活用するにあたっては、セキュリティ対策を講じることが必須です。
具体的にどのようなセキュリティ上の不安があるかというと次の通りです。
①不正アクセスや情報漏洩
②利用者認証の脆弱性
③データ通信の盗聴リスク
④内部不正
⑤システム障害や災害時の停止
これらに対して、実際に講じられている対策、講じるべき対策は次の通りです。
①強固な認証基盤
②暗号化通信
③アクセス制御・監査ログ
④厚労省のセキュリティ基準
⑤災害・障害対策
Q.電子カルテ情報共有サービス導入の補助金は、クリニックは申請できませんか?
クリニックが電子カルテ情報共有サービスを導入する場合、経済産業省の「IT導入補助金」を活用することが推奨されています 。
Q.導入後の現場の運用で特に注意すべき点は?
電子カルテ情報共有サービスを導入した後、スムーズに運用するために、以下の点に注意することが重要です。
①患者への同意取得フローの確立
受付での同意取得は、現場の負担になりがちです。患者にサービスの内容や情報共有の範囲を簡潔に説明できるよう、院内向けの簡単な説明マニュアルや同意取得のためのチェックリストを作成しておくとよいでしょう。
②共有情報の活用方法の明確化
医師や看護師が、共有された情報を日常の診療にどう活用するか、事前に運用ルールを定めておきましょう。たとえば、「初診の患者は、必ず電子カルテ情報共有サービスで過去の処方やアレルギー情報を確認する」といったルールを設けることで、より安全で効率的な診療を実現できます。
Q. どのような場合に情報が共有されるのですか?
電子カルテ情報共有サービスは、患者のプライバシーを保護するために、情報共有の範囲や条件が厳しく管理されています。具体的には、次の条件が満たされた場合にのみ、情報が共有されます。
1. 患者がマイナ保険証を利用する
医療機関の窓口でマイナンバーカードを健康保険証として利用して、本人確認をおこなう必要があります。
2. 患者が情報提供に同意する
マイナ保険証の顔認証付きカードリーダーで「情報提供に同意する」と意思表示した場合に限り、情報が共有されます。
3. 情報が共有されるのは、患者が過去に診療を受けた医療機関の情報に限定される
「すべての情報が無条件に共有されるわけではない」という点を、医療従事者や患者は理解しておく必要があります。
医療DX推進の全体像は?
前半で述べた通り、電子カルテ共有サービスとは、医療DXを進めるうえでの骨子となる取り組みである「全国医療情報プラットフォーム」の仕組みの一つです。
では、医療DX推進のための取り組みの全体像はというと、全国医療情報プラットフォームを含む5つの主要な取り組みで構成されています。
具体的には、次の5つの取り組みです。
①マイナ保険証への移行
②全国医療情報プラットフォーム構築
③電子カルテ情報の標準化
④診療報酬改定DX
⑤社会保険診療報酬支払基金の改組
参照:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスについて」「医療DXの推進に関する工程表(概要)」
また、2025年度に実施が予定されていることのうち、医療現場と関係しているものは次の4つ です。
①電子処方箋の導入100%達成
②3文書6情報の共有開始
③標準型電子カルテα版の提供開始
④共通算定モジュールα版の提供開始
つまり、各医療機関は、電子カルテ情報共有サービス導入の準備を進めると同時に、これらについても理解を深めていくことが大切だということです。
医療DX周りは、とにかくスピーディに対応していくことがおすすめ
デジタルへの苦手意識が強いと、「医療DXへの対応はなるべく後回しにしたい」と対応を後手後手にしがちです。しかし、対応が遅くなると、「補助金申請が締め切られる「義務化されることになり、結果的に対応を急かされる」「やらなければならないことが他にも増えてきて手が回らなくなる」といった事態にも陥りかねません。そうなるのを防ぐためにも、できるだけスピーディに対応していくことがおすすめです。また、そうすることによって、たとえば医療機関間との情報共有がスムーズになるなど、できることがどんどん増えていくので、医療機関として大きく成長するためにも、早め早めの行動を心がけてくださいね。まずは、自院の電子カルテベンダーに、電子カルテ情報共有サービスへの対応状況を確認してみましょう。
特徴
オンライン診療機能
システム提携
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。





